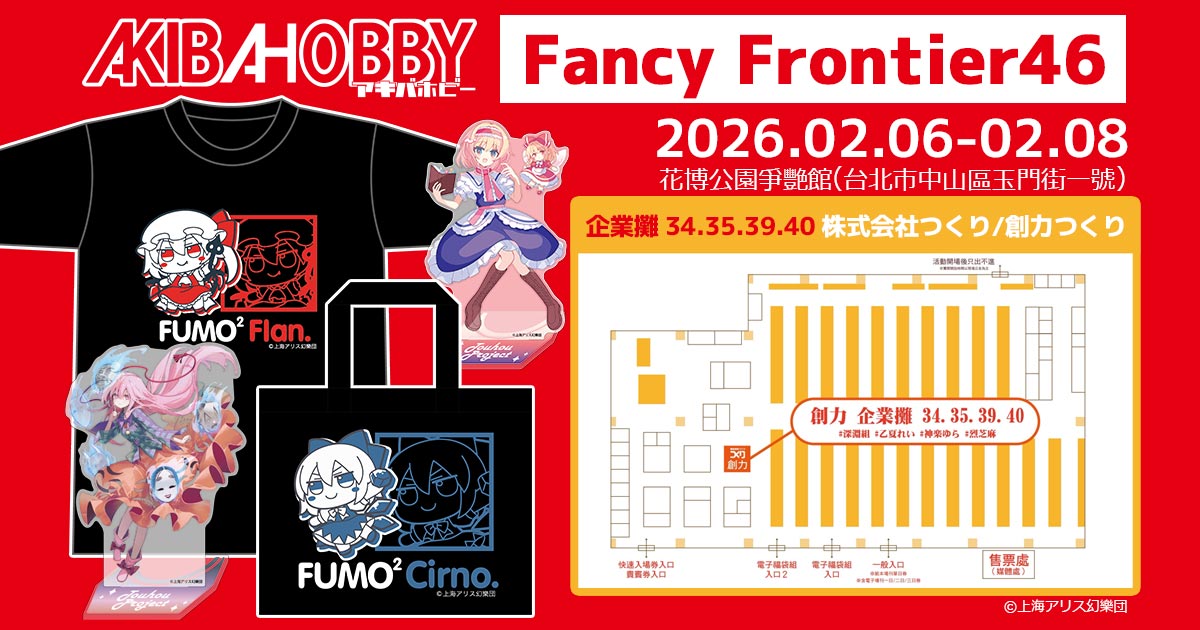【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第60回 陽動】
時折鳴り響く汽笛の音が、地下空間に木霊し消えていく。
冷ややかな空気の中を進む列車の内部では、走行に合わせて天井から吊り下げられた灯りがふらふらと揺れ、その動きへ呼応するように明滅している。
地獄の炎を燈したそれは狭いガラスの中に閉じ込められ、物悲しい輝きを放っていた。
薄明かりに照らされる車内には地上から戻った亡霊たちが乗せられていた。誰ひとりとして言葉を発しない。というよりも発せなかった。
彼女たちの霊格では、残念ながらそこまでの知性を取り戻すことはできなかったのだ。
人として生まれ、短い時を生きて死んでいくからこそ得られる、命の輝き。
ひとたび朽ちれば輪廻の環に戻り、また新たな生を待つ定めを受け入れられなかったがゆえ、彼らはただどうしてそう考えるのかもわからなくなってしまった執念――“故郷へ帰りたい”という想いだけを抱えて戦っている。
狂おしいまでの願いにもかかわらず、それがどこから湧き上がってくるかもわからなくなってしまった虚しさからだろうか。
ある者は床に腰を下ろして視線を虚空にさまよわせ、またある者は床の一点を所在なく見つめていた。
そこへ突然、轟音と金属のひしゃげる音が生まれた。
「……!?」
一拍遅れて集まる亡霊たちの視線。その先では後尾車両に連結されている壁面が、外側から内側へ大きくへこんでいた。
「…………」
「……?」
亡霊たちは互いに顔を見合わせ、小首を傾げたりしている。これもまた知性が限られているがゆえの弊害だった。
何か重たいものが偶然衝突したのだろうか。それにしては妙な形だった。まるで何者かが拳で殴りつけた跡のような――
ふたたび轟音。それも立て続けだった。困惑で動けないままでいる亡霊たちの前で壁はどんどん形を歪ませていく。
「…………!!」
事ここに及んでは亡霊たちも警戒態勢に移行する。さすがに只事ではないと気付いたのだ。
彼女たちが様子を窺っている中、いよいよ叩きつけられる衝撃に耐えられなくなった壁が、金属の軋む悲鳴のような断末魔と共に大きく破れ、人間の頭くらいの穴が開く。
そこからは――内部の者たちへ存在を誇示するように、握られたままの拳が突き出されていた。
「なんだい辛気臭い場所だねえ。葬式みたいな空気じゃないか」
破断した部分を掴み、鉄でできた壁を粘土細工のようにこじ開けて貨車内へ入ってきたのはひとりの鬼――星熊勇儀だった。
「いや、そいつらみんな死んでいるから。ていうか、こんな暗くて見えるのかい?」
冷静なツッコミが背後で様子を見守っていた小町から放たれた。
素手で壁をぶち抜くような非常識さを見せつけられ、言葉が出てこなかったのは内緒だ。
「愚問だな、わたしらは地下の妖怪だよ? 夜目が利かなかったらどうしようもないじゃないか。あんたこそ大丈夫なのか?」
「こっちも同じだね。死神は夜こそ我が領域……って言うと吸血鬼みたいだな。まぁ昼夜問わず活動するけど、本来は夜の眷属だし問題ないよ」
一瞬ドヤりかけた小町だが、すぐに正気に戻ったのか気恥ずかしそうに言い直した。
「死神が勇儀さんと対等に口を聞くなんて妬ましい妬ましい……」
ふたりのやり取りを眺めるパルスィはどこまでもブレなかった。
「あんた誰にでもそんな感じなのかい?」
居心地の悪い嫉妬の視線を受け、小町は呆れたように問いかけた。そんなに妬ましいならもっと積極的に会話に入ってくればいいのにと小町は思ってしまう。
「誰にでもだなんて。そんなに喋る相手がいると考えられるくらい知り合いが多いのね。妬ま――」
「めんどくさいねぇその性格。じゃあさ、あたいが友達になってやるよ!」
「――は?」
まだるっこしくなってきた小町が提案し、パルスィが大きく目を見開いて固まった。
「さっきの妖夢とにとりも多分友達になってくれるさ。全部落ち着いたら話してみなよ。いいやつらだから」
呆然としているパルスィには気付かず、小町は思いつくままに話を進めていく。
橋姫としての性質上、妬みをぶつけずにはいられないが、そうすればまた相手から鬱陶しいと思われる。今度もきっとそうだ。そんなもどかしさを抱えていたパルスィは、予想外の事態に思考が完全に停止していた。
「ど、ど、ど、ど、な、な、な、な、わわわわたしがそそそそんなこここととででで」
「なんだい、今度は変な方向でめんどくさくなっちまったな」
壊れた通信機のように同じ音を繰り返さなければいけなくなってしまったパルスィ。小町は助けを求めるように勇儀を向いた。
「はっはっは! こいつは傑作だ!」
一方、勇儀はさも愉快そうに腹を抱えて笑っていた。こんな状況だというのに、左手に持った酒杯の酒を時折舐めている始末だ。
「笑ってないで畳んじまうよ。荷車はここ含め全部で5つもあるんだ、妖夢たちに矛先が向かないとも限らない」
ほんの少し前まで漂っていた寂寥感は、闖入者たちによって妙な方向へと変えられていた。もしかすると、これが生ある者の命の輝きなのかもしれない。――おそらくは。
「わーってるって。さてと待たせちまったね」
あらためて勇儀は小さく肩を鳴らすと、行く手を塞ぐ亡霊たちに視線を向けた。
「……!!」
すでに臨戦態勢となった勇儀からは圧力が放射されはじめていた。味方でさえパルスィの嫉妬心とは別次元の居心地の悪さを感じるほどだ。
押し寄せる鬼気を受け、困惑混じりに様子を眺めていた亡霊たちも続々と立ち上げり各々の武器を構えていく。
ようやく乗り込んできた者たちが排除すべき敵であると認識したためだ。
「……?」
困惑の気配が亡霊たちから無意識に漏れ出た。
ほんのすこしの動作で先制攻撃できるにもかかわらず、今の今まで亡霊たちは自らが動けないでいたことに気付いた。しかも、殺人を手軽なものにまで昇華せしめた近代火器を構えながらだ。
そう、“人でなし”となった彼女たちは先ほどから自分たちを支配している感情を自覚できないでいた。それが圧倒的な存在を前にした恐怖であることに。
「動けないかい? 戦う気になった鬼を前にしたら無理もない」
勇儀は挑発するようにゆっくりと一歩を踏み出した。依然として亡霊たちは引き金を引けないでいる。
しかし――時に恐怖は狂気によって塗りつぶされる。この場合は執念と呼ぶべきか。
互いの間に漂っていた緊張感はいつしか消え失せ、元の冷えた空気を感じられるようになっていた。
列車が地下の澱んだ風を切りながら進んでいく中、車輪がレールの継ぎ目に接触する音が断続的に聞こえてくる。まるで機能を喪失してしまった亡霊たちの心音を表しているようだった。
「実力差がわかっていてもやるってのか。いいねぇ、往生際が悪いのは嫌いじゃない。だけど、あんたらの戦いはここで終わりだ」
勇儀はそっと体勢を変え、片方の拳を軽く突き出すようにして構えた。言葉を交わせない亡霊たちに対する彼女なりの礼儀として。
次の瞬間、勇儀の姿は搔き消えた。一拍遅れて床が下駄の歯の形にへこんでいた。
「悪いがその妙な武器は通じないよ。あんたらの得物は超至近距離に持ち込まれたら途端に扱い辛いものになる」
次に放たれた言葉は亡霊たちの真っ只中からだった。
ぎょっとしたように彼女たちの銃口が一斉に動くが、その時にはすでに人の形をした暴風が生まれていた。
もっとも不幸だったのは繰り出された右拳の直撃――いや、激突を受けた者だった。
打撃を受けた亡霊の全身が衝撃波に震えた。肉が押し潰され、筋肉の繊維はバラバラになり、骨は砕けて内臓に突き刺さる。亡霊とはいえ人間大の質量が宙を舞い、壁にめり込んで動かなくなった。
「わーお……」
これが鬼の膂力かと小町が呻いた。
勇儀の全力であれば肉体が破裂していたかもしれない。
仲間の惨状を目の当たりにしながらも、亡霊たちは侵入者を食い止めようと引き金を絞る。いかに鬼とはいえ鉛弾を至近距離から浴びて平気ではいられないはずだ。
しかし、勇儀は驚くべき戦いの勘でそれに対応してのけた。
自身に向けられる銃口の中でもっとも脅威度の高いものを瞬時に見抜き、拳を振り抜いた姿勢のまま酒杯を持つ左手の中指だけでそっと動かしてみせた。
強引に逸らされたPPSh-41銃口は、導かれるままに味方の肉体へと次々に銃弾を叩きこむ。
おそろしいのはここからだった。着弾の衝撃で今度は銃撃を受けた亡霊が意図せぬ方向へ銃火を迸らせ、それが連鎖的に被害を拡大させていく。
一瞬で周囲の敵を蹴散らした勇儀は、勢いに乗ったまま奥へ向かい足を踏み出す。亡霊たちも抵抗を試みるが、桁違いの突破力に彼女たちはなす術もなく壁や床に叩きつけられる。
ただ腕や足が振られただけだ。にもかかわらず、その一撃だけで全身の骨を容赦なく砕かれる。尋常ではない威力だった。
物語の悪鬼羅刹が実在するならば、それは彼女のような――――いや違う。彼女こそが正真正銘の“鬼”だった。
「悪くはないけど、いまいち歯応えがないねぇ!」
「これで酒を零さないために加減をしてるなんて、タチの悪い冗談だよ!」
小町もまた狭い貨車の中で空間を渡りつつ、大鎌を振るって邪魔にならないよう亡霊たちを仕留めていく。
「そうかい? 力押しだけで解決させようとすると張り合いがなくてね!」
「今回ばかりはあんま気にしないでほしいもんだ!」
亡霊の急襲を回避し、背後に回り込みながら鎌を旋回させ小町は叫んだ。
「そいつは無理な相談だ」
鈍い音が上がった。亡霊がまたひとり、全身を破壊され床へ沈められる。
「なにせ、わたしは鬼だからね」
凄惨さを感じつつも、どこか色気のある笑みで勇儀は答えた。それを見ているとなんだか小町としても頼もしくなってくるから不思議だった。
不意に勇儀の表情が鋭くなる。
亡霊たちの垣根の中へ視線を向けると、そこから突進してくる者がいた。
硬質のもの同士がぶつかる音が響き渡った。颶風のように突き込まれた銃剣を、腕の動き――はめられた枷で刃を弾くようにいなした勇儀が、襲撃者へ向けて獰猛な笑みを浮かべた。
「へぇ、あんたは動きが違うねぇ!」
対する亡霊は表情を動かさず、さらに踏み込んできた。短機関銃の銃火にも劣らない速度の刺突が連続して襲い掛かる。
「こりゃいい! 楽しめそうだ!」
「コ、コは……我が、部隊ノ……守りシ場所……。先ヘハ……進マ……せヌ……」
抑揚を欠いた掠れたものながらも、亡霊――部隊長の声には鼓膜を揺さぶるような覇気があった。
そして、その覇気は次なる攻撃となって放たれる。
円を描くように滑らかに動く勇儀の腕は、高速で叩きこまれる刃の軌道を逸らして無効化。
亡霊は踏み止まろうとするも鬼の前進を止められない。それでも死角を狙った蹴りを送り込んでその歩みを止めんと食らいつく。
「うへぇ、あんな中に奇襲でも加われるかい!」
勇儀の大立ち回りを、入って来る時に使った穴の向こう側から小町は眺めていた。
雑兵はまだ残っているが、それぞれ主役同士に戦いを委ねる流れのようなので、小休止させてもらっているのだ。適格にサボるタイミングを見つけられるあたりが実に彼女らしい。
「思ったより取り回しが悪いのね、その鎌」
同じく飛び交う銃弾を避けるように隠れていたパルスィが語り掛けてきた。主戦場はすっかり向こうに移ってしまったので手持ち無沙汰なのだろうか。
「こんな狭いところだとな。ええと、パルスィだっけ? いかにも肉弾戦は得意じゃなさそうだけど、何か特技はあんのかい?」
「え、う、うん。一番得意なのは嫉妬を操ることで……でも亡霊には効かないから、こっちがいけるかも――」
パルスィが腕を掲げ、思念を送り込むように何かを呟いた。
次の瞬間、仲間を援護するタイミングを見計らっていた亡霊たちの銃の部品が突如として脱落。一斉に地面を叩き金属の乾いた音の多重奏を引き起こしていく。
「なかなかやるじゃないか。まさかこの状況にぴったりの技を持ってるとはねぇ」
「うう、地味すぎる。もっと華々しい技がないのが妬ましい妬ましい……」
パルスィから上がるのは相も変わらず妬みの声だった。小町の賞賛を素直に受け止められないようだ。
「誰が妬ましいのさ、言ってることめちゃくちゃだよ。間違いなく役立ってるから贅沢言うもんじゃない」
「そ、そうかな。へへへ」
観客のいない戦場の片隅でちょっとした漫才繰り広げられている間に、戦いは決着を迎えようとしていた。
空気を押しのけて突き出される勇儀の拳。唸りを上げ衝撃波を撒き散らし、射線上の敵を吹き飛ばそうとする。
跳ね上がったKar98kの銃身が盾となり、火花を散らしながら打撃を逸らしていくが、すべては受け流せず部隊長の膝が床へ落ちる。
好機か。
見守っていた小町は叫びかけた。
――否。防御しながらも部隊長は間隙を縫うように伸ばされた腕の内側へ侵入していた。
右手で操る銃剣付のライフルで巧みに防御しながら、部隊長は残る手で予備の銃剣を抜いていた。
下から斜めに走った刃を、勇儀は左手の枷で受け止めた。渾身の一撃を受けても、左手の酒杯からは一滴の酒も零れていない。
「ナん……ト……」
策が不発に終わった部隊長の瞳が驚愕に見開かれる中、戻って来た右腕の鎖が彼女の首に絡みついた。
「いい戦いだったよ」
勇儀が短く告げ、身体ごと大きく回転。勢いのままに部隊長は床へ叩きつけられ轟音が上がる。人の形にめり込んだ床の中で、彼女はすでに動くことすらできなくなっていた。
「さぁ、片付いた。次に行こうか」
空いた腕を軽く回し、次なる戦いを求め前の車輌への扉に拳を打ち付けた。
それを見ていた小町が口を開く。
「なぁ。それさっきも思ったんだけど、多分引き戸だよ」