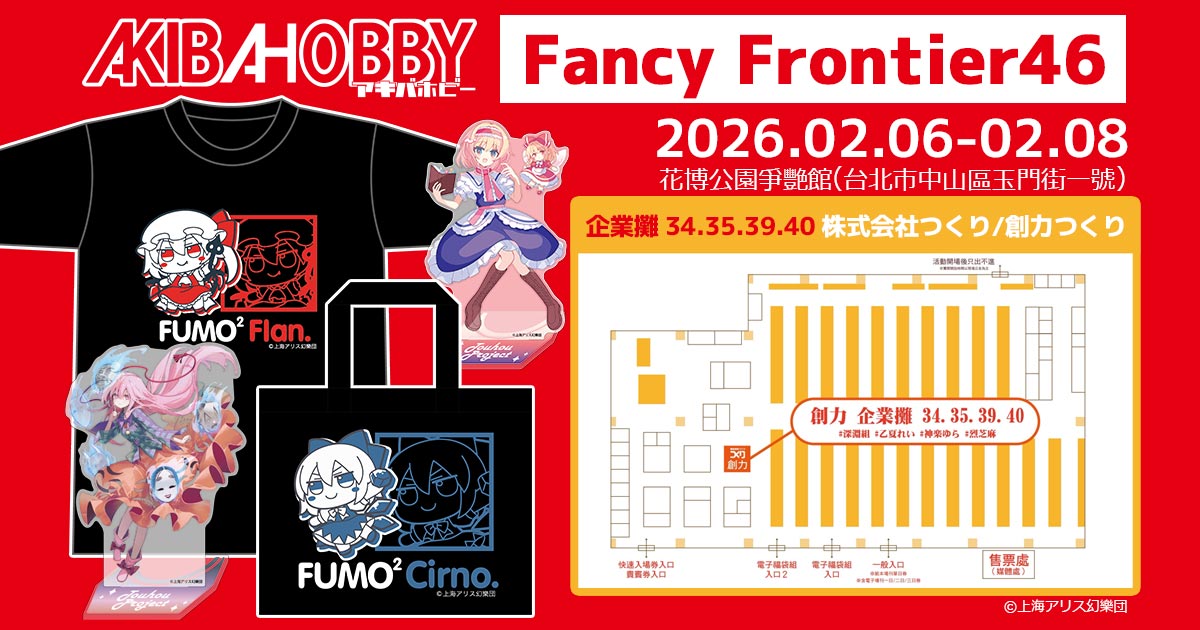【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第36話 龍虎】
「パチュリー・ノーレッジ……」
森の奥から近づいて来る魔女一行に視線を送りながら、妖夢が呟いた。と同時に、いつでも動けるよう背負った刀の柄の在り処を意識する。
この局面で現れたとなれば、偶然にしてはあまりにもできすぎている。いかに見知った存在であろうと、妖夢としては警戒せずにいられなかった。
ましてパチュリーは単身ではなく、紅魔館の面子を伴っている。最も厄介な存在である吸血鬼、フランドール姉妹の姿こそないが、それでもここで一戦交えるとなれば油断していい相手ではなかった。
「そう警戒しないでちょうだい。ここに来たのは単なる偶然よ」
特段表情を動かすことなく、パチュリーは言葉を発した。
言葉に抑揚がなく、ピリピリしている妖夢たちからすればこれがまた実に怪しく感じられる。
「じゃあ、なんで離れた場所からこっちの会話が聞こえてるんだい。そんなんで偶然なんて言われても白々しいようにしか感じられないよ」
一行の内心を代弁するように、小町が胡乱な視線を闖入者へと向けた。
妖夢ほどではないが、彼女もまた油断なく表情をわずかながらに引き締め、目立たないよう大鎌の柄に手を這わせている。ここまで来て油断から足をすくわれるような目には遭いたくないのだろう。
(辻斬りの方はともかくとして、サボりの死神までこんな剣呑な空気を纏うってどういうことかしら。いつぞや起きた、精神に影響を及ぼすような異変ではないみたいだけど……)
パチュリーはわずかに眉根を寄せ、内心で訝しんだ。
何も彼女の反応が見当違いなのではない。普段の幻想郷――――弾幕ごっこで決着する状況下であれば、間違いなく妖夢たちの反応は行き過ぎなものだ。
ところが、妖夢たちにとって、今はかつてないほどの非常時であり、これまで潜り抜けてきた戦いの記憶が彼女らの感覚を否応なしに鋭敏なものへ変えていた。
「べつに盗み聞きしたつもりはないのだけれど。本を集中して読みたいときは静かな環境で読みたいでしょう? 単純にその逆もあり得るというだけだわ」
ふたりから向けられる警戒の視線を受けてもパチュリーは涼しい顔のまま答えた。
こういうぶっきらぼうなところがいけないんだろうなぁと傍で控える美鈴は思う。誤解を解きたいのであれば、それなりの態度というものがある。
「え、じゃあなんですか? 今までも聞こえてなかったんじゃなくて、意図してシャットアウトしてたんですか……。ひどいなぁ……」
パチュリーの後ろで小さく眉を顰める小悪魔。自身の発言が思わぬところに飛び火したことで味方からの後ろ弾を受けたパチュリーは、少しだけばつの悪そうな顔を浮かべた。
「……それは置いておいて。何度も言うけど、こちらに敵対する意思はないわ。なんだか愉快なことに首を突っ込んでいそうだからつい口を挟んでしまっただけよ」
釈明にしては端的なもの言いすぎた。特に興味はないとでも言わんばかりの言葉が、聞いている妖夢たちの神経を微妙に逆撫でする。
事件に巻き込まれている側が、部外者から無責任な発言を浴びせられると、ここまで苛立ちを覚えるものなのか。今後は異変を解決に向かう巫女を見てもあまり刺激しないようにしようと、おそらく今だけになるだろうが妖夢たちは固く心に誓うのだった。
「そうだ。あなた、先ほど湖の敵を放置していくのは推奨しないと言っていましたよね? 具体的に、何がまずいと言うんですか?」
よくよく考えてみれば、パチュリーは“動かない大図書館”として知られており、前半部はともかくとしての後半部の異名に違わぬ豊富な知識を持っているはずだ。
いつぞや月を目指したロケットのように独自解釈で厳密には間違っているケースがないとも言えないが、“識者の意見”として聞くだけならタダである。
「さっきから聞こえてくる得体の知れないこの音。どうも、そこの河童には心当たりがあるようね」
「……まぁね」
質問に質問で返す形、しかも矛先まで変えられ、間接的に無視された妖夢は憮然とした表情となった。それに気づいたにとりも、迂遠な物言いをされたためか素っ気ない言葉を返す。
「あなたたちは気付いていないようだけど、湖の物とは別でもうひとつ、厄介なやつが館を狙っているみたいなの。そっちはさっきわたしたちが遭遇した――――」
事のあらましを説明しようとしたところで、妖夢と美鈴がほぼ同時に手を掲げパチュリーの言葉を途中で止めた。何事かと問いかけようとしたにとりも、すぐに彼女たちの浮かべる表情で事態を把握。ティーガーⅡのハッチへと戻る。
「どうやら撒いてはいなかったみたいですね」
忌々しげにつぶやいた美鈴に、パチュリーも苦い顔で頷く。
「……わたしとしたことが迂闊だったわ。斥候くらい送り出してくると予想して然るべきだった」
(慣れない運動で思考のためのリソースまで浪費していただけでは?)
余計なことを口にして上司の期限を損ねても面倒なので、流し目の視線を送るにとどめる小悪魔。
「なるほど、余計なお客を連れてきてくれたわけですか」
楼観剣を抜いた妖夢が、森の中へと鋭い視線を送りつつ毒づいた。どこかパチュリーを揶揄するような含みがあった。
「敵の数は多くない。ここはわたしが片付けます」
「待って。あなた、あの亡霊を倒せるっていうの?」
今度は興味を覚えたのか、パチュリーのほうから話しかけてきた。それなりにわかっていたが勝手なものである。
「ええ。どういう巡り合わせかわかりませんがね」
敵が迫っている中、まともに応対している暇もないため短く答え、妖夢は森の中へ向かって疾走を開始する。
「わたしも手伝います!」
声と共に背後から美鈴が追随してきた。ここで「待ってくれ」と言ってこないあたり、戦い方を心得ている。これなら共闘するうえでの不安もない。
「わかりました! でも、無理に倒そうとしないでください! 敵の始末はこちらの役目、行動力を奪ってくれるだけで構いません!」
「承知です!」
打てば響くとはこのことだろうか。美鈴は妖夢の指示に従うと決めたらしい。
千の理屈を並べるよりも一つの言葉と態度で表したほうが話は早い時もある。武に関わる者には往々にしてそういうところがあった。決して難しいことを考えられない脳筋だからではない。
「左側は任せました!」
先ほどパチュリーが口にした内容からすでに亡霊との遭遇および戦闘は経ているものとして、銃火器に対する警告は出さない。
「はい!」
森の中に潜む亡霊たちへと並走して接近する妖夢と美鈴は、示し合わせたようなタイミングで同時に左右へ飛ぶ。間髪容れず銃声が鳴り響き、直前までふたりがいた場所を弾丸の群れが風切り音を残し通り過ぎていく。
速度に乗ったふたりはすでに弾丸からは遠く、そして自身の間合いへ達するまでに距離を詰めていた。
斥候ともなれば亡霊の中でも手練れなのか、銃撃を止めて高速で腰の短剣に手を伸ばす。
しかし、その時には間合いへと入り込んでいた美鈴の足が鞭のように伸びていた。
跳ね上がった足はあばら部分へと突き刺さるように直撃。込められた衝撃によって亡霊の身体が瞬間的に浮かび上がる。
つま先を通じて伝わってくる筋肉が軋む鈍い感触。続いて上がったのは肋骨をへし折る音だった。
「ご、ぶっ……!」
亡霊の口腔から空気の漏れるくぐもった音と共にどす黒い血が噴き出す。折れた肋骨が肺に突き刺さったのだ。
「よし、いける……!」
地面に膝をついて動きの止まった亡霊を無視し、美鈴は確かな手応えを引き連れて次の相手へ向かう。
「ふっ!」
大地を蹴った勢いのまま次なる敵の懐へと潜り込み、“気”を纏わせた掌底を胸部へと叩きこむ。
掌底に生じる衝撃と、目の前で後方目がけて吹き飛んでいく亡霊。その先にあるのは太い木の幹だった。人間ひとりぶんの全力突進を受けることになった木は、衝撃に大きく揺れ耐えきれなかった葉がひらひらと舞い落ちてくる。
「あら、ちょっとやり過ぎましたかね?」
とぼけたように嘯く美鈴だったが、その瞳には鋭い狩人の光が宿っていた。
そう、美鈴とて日々太極拳を舞ったり、居眠りをしたりするついでに門番をしているわけではない。
元々身体能力の高い妖怪でありながら武術を修得しているように、彼女は先ほどの交戦で得た経験から、次に亡霊と遭遇した際、どのように戦うかを脳内で予行演習していたのだ。
仮初の肉体を得て実体化した亡霊を相手に、中途半端な攻撃ではダメージを与えようとしても対生者ほどの効果は得られないが、それでも人型であるがゆえの弱点は確実に存在している。
当然ながら、足を失えば歩けなくなるし、腕を失えば武器とて操ることもできなくなる。これは間違いない。
亡霊でいるためには人間であった時の想いは捨てられず、それゆえに逃れることのできない呪縛でもあった。
「むっ」
刀を振り回す敵よりも与しやすいと判断したか、亡霊たちは妖夢よりも先に美鈴を倒すべく左右から同時に襲い掛かってきた。
いや、確実に葬り去るための手段に出ようとした。
一体が美鈴の蹴りで吹き飛ばされた瞬間、重心を低くした姿勢で武器を捨てて突進を仕掛け、そのまま抱き着くように抑え込んでくる。
「くっ、この! なにをするつもりですか!」
引きはがそうとする美鈴。腰にしがみついた亡霊は彼女を見上げ――――“嗤った”。
それは生者への羨望であり、そして自分たちの場所へと引っ張り込もうとする怨念が作り出した表情であった。
回された手には鈍く黒光りする果実にも似た鉄塊、F1手榴弾が握られていた。
「は、な、し、な――――」
抵抗むなしく手榴弾のピンが引き抜かれようとした瞬間、亡霊の頭部に飛来した短刀が深々と突き刺さる。無念の表情を浮かべたまま青白い粒子へ還っていった。
「美鈴! まだ残っていますよ!」
鋭い叫びが投げられた時には美鈴もまた動いていた。
向き直った先には、味方の失敗に気付き腰だめに構えた短剣を抱え込むようにして肉薄してくる亡霊の姿。もちろん、その程度では彼女を止めることなどできはしない。
「お仲間の分まで……喰らいなさい!」
唸りを上げて放たれた回し蹴りが亡霊の顔面を直撃。完全に力負けした死者の身体は、蹴られた毬のように猛烈な勢いで吹き飛んでいく。
「まったく……こっちに寄越さないでくださいよ……」
飛ばされた先にあったのは、この短時間で亡霊をすべて片付けた少女の姿だった。
風を切るように鋭く翻った長刀の刃が、なす術もない亡霊兵の胸部を斜めに両断。断面から吹き出す血飛沫が空気中に撒き散らされる。
「妖夢さん、これを!」
美鈴から投げられた白楼剣を受け取りながら一閃。
亡霊の身体から漏れる血の霧は青白い光の粒子へと変わり、その根本である肉体もまた同じように実体を失い消滅していく。
あとに残されたものは亡霊が背負っていたライフルのみ。偶然だろうか、地面へとほぼ垂直に突き刺さった銃は、まるで墓標を表すかのようであった。
「さて、これで片付きましたかね」
すべての迷いを断つかのように刀身を振るい、刃を腰の鞘へと収めた妖夢が辺りを見渡しながらそっとつぶやいた。