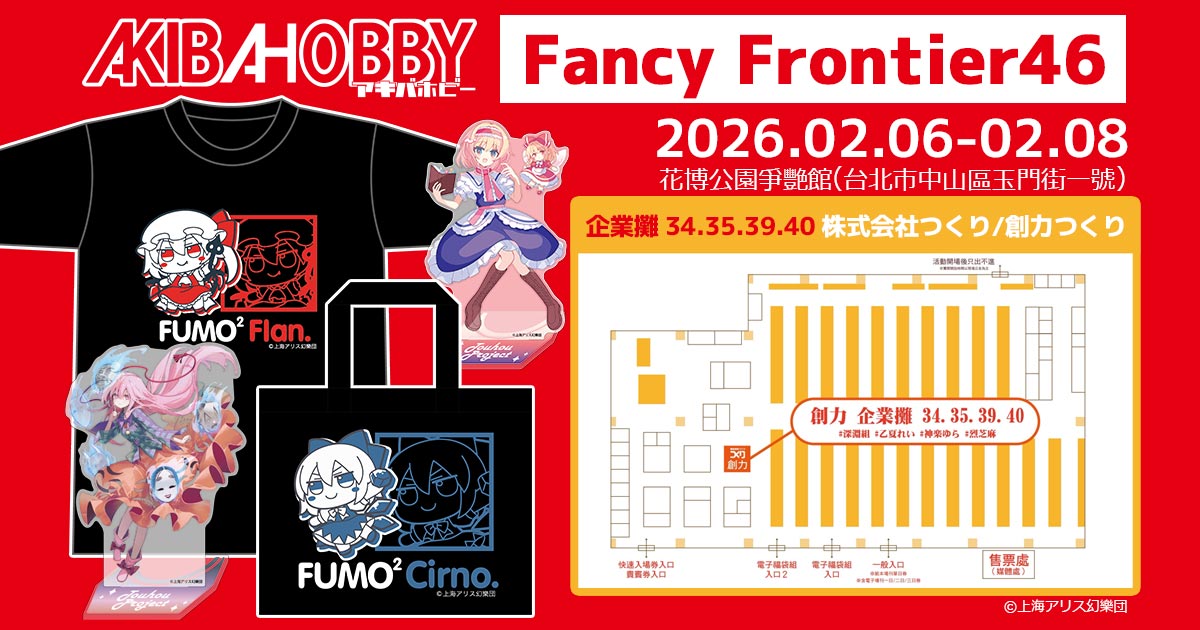【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第34回 虎口】
閃光に一瞬遅れて生じた轟音と、それに伴う強烈な爆発によって大量の土砂が巻き上げられ、驟雨のようにあたりへと降り注いだ。
上空から重力に引かれて落ちてくる土砂がティーガーⅡの上面装甲を叩く。もちろん、この程度で損害を負うことなどないが、中にいる乗員たちの精神には大変よろしくない。
「こ、今度は何です……!?」
コマンダーキューポラの視察口越しに外部の様子を見る妖夢から震え交じりの声が漏れる。
タイミング良く戦車の内部へ戻っていたから良かったようなものだが、そうでなければ爆風でどこかしらやられていたかもしれない。そもそも、直撃していればこの戦車ですら無事であったかどうか。
「まさか妖怪の山が噴火でもしたってのかい? 妖夢、外の様子は!?」
「わかりません! とにかく粉塵がすごくて……」
一刻も早く様子を知りたいが、これではハッチを開けても同じであろう。また同じ爆発が起こらないとも限らないのに、生身のまま出て行く無謀さはさすがの妖夢も持ち合わせていない。
「いったん森の中に引っ込むよ! 身を隠さないと!」
皆が混乱状態に陥りかける中、操縦手であるにとりの判断は迅速だった。すぐさま車体を全力で動かし、森の中へと引っ込んでいく。
どこから攻撃を受けたのかまるでわからない以上、被視認性を下げようとするのは間違いなく有効な戦法だ。彼女のように兵器に対する予備知識がなければ、そこには気付けなかったかもしれない。
そして、この咄嗟の判断こそが“戦場”において生死を分ける。
「にとり、もしかして今の攻撃が何かわかったんですか!?」
「たぶんね……。こんな芸当ができるヤツは幻想郷の住人だと限られてる。しかも、問答無用ってんだから十中八九敵の攻撃だよ。火山の噴火だったらこんなもんじゃな――――」
ふたたび付近で生じた轟音と爆発がにとりの言葉を遮る。先ほどと比べて幾分か小さく感じるのは爆心地が遠のいているからだろうか。
しかし……と妖夢は訝しむ。
すくなくとも付近――――目に見えた範囲でこれほどの破壊力を持つ攻撃をしてきそうな敵は存在していなかった。ティーガーⅡの装甲越しでもわかる威力は、何回か体感した戦車砲とは比べ物にならない。
「湖に出ている霧の向こう側、そこに何かいるんだよ。狙いはわたしたちか、さっきのT-34の砲炎を見て当たりをつけた牽制射撃か……」
目の前に広がっている湖には、昼間はその名の通り霧が立ち込め視界が悪い。この場所には妖精や妖怪が集まりやすく、特に夏は水場を求めて多くの妖怪が集まることで知られているが、何者かが潜む今ではその気配がまるで感じられない。
実際、チルノでさえ住処の湖を離れているのだ。この爆音の影響を受けているのは間違いなかった。
「破壊の規模から考えると結構な大物がいそうな気がするんだけど、そんなものが今回の異変で流れ着いているなんてのはね……」
にとりには見えない敵の見当がついているらしいが、どうも納得がいかないようだ。
湖の正確な広さは誰も知らないが、それほどの大きさではなかったと妖夢は記憶している。
いや、それよりも妖夢には気になることがあった。あるいは、たった今思い出したとも言う。
「ところで、外にいるチルノは大丈夫なんですか……?」
「「「あっ」」」
皆すっかり忘れていたらしい。あれだけ頼み込んで協力を請うておきながらなんとも薄情なものだった。とはいえ、いきなり正体不明の攻撃を受ければこうもなる。
「わ、わたしが探してきます!」
「あ、妖夢。エンジンのとこにはいないかもしれないよ! さっきから温度が上がってきてるし」
すでに謎の攻撃が遠ざかっていったこともあって、妖夢はにとりの「早く冷却装置を見つけてきてね」とも取れる言葉を受けながら、おそるおそるハッチを開けて外へと出て行く。
やはりエンジンルームの真上にチルノはいなかった。
「ま、まさかとは思いますけど、戦車に巻き込まれたりしてないですよね……?」
一瞬、不吉な考えが妖夢の脳裏に浮かび、視線をさまよわせるかどうか躊躇してしまう。
亡霊相手ならいざ知らず、いくらなんでも見知った顔が履帯に巻き込まれて潰れたカエルのように、あるいは先ほどの爆発に巻き込まれて見るも無残になった姿など見たくはなかった。
「も~、いったいなんなのよ、この爆発は!」
最悪の事態を想定しながら覚悟を決めた妖夢の耳に、聞き覚えのある声が飛び込んでくる。
視線を向けると森の木々の向こう側から、チルノがこちらへ向かってふらふらと飛んでくるところだった。
「無事だったんですか、チルノ!」
近寄って見たところ特に傷などはない。だが、大量に巻き上げられた土砂を浴びたらしく、彼女の服はところどころ汚れていた。
「はぁ……。さいきょーのあたいもさすがに今回ばかりは死んじゃうかと思ったわ……」
ぼさぼさになった髪もそのままにチルノは肩で息をしていたが、特に異常らしきものは見受けられなかった。
第1次世界大戦のような大規模な戦いでは、爆音を伴う砲撃によってシェル・ショックとも呼ばれる戦争後遺症を発したりするのだが、どうも妖精だからかはたまた別の理由なのか案外けろっとしていた。
「困るよ、チルノ。ちゃんとエンジンの冷却してもらわないと。コイツの心臓が焼きついちゃうんだからさぁ」
操縦手席のハッチを開けて、にとりが顔を出す。
心配なのはチルノの身体ではなく、ティーガーⅡとでもいわんばかりのセリフだった。いや、たぶんそうなのだろう。こういう時、にとりはブレない。
とはいえ、さすがの妖夢も「それはどうなのか」と口を挟みたくなるような言い方だった。
「ちょっとちょっと! 自分は安全な場所にいるからって無茶言わないでよ! あんなひどい動きをされて、それでもしがみついてなんかいられないもの!」
予告もなしに急加速されたり超信地旋回をされて、外に乗っているだけに等しいチルノが平気でいられるわけがない。むしろ、今こうして生き残っていること自体が奇跡に等しいほどだ。
逆に言えばどこまでも運が良かったのだろう。早々に車体から振り落とされ、落ち着くまで森に隠れていようとしたのが功を奏したと言える。
「にとりはいつもあんな感じなので、気を悪くしないでくださいね。今はチルノだけが頼りなんですから」
とりあえず妖夢は大事な保冷剤――――もとい協力者を宥めておく。ここでヘソでも曲げられては敵が強大になっていく今、本格的に追い込まれてしまう。
「もう、仕方ないわね! 本当にヤバいと思ったら逃げるからね!」
なんとか機嫌を直したチルノはティーガーⅡのエンジンルームへと戻り冷却を再開する。それを見て妖夢は胸を撫で下ろす。
「よいしょ。とりあえずこれでエンジンは大丈夫そうだね」
いったんエンジンを切って冷却を優先させることにしたか、戦車の外へと出てきたにとりが大きく伸びをして窮屈な車内で固まった身体を解す。
「ねぇ、にとり。備えもなく戦いたくないから先に聞いておくんだけど、湖にいるのはどんな敵だと予想しているんだい?」
にとりを追うように砲塔のハッチから出てきた小町が問いかけた。
「鉄の島」
「……へ?」
予想をはるかに超えたにとりの言葉に、思わずふたりは目が点になる。
「わかりやすく言ったら見た目はそんな感じ。だけど正体は船だよ」
「いや、島みたいな船って……」
そんなことを言われても妖夢にはまるで想像がつかない。白玉楼のすぐ近くにある池にはいくつか離れ小島があるが、それくらいしか見たことがないのだ。これで想像しろと言われても無理がある。
「わかんなかったらいいけど、わたしたちが知っているような――――そこのサボり死神が使ってるようなチャチなものじゃないよ」
「ちょっと、あたいの仕事道具をなんだと」
予算がなくて更新できず、だましだまし使っている仕事道具である。上司のケチさなど思うところはあるが愛着もある。
そんな小町の抗議に食い気味に説明を続ける。
「十人や二十人運べるからって自慢にならないよ。鋼鉄でできていて、何千人も乗り込んで運用している、このティーガーⅡの戦車砲でさえ比較にならないほど大きな砲を積んだヤツだ」
「この戦車よりも重い!?水にそんなものが浮かぶんですか!?」
「技術の発展ってのはすごいもんだよ。そりゃあちょっと前に騒がれた空飛ぶ宝船とは原理から何から違うけど、考え方によっちゃあずっと脅威になる。もしも幻想郷に海があったら手が付けられなかったかもしれないくらいのヤツさ」
語るにとりの頬を汗が流れていく。自分の想像が外れていてほしいと願うかのようだった。
「ねぇ、にとり。どうしても倒さなきゃいけない敵なのかい、それ」
不意に小町が何か思いついたのか言葉を発した。
「どういう意味だよ、小町」
「さっきから鳴り響いている音がその鉄の船とやらの攻撃だとしたら、霊夢が結界の異変を感知して飛んで行ったのと同じくらいから聞こえ出したよねぇ?」
にとりの疑問を受けて小町は語り出す。
「その船の目的ってのは幻想郷を隔離している結界の破壊だと思うんだよ」
場違いともいえる亡霊たちの目的がそれだとすれば様々な疑問も解消する。
たまたま彼岸と此岸の境界が曖昧になっているせいで地獄から零れ落ちたが、幻想郷自体に用はないから外の世界に出ようとする。そのために結界を破壊したいのだとすれば……?
「だったら、ここで無理に相手しなくても、迂回して敵の本拠地を叩いちまえばいいんじゃないかい? 霊夢が結界を維持しようとする限り、その船は結界を攻撃し続けることになるんだろ?」
たしかに一理ある。
なにしろ本当に艦船クラスの敵がいれば戦車砲程度ではどうにもならない。駆逐艦のような小型艦であればまだ勝率はあるかもしれないが、だとすればあんな砲撃を行うことは不可能だ。この時点で半分結論が出ているようなものである。
「たしかに、わたしたちの目的は敵の最終兵器の阻止ですが……」
「死神の思いついた悪知恵にしてはなかなかだけれど、それはあまりおすすめできないわね」
妖夢の言葉にかぶせるように、控えめでありながらも通りの良い声が辺りに響き渡った。
声の方向へと妖夢たちの視線が一斉に向く。
「あなたは――――」
森の木々の奥から覗く長い紫色の髪。それと同じく紫と薄紫で固められた服に身を包む姿は見る者にゆったりとした印象を与える。頭に被る三日月の飾りをつけたドアキャップのような帽子も相まって、まるで寝間着のまま外へ出てきたかのようだ。
“動かない大図書館”の異名を持つ魔女、パチュリー・ノーレッジが立っていた。