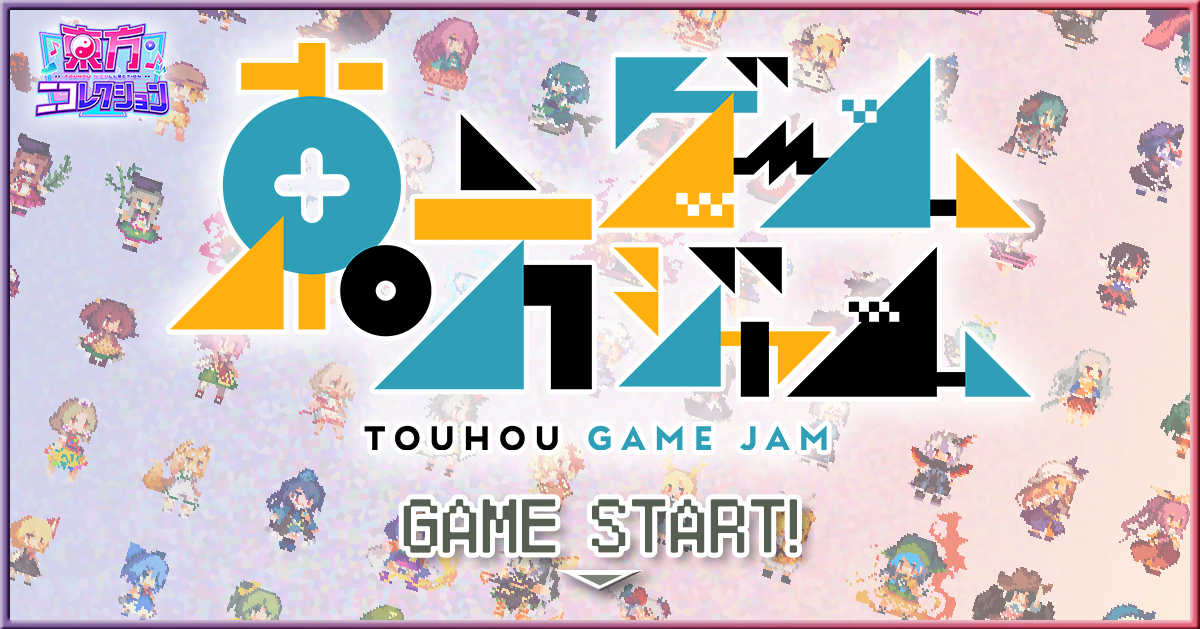【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第26回 防空】
「にとりたち、上手くやってくれたみたいですね」
視線の先でふらつくP-36Cの姿を見て妖夢が満足気につぶやいた。
「あとはこっちでなんとかしろと……」
既に破片にやられてふらついているやつは上に任せたとばかりに小町とにとりのコンビは2機目を狙いにいっていた。
たしかに自分たちが襲撃を受ける可能性を考えれば、健在な方を狙うべきだろう。あくまでも対空砲――――FlaK36はこちらを支援するための存在なのだ。
また、段々とFlaKの扱いにも馴れてきたらしく、地上から立て続けに轟音が発生。カタログスペック上では毎分15~20発の射撃が可能らしいが、単体で都度狙いを修正しながら運用している以上そこまでの速度では撃てていない。
しかし、それでも飛び回る妙な連中を相手にしているだけで済んでいた亡霊からすれば新手は大きな脅威だった。
「おっと、逃がしゃしないぜ!」
必死で逃げようとするが、魔理沙の光弾が進む先へと放たれ逃げ場を塞ぐ。
そこへ狙いを修正した対空榴弾が炸裂し、砲弾に秘められた威力を余すことなく発揮。例の如く直撃弾とはいかなかったものの、破片効果によって機体にいくつもの風穴を開けられたP-36Cが胴体部分から煙を吐き出す。
「命中! 今です、魔理沙!」
妖夢が叫ぶ。魔理沙に指示を出した彼女もまた独自に動いており、またとないこの機会に手負いの1機を仕留める気だ。
「わかってるよ! こりゃ一大チャンスだぜ!」
舵を破壊されたことでそれまでの挙動が不可能となり、速度までもが大きく落ちたところに距離を詰めた魔理沙から放たれた大量の弾幕が集中。航空機レベルの装甲では耐えきれず光弾は内部へと侵入し、燃料に引火したかついに空中で爆散する。
「よーし、いっちょ上がりぃ!」
箒を器用に操りながら両手を上げて勝利を叫ぶ魔理沙。
その傍らで、妖夢もまた手負いのP-36Cにトドメを刺すべく空を駆けていた。
姿勢を安定させるのがやっとの敵へ最高速で向かうと、その胴体に楼観剣の刃を突き立てる。
「取りついた……!」
残念ながら単座のP-36Cに後方への攻撃手段は存在しない。
元々そんなこと――――生身の相手との戦い――――を想定しているわけもないが、敵に物理的に取りつかれた以上、急激な機動で振り落とすくらいしか対抗手段はない。
しかし、そんなことをすれば良くて機体は安定を失い、最悪の場合翼なりが破損して瞬く間に地上へ向かって墜落を始めるだけだ。
操縦席からこちらを振り返った亡霊の目にはどこか焦りの感情が浮かんでいるように見えた。
「大人しく、お縄につきなさい……!」
二振りの刀を交互に突き刺しながら徐々に距離を詰めてくる光景など、亡霊からしても恐怖の対象でしかない。
もちろん、そんな動揺など知ったことではない妖夢は止まらない。
一方の亡霊も帰還することは諦めたか、機首を落として降下し始めた。
舵がきかなくとも地面に向けて突っ込むだけなら問題なくできる。懸命に機体を安定させながら高度を下げつつ向かう先は――――
「死なば諸共とはまた大した武士道ですが……」
その気になればいつでも逃げ出せる妖夢ではなく、奪取された対抗手段を道連れにしようとしていた。今後の戦術的には見れば間違いなく正解だ。
急降下で振り落とされそうになる中、妖夢は操縦席を目指して進んで行く。
時間との戦いだった。FlaK36は射撃を行っていない。急降下してくる相手を狙うのは困難なこともあるが、どちらかと言えば妖夢を巻き添えにしないためだ。
問答無用で撃たれるよりはずっといいけれど、目的を達成するために下手な躊躇はしないでほしい。生死に頓着のない妖夢は不穏なことを考えながら、構わず進んでいく。
「往生際が悪いぞ!」
ついに間合いへと侵入した妖夢は叫び声と共に楼観剣を水平に薙ぐ。
妖怪10匹分に相当すると言われる殺傷力が顕現し、先ほど別の敵で貫いた風防を今度は完全に破壊。風防の中にあった亡霊は首を刎ね飛ばされ鮮血が噴き上がる。
機体の挙動が不安定になる中、首を失った本体へ白楼剣を突き刺して霊体化させ、妖夢は本格的に制御を失った機体を蹴って地表への急降下から脱出。
進路を大きく逸らしたP-36Cは目的を果たせず森の中へ落下し爆炎を上げた。
「ホントとんでもない戦い方をするよな、妖夢は……。よし、これで敵はあらかた片付いた! どうせ連中もまた来るだろうし、対空防御陣地を構築するよ! アリス、手伝って!」
念のため避難していたにとりが、パンパンと手を叩いて声を上げた。
まるで水を得た魚だ。いや、河童だから厳密には違うのだろうが、水(際)に住んでいるしやはり似たようなものだろう。
「まったく……来たばかりだっていうのに人使いが荒いわね。悪いけど、専門用語を話されても理解できないの。ちゃんとわかるように指示を出してちょうだいね」
「大丈夫だって。そんなに難しいことはさせないよ」
不承不承といった様子ではあるが、またあんな連中を相手にするのは堪らないのだろう。アリスは手際よく人形たちをにとりの指示通りに動かしていく。
「あ、魔理沙は空中で警戒しといてくれない? もしあの飛行機械がまた来たらこっちに誘導してもらうからね」
「えぇー、わたしがやるのかぁ?」
不満を隠そうともしない気だるげな声。
「そう言うなよ。危険だけどこれを頼めるのはスピードに優れるあんただけだ。頼まれちゃくれないかい?」
こういう相手には真っ向から正論を並べるよりもおだててその気にさせた方がいい。そのあたりはにとりも十分に心得ていた。
「む、そうまで言われちゃ悪い気はしないな。わかったぜ、任しておきな。でも、わたしだけで落としてしまっても構わないんだろ?」
まだ始まってもいないのに自信満々でいる魔理沙。
そういうのを“フラグ”と言うんじゃなかったか。にとりは外の本で読んだ知識を思い出す。とはいえ、おそらく迷信の類だろうし、わざわざ触れるようなことでもないだろう。
「自信があるのは結構ですけど、油断してると痛い目に遭いますよ?」
魔理沙の楽観的な態度が気に入らなかったのか、生真面目な妖夢は戻ってきて早々苦言を呈する。
この異変に関わってからずっと振り回され気味というよりは何度も命の危険に晒されてきたのだからそんな言葉のひとつも言ってやりたくなるのだろう。
「まぁまぁ、そんなに目くじら立てなさんなよ。ちゃんと任された仕事くらいはするからさ! またあいつらが来たら、なんか合図を出すなりして知らせればいいんだろ? じゃあな!」
面倒くさい相手に絡まれたとでも思ったのだろう。魔理沙はひらひらと手を振るとそのまま箒に跨って空へと飛び出して行く。
「はぁ……。本当に大丈夫なんですかね、あれで」
溜め息を吐き出す妖夢。
援軍に来てくれたのはありがたいし、事実彼女たちがいたから空飛ぶ敵も含めてこの場を無事確保することができたのも理解している。
ただ、あの緊張感のなさだけがどうにも気になるのだ。
「不安に思うのもわかるわ。でも、ああ見えてやることはちゃんとやるから大丈夫でしょう」
似たような思いなのかすこしだけ苦い笑みを浮かべつつ、取りなすようなフォローの言葉がアリスの口から発せられた。
魔理沙との付き合いが長いぶん、振り回されながらもその性格まで熟知しているのかもしれない。
「さてさて。これでこの場は確保できたね」
ぱんぱんと手を叩いてにとりが話題を変え、忙しさをアピールするかのように対空砲へと向かっていく。
「あ、わたしたちで敵の航空戦力を引き付けておくから、妖夢と小町はこのまま敵の本拠地に突入しちゃってよ。あれを相手にしながら進むのは厄介だから陽動が必要だよね」
「いーや、ちょっと待った」
FlaK36のハンドルをどこか楽しげに回しているにとりの背中に小町の言葉が投げかけられた。
「……なにかな?」
にとりの声はどこか上擦っていた。やましいことがあるのか小町たちの方を振り返ろうともしない。
「なに? じゃないよ、まったく。兵器に詳しいあんたがいなけりゃ、肝心のやつを見つけたってどうにもできないじゃないかい」
錆びついた機械のようにぎこちない動作で背後を振り返ったにとり。表情に浮かぶ笑みはどこか引きつっている。
「そうです。ここまできて自分だけ逃げようなんて考えてもそうはいきませんからね」
腰に手を当てて胡乱げな表情で視線を向ける剣士と死神の少女。
「まさかこの期に及んで妙な真似はしないよな?」と視線が雄弁に物語っていた。下手に答えれば沸点の低くなっている今のふたりからどのような目に遭わされるかわからない。にとりの額にじんわりとイヤな汗が浮かび上がる。
「なに? 敵とやらをやっつける以外に何か厄介なことでもあるの?」
さすがに会話の内容が気になったかアリスが小首を傾げて疑問を挟む。
「えーと……」
素直に言ってしまってもいいものだろうか。妖夢と小町は顔を見合わせる。
「あぁ、大丈夫よ。下手に興味を持たれたら大変だしものね」
「よくわかってらっしゃる」
魔理沙がいるであろう空に視線を向けたにとりに、アリスはこちらの事情を慮るように小さく笑みを浮かべた。
「その様子だと、あまり他人に知られたくない内容なんでしょ? わたしも厄介ごとに巻き込まれるのはごめんだから、漏らしたりしないわ。ただここまで関わった以上、事情くらいは知っておきたいってだけ」
たしかに、彼女は幻想郷住人の中でも行動派として位置づけられてはいない。動く時にしても多くは誰かに巻き込まれたり、あるいは已むに已まれずといった具合だったりで、自分から積極的に何かを起こそうとするタイプではなかった。
ここまで巻き込んでいるし助けてももらった。差し支えない範囲で教えておいた方がいいだろう。
「ご配慮感謝します。想像されているようにあまり多くは語れませんが、幻想郷の危機が迫っています」
これが妖夢にできる範囲の答えだった。
「この異変で? いつものようなのじゃなく?」
アリスの問いに妖夢は静かに頷く。言葉に出さないことが事態の深刻さを裏付けていた。
「敵を倒しただけでそれが解決するかは未知数なんです。そして、厄介なものをどうにかできそうなのが、そこで逃げようとしてくれた河童でして」
「に、逃げるだなんて人聞きが悪いなぁ! そんなつもりなんてないよ!?」
反論を叫ぶにとりだがまるで説得力がない。その証拠に目が不自然なくらい泳ぎまくっていた。
「そう。なら、すこしだけ時間をちょうだい。あの機械を使う役目、わたしの人形でどうにかできないかやってみるから。さすがに危機とあればわたしも動くに吝かではないわ」
それからアリスはにとりの指示を受けてFlaK36の使い方を学んでいく。
魔法への造詣があまり深くない妖夢たちにはどういう原理かさっぱりだったが、操られる人形たちは見事なまでに要求通りの動きを果たすようになっていった。