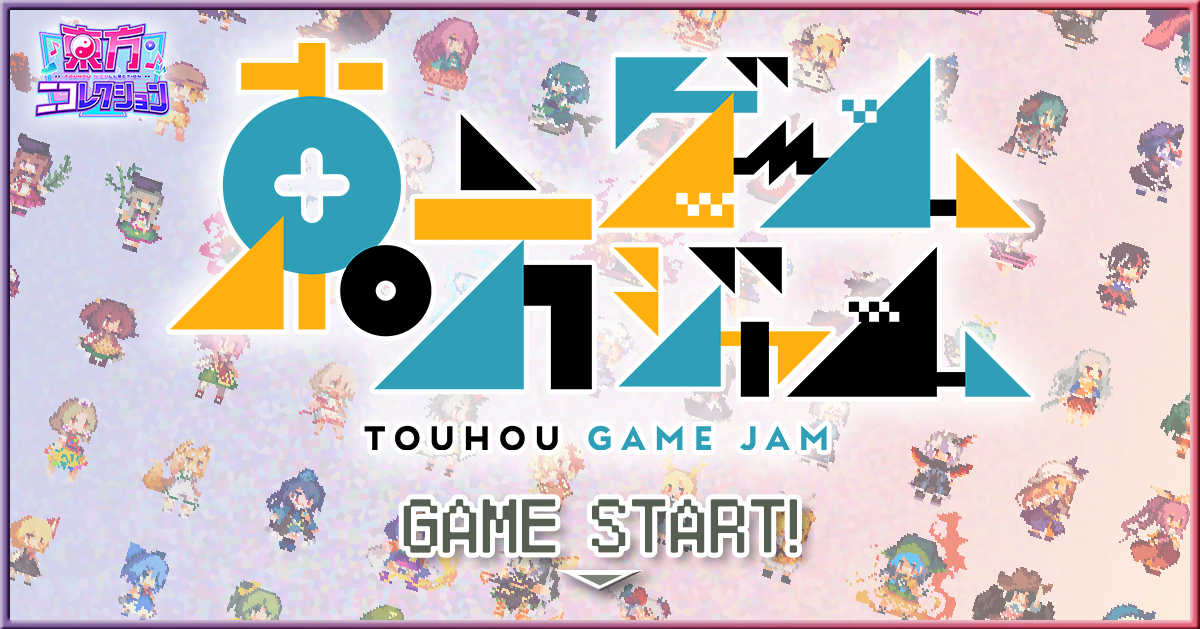【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第19回 歩戦】
「うひゃあっ!?」
突如として生じた爆風の煽りを受け、妖夢は飛んでいるのに踏ん張りが――というのも変な話だが――きかなくなり身体が宙を舞う。
常人ならそのまま吹き飛ばされて地面か木の幹にでも叩きつけられているであろうが、あいにくと空を飛ぶことなど何ら珍しくない幻想郷の住人には関係ない展開だった。
すぐに体勢を立て直し、姿勢を安定させる。
「うおっと、こりゃヤバいね! ……妖夢! ちょっと空へ逃げて様子を見るよ!」
「わかりました!」
こういう時ばかりは勘がしっかり働くのか、傍らにいて同じように飛ばされかけた小町が器用に回転したまま叫んだ。
さすがに妖夢もここから何も考えず敵目がけて斬り込むような真似はせず、活路を上空へ見出した小町と共に一旦上空へと退避する。
「いったいなんなんです、あれ……! てっきり魔法使いの奥の手でも喰らったかと思いましたよ……」
辺りに漂っていた土煙が晴れると、砲弾の直撃を受けた場所は更地となっていた。凄まじい破壊の様を見せつけられた妖夢は思わず首を竦める。
無慈悲に叩きつけられたのは個人の強さなど完全に超越した破壊のためだけの力。
誰が強いとかそのような規模など軽く通り越し、ただその瞬間あそこにいただけという理由であっけなく死ぬ――――“理不尽なまでの暴力”だった。
「ははは、あたしゃもう帰りたくなってきたよ……。そろそろ妖怪だ死神だが生身でどうにかなるところを通り過ぎているんじゃないのかい?」
さすがの小町も次々に塗り替えられていく事態を前にしては乾いた笑いしか出ない有様だった。
「……もし逃げたら、地の果てまで追いかけても斬り捨てますからね?」
小町に向けられる妖夢の目に、冗談の成分は一切含有されていなかった。
「じょ、冗談だよ? この期に及んであたいだけ逃げ出すわけないじゃないかぁ。やだねぇ、妖夢は。あはははは……!」
仄かに漂い始めた鬼気に気圧されるように小町は慌てて否定した。
昨日から重なるように起きている戦いのせいか、妖夢の思考形態がかなり攻撃的になっている。これ以上、変に刺激をするとこの場で自分が斬られかねない。伊達に“辻斬り”の異名を持っていないのだ。
「まぁいいですけど。それよりもどうやってあの新手を倒すか……」
それにしても、今の攻撃はとんでもない威力だった。
もしも近くにいたら直撃せずとも衝撃で身体の内部をやられていたかもしれない。迂闊に近寄れない敵を前に、妖夢の背中にじんわりと冷や汗が浮かび上がる。
「……ねぇ、それもいいけどちょっと待ちなよ。にとりはどこに行っちまったのさ?」
「あっ!」
今になって仲間であるにとりの不在に気が付いた二人が視線を動かし、そして硬直する。
彼女たちの視線の先には、ついさっきまで彼女が操っていたはずのSd.Kfz.223――――その残骸が無残にも吹き飛ばされて転がっていた。
「に、にとり……!」
ちょっと壊れた程度ではない。
燃料に引火したか生じた爆発で内側から弾け飛び、今も残った燃料から炎を上げ続けているSd.Kfz.223の無残な姿がそこにはあった。
もしも、にとりがあの中にいたのだとしたら、どう考えても生きていられるようには思えなかった。
「ま、まさかこんな……」
ついに味方から犠牲者が出てしまった。こんなことならついて来るなんて言った時に止めておけばよかったのではないか。
取り返しのつかない事態となってしまい、妖夢の白い顔から血の気が引いていく。
「……ちょっとちょっと、妖夢? 驚かせちゃったのはわかるけど、だからって勝手に殺さないでくれよ」
すぐ真後ろから若干引き気味に発せられた声。
「えっ、にとり!?」
驚いた妖夢が振り返ると、そこには胡乱な表情を浮かべるにとりの姿があった。
「生きていたんですか!? ま、まさか幽霊とかじゃないですよね!?」
混乱していたのと嬉しさ余ってぺたぺたとにとりの全身を触りまくる妖夢。自分のように半霊が出ていない時点でわかりそうなものだが、まったく
「ちょっ、そんなじっくり触んなよ、恥ずかしいなぁ!」
「あっ、ちゃんと肉体がある……。いやでも……本当に生きてて良かったです……」
お化けを見れば泣き出したりと、情緒不安定――――もとい、なんだかんだと感受性豊かな妖夢の目には、ほんのりとではあるが涙が浮かんでいた。
半分死んでいるヤツに言われるとなんだか不思議な気分になってくるな……。
にとりはどことなく釈然としない気分となるも、状況が状況だけにここで口には出さなかった。
「そりゃ用心してたさ。あんなヤバいヤツが出てきちまったんだ、デカいのに乗ってるあたしが真っ先に狙われると思って直前で脱出しといたに決まっているだろ」
よくよく見るとにとりの髪や頬には煤がついており、帽子や服の端は微妙に焦げていた。本当にギリギリの脱出劇だったのだろう。あらためて油断など微塵もできない存在が敵に回っていると思い知らされる。
「って、マズい! 見つかった!」
それまで獲物を探して辺りを睥睨するように進んでいた鉄の箱――――戦車が不意に動きを止めた。
砲塔がゆっくりと旋回を始め次いで発砲。
空気ごと聴覚を殴りつけられるような轟音が響き渡り、妖夢たちの近くを砲弾が音速を突破して通り過ぎていく。
「へへん! そう簡単に当たるかってんだ!」
挑発するように小町が叫ぶと、戦車の重厚そうな上蓋が開き、中から姿を覗かせた亡霊がこちらに向けて見たことのない形の銃を向けてくる。
同時に戦車の背後にあった森の中からも同様の装備を持った亡霊歩兵たちが進み出てきた。
「小町が余計なこと言うから敵が増えたじゃないですか!」
「ええっ!? これってあたいが悪いの!?」
「くそ、あいつらの武器までイイものになってきてる! このぶんだと、あたしたちも本格的に脅威だって認識されたのかね!」
今となってはもうにとりも銃撃がくるとの警告までは発しない。
すくなくとも今回の敵を相手に悠然と構えていることが即座に死へと繋がりかねないと妖夢も小町もとうの昔に身体に刻みつけられていると理解しているからだ。

「攻撃が変わった……?」
軽快な音が複数重なり、それと共に飛来する弾丸を妖夢たちはそれぞれに回避していくが、それが今までのような単発のものではないことに気付く。
「わかりやすく言えばね、あの連中、だんだん強くなってきてるんだよ」
にとりがわずかに表情を険しくして告げる。
新手の亡霊たちが手に携えているのは、PPSh-41、ドラム型の弾倉と木製の銃床が特徴的な、Kar98kとおおよそ同時期にドイツではなくソビエト連邦で使用されていた短機関銃だ。
Kar98kのような小銃に求められる、ある程度離れた交戦距離での安定した戦果および命中精度ではなく、近距離における瞬発火力を重視しており、また銃身が短くされていることもあって今いる森のような場所での取り回しに非常に優れている。
先ほど自分たちが使ったMG34ほどの威力や速度はないように感じられるが、それでも妖夢たちは生身なのだ。殺傷力を突き詰めた礫――――弾丸を至近距離から喰らってしまえば当然のことながらひとたまりもない。
しかも、銃身そのものが短くなっている分、銃口を避けて相手の間合いに入り込むのがより困難になっている。もしあれを持った亡霊と戦うならば、より速い剣が求められるのだと妖夢は直感的に理解する。
「たしかに、あんだけ多いと厄介だね。前のヤツらと違うのはあたいにもわかるよ」
三人はPPSh-41から立て続けに放たれる弾丸の群れを回避し、とりあえず一旦は彼我の距離を稼ぐ。
亡霊の数こそ多いものの、Kar98kのように狙ったところで遠距離まで届きそうにないのがせめてもの救いだった。
「厄介な雑兵が増えましたね……。けれど、肝心の鉄の箱はさっきみたいに撃ってきませんが……?」
上空に対してあの兵器では仰角をつけられないのか、そもそも対空目標を想定していないのか、すくなくとも今は先ほどの攻撃はできないようだ。
「あぁ、あれは地上専用なんだ」
「ということは、あれの詳しいことも知っていると?」
にとりの返答に妖夢が疑問を挟む。
「そりゃね。あんたらに言ってもわからないだろうから細かい説明はしないけど、陸上なら最強クラスに分類される兵器だよ。とんでもなく分厚い装甲――――鋼の板に覆われているからこんな弾丸なんて通りゃしないし、あればっかりは妖夢の剣で斬ろうとするのはおすすめしないね」
短く嘆息して、にとりは手に持っていたKar98kを背中のリュックへと差し込み、代わりの武器――――用心のために持ってきていたパンツァーファウストを握る。
早速出番がきてしまったことに嘆くしかないが、あれをどうにかしないことには先にも進めそうにない。
「うーん、斬れないって言われるとなんだか試してみたくなるんですが……」
楼観剣の柄を握った妖夢の双眸に剣呑な光が宿る。発言が完全に辻斬りとか猟奇殺人犯のそれであった。
「あんたさぁ……。こんな時くらいもうちょっと冷静になれないのかよ? とんでもなく危ないヤツみたいじゃないか」
「心外ですね。にとりが機械を前に我慢ができないように、わたしだって斬れそうなものがあったら斬りたくなるってだけなんですよ?」
あまりの緊張感のなさに、いよいよにとりは頭が痛くなってきた。
ビビって動けないとかそういう状況でないだけまだマシなのだが、本当にこの連中は異変を解決する気があるのだろうかと疑いたくなってしまう。
「わかったから、もうちょっと落ち着いてよ……。斬れる斬れないは試してみないとわからないけれど、それより気をつけなきゃいけないのはあの主砲だよ。間近で砲をぶっ放されたらその衝撃だけで本物の幽霊になれるからね」
例の如くそんな余裕もなかったためにとりは語らなかったが、4ストロークV型12気筒水冷ディーゼルの唸りを上げながら陣取っているのはT-34。PPSh-41と同じくソビエト連邦を中心にかつて使用され、総生産台数は84,000輌にもおよぶ戦車である。
全体的に角張った印象を受ける車体に小ぶりな砲塔が鎮座しており、戦車そのものを見たことがない幻想郷の住人はまるで巨大な鏡餅が動いているように思うかもしれない。
「じゃあどうやって倒せばいいんです? あの様子だと近付くことさえ難しいんじゃ?」
「あいつは強力な分、移動しながらじゃまともに撃てないって制約もあるんだ。無理すりゃ撃てないこともないけど、どのみち反動が強すぎてまともに当たりゃしないからね」
今回対峙しているT-34が、シリーズの中でもT-34-85と呼ばれる85mm主砲でなかったのは不幸中の幸いと何かに感謝すべきだろうか? とにとりは思うもすぐに脳内で否定する。
生身の存在が弾丸を相手にしている時点で無茶苦茶なのだ。こちらにも戦車があれば相手の砲弾の能力如何が生存性にも大きく関わってくるが、どうせ当たれば一撃で死んでしまう。
もっと言えば弾丸にハチの巣にされるか、砲弾で爆散させられるか――――もはや気持ちの問題でしかない。
「つまり?」
「陽動をかけてもらってる間に、あたしがパンツァーファウストで仕留めるよ。どうせ斬り込みたくてウズウズしているんだろ? 雑魚どもを仕留めるついでに戦車を翻弄してよ」
重さをものともせず、兵器を肩に担いでにっかり不敵に笑うにとり。
その表情見て、妖夢も「にとりだって自分と同類じゃないのだろうか?」とすこしだけ不満げに思うのだった。