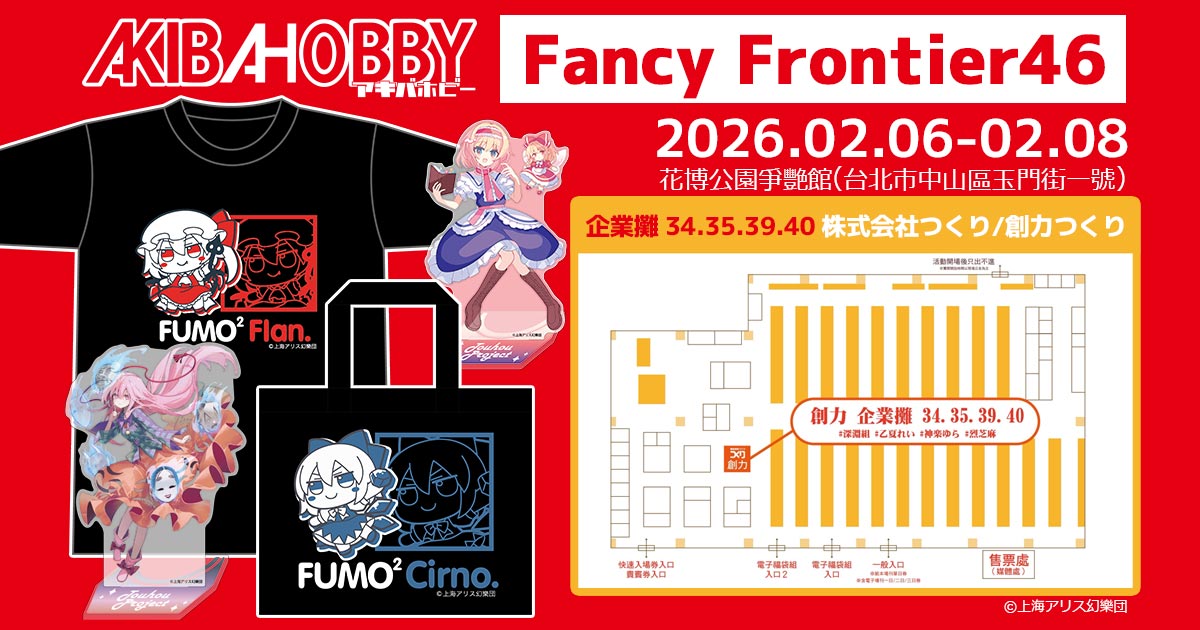【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第14回 能力】
「しっかし、気になるのが他の兵器がどうなっているかなんだよなー」
山へと向かう道すがら、Sd.Kfz.223の運転席に座り大好きな工業製品を思う存分堪能しているにとりがふとつぶやいた。
細かいことだが、つぶやいたと表現するのはいささか正確ではない。
唸りを上げるホルヒ3.5 75馬力水冷V型8気筒ガソリン内燃機関に負けない声を出さなければ隣人に話しかけるのも大変な状況なのだ。
そのせいで、にとりは普段の彼女よりもずっと大きな声を腹の底から出していた。
「ああ、他の河童たちが持って行って解体作業をしているってやつですか」
銃座の中ではその長さがかえって邪魔となるため、楼観剣を抱えた妖夢が同じく声を張って訊ね返す。
見方によってはこんな時に気が抜けていると思われそうなものだが、常に緊張状態とあっては咄嗟の時に最高のパフォーマンスを発揮することはできない。
そのため、これこそが妖夢にとっての臨戦態勢といえた。
とはいえ、それでもなにかあればすぐさま打って出られる姿勢を維持できているのは、まさしく剣士としての積み上げてきた研鑽が為せるものだろう。
「そうそう。わたしと同じ目に遭ってなきゃいいんだけどねぇ」
河童という種族に個人主義な面が強く備わっているとはいえ、けして仲間が心配にならないわけではない。
他の妖怪などと比べて特段戦闘力に優れるわけでもない以上、機械をいじりたい欲求を捨てて上手く逃げてくれていれば……。
ハンドルを握りつつも、にとりは内心でそう願っていた。
(でも、たぶん無理だろうな)
自分自身が無理だったのだ。正直なところ他の河童がどうにかできるとは到底思えない。
「にとりが心配な気持ちはわからないでもないですが、気にしていてもキリがないですよ。今は問題を解決するしか……」
とにもかくにも時間がないのだ。
断片的な情報しかないようなものだが、空を攫った目的を八咫烏の力で、それを利用して厄介な兵器の起動を企んでいると仮定すればほとんどの説明がつく。
「それに敵の首魁を倒せば終わりじゃないんですか? この手の異変は大本をどうにかすれば終わるものでしょうし」
いささか楽観的な物言いだと妖夢は自分でも思うが、現状では他に取り得る選択肢がないのだ。
ならば、立ち塞がる敵をすべて斬り捨てて先へ進むだけだ。
「いやぁ、あたいはそう簡単にいかないと思うけどねぇ」
そこで霊魂関係のエキスパート、小町が欠伸交じりに言葉を挟んできた。
狭い銃座の中だというのに相変わらず頭の後ろで手を組んだりとまるで遠慮がない。
「あら、小町。起きていたんですか」
こんな時に暢気なものだと言葉と共に視線を送る妖夢。
これほどまでに騒がしい環境下にもかかわらず、彼女はついさっきまで舟をこいでいた。
もちろん彼女が普段漕いでいる三途の川の渡し舟ではなく、居眠りの舟だったのは言うまでもないことだ。
しかも、たまたま敷布代わりになりそうなものを見つけたようで、それを誰にも言わぬままちゃっかり占有していたあたりが実に小町らしく抜け目がなかった。
「そりゃそうさ。繊細なあたいにゃ、この荷車はちょっとうるさすぎるんだよ」
胸を張って答える小町。
(……たぶん自分の知っている繊細さとは違うものだろうな)
妖夢はあえて触れずにスルーした。
「で? その“大佐”とか言ったっけ? 亡霊たちの親玉がなにからなにまで操っているのなら、昨日から遭遇している亡霊たちだってもっと次から次に襲ってきても不思議じゃないだろ?」
「その気配がないということは、つまり亡霊を操る能力ではない……?」
「そう考えるのが自然だろうねぇ……。実際、そんな能力があったところで一度彼岸に渡ってしまった霊魂を亡霊に変化させるだけじゃなく、こんな風に此岸で受肉させるなんてできるもんじゃないはずだよ。世の中、そこまで甘くできちゃいないのさ」
珍しく知性を披露する小町。
どこで見つけてきたのか、いつの間にか死神の少女は緑の新芽がふたつ先端についた小枝を咥え、器用に下顎を動かしてそれをぴょこぴょこと上下させていた。
「小町、そんなことをしなくてもお腹がすいて樹液が吸いたいならちゃんと言ってくれれば……」
心底気の毒なものを見るような目で妖夢は小町に視線を向ける。
数々の辻斬り行為で蛮族の親戚くらいに思われている妖夢だが、なにげに育ち自体は悪くない。それゆえにカッコつけに枝を咥える小町の行動が理解できないのだ。
「ちょっと? あたいはカブトムシやセミじゃないんだけどね?」
気分を出そうとしているところに水を差されたからか、小町は不満そうな表情を浮かべて妖夢を見る。
「いやですね、小町。そんな失礼なこと思っているわけないじゃないですか。ほら、セミならもっと忙しそうに鳴いて回っているでしょうし、カブトムシだって子孫を残そうと懸命になっているんですから、小町と一緒にしたらあちら側に失礼ですよ」
「……あれ? もしかしてあたい、虫以下の存在に思われているわけ……?」
強張った表情を浮かべる小町の口からついに枝がぽろりと落ちた。
「いえ、そんなことは。ただ、映姫様が派遣したわりにはそこまで役に立っていない気がするだなんて、さすがにわたしの口からはとても……」
「ねぇ、妖夢!? それってほとんど口にしてるようなものだと思うんだけど!?」
あまりにも容赦の欠片すらない妖夢の言葉を受け、小町は先ほどまでとはうってかわって涙目になっていた。
それほど長く一緒にいたわけでもないのに、妖夢の放つツッコミの切れ味が彼女の振り回す刀へと近付いているような気がする。
あるいは徐々に気心が知れてきたことで遠慮がなくなっただけかもしれない。
「ははは、わたしもセミ……じゃなかった、サボり死神の意見に同感だね。兵器と同化した亡霊を従えているってくらいじゃないのかな。さしずめ“亡霊を指揮する程度の能力”ってところかね」
ふたりが繰り広げる会話にけらけらと笑いながらも、にとりはちゃんと話の流れを元に戻すのを忘れない。
ふとした時にマッドサイエンティズムを発揮することのある彼女だが、不思議なことにこのメンバーの中ではブレーキ役の地位を築きつつある。
霊夢あたりが見たらさぞや奇妙に感じるであろう光景だった。
「“亡霊を指揮する程度の能力”……。字面だけなら大したことはないように聞こえますけど――――」
車輪が石に乗り上げたのかひときわ強い振動が伝わってくる。
「そんな単純な話で済むのなら、幻想郷が過去最大級の危機を迎えてなんていないでしょうね」
「だと思う。異変って言えば、わたしたちが慣れ過ぎたのかそれほどでもないように聞こるけど、今回ばかりは正直非常事態でしかないね」
にとりの吐いた溜め息が妙にはっきりと聞こえた気がした。
これなら住人同士で小競り合いをやっている方がずっとマシというものだ。
「なんでこんなことになっちゃったかなぁ……。でも、あちこちに協力を求めるわけにもいかないですし」
妖夢は嘆く。
元々、冥界側だけで片付けようとしていた曰くつきの案件だ。
此岸側は此岸側で動いていたようだが、八雲紫をして博麗の巫女を動かさなかった時点で別の思惑や事情があるのは明白である。
ましてや、現場要員にすぎない自分たちが独断で進めるわけにもいかない。
「前提から厳しいね。しかし、こういうところでみんなの協調性のなさが出るとはなんだかね~」
「しかも相手は統率のとれた集団ときたもんだ。そんな連中を相手にあたいたちだけで孤軍奮闘ってまるで笑えやしないよ」
各々の表情に苦いものが浮かぶ。
この先直面するであろう問題は、“相手が集団戦に長けている”点にある。
幻想郷の住人は良くも悪くも気まぐれかつ個人主義であり、どれだけ判断基準を緩くしても仲が良い程度で、複数で群れて動くようなことは滅多にない。
共同体――――一定の勢力を築き上げている者たちも存在はするが、統制が効いているわけでもなく精々が同じ趣味の集まりと言い換えてもいいだろう。
「味方がいれば楽にはなるでしょうけど、藪をつついて蛇を出してしまうのも本末転倒ですしね」
力を持つ者たちが一致団結すれば解決できるんじゃ……と妖夢の脳裏を一瞬考えがよぎったが、すぐにそれが不可能だと気付く。
下手に異変の情報を広めてしまえば、この危機を自らの企みに利用する輩が現れる危険性があった。
その証左というわけではないが、異変を解決したと思った矢先に、また別の黒幕なり闖入者なりが現れて余計に面倒な事態が起こりかけたと聞いたこともある。
件の究極兵器や各種武器・兵器群を目の当たりにして、それらを我が物にしようと企まない保証はどこにもないのだ。
「河童でさえ夢中なんだ。あれを手に入れて、本来の目的で使わないほうがどうかしているってもんさ」
多くの死を見て来たからか、こういう時に小町はどこか達観したような物言いをする。
しかし、妖夢としても一概に否定できるものではなかった。
圧倒的な暴力であるがゆえに、それは同時に抗いがたいほどの魔力さえも有している。
剣の道を究めんと長年研鑽を積んできたがゆえに、種類は異なれど力を求めたがる心理は妖夢にも理解できた。
「そうそう。結局幻想郷が滅亡しちゃうんじゃ命をかける意味がないよ。あんたらは向こう側だからいざという時は関係ないかもしれないけどね」
あまりにも笑えない事態を想像した三人の気分が急降下していく。
「ばか言うでないよ。異変を解決して、それで今度は内ゲバでドカンなんて御免だっての。あたいの仕事を増やさないでおくれ」
「けっ、どこまでも怠惰な死神だな」
「まぁまぁ。こうは言っていますけど、小町だって悪ぶってるだけで本意じゃないわけ――――っ!」
ふと妖夢は首の裏あたりがチリチリとする感覚に襲われ言葉を止めた。
普段とは違う――――正真正銘の命を懸けた戦いを繰り返してきたことで、五感だけでなく意識のほうまでもが鋭くなっているのだろう。
妖夢の様子が急変したことを受け、小町とにとりも表情を固くする。
遠くに複数の気配。銃座から頭を出して目を凝らすと亡霊たちの姿が見えた。
「また変なものが置いてありますね」
妖夢が注ぐ視線の先には大きな筒のようなものが四つほど天を向いて鎮座していた。
ところが、その兵器は別の役割があるのか微動だにせず、周囲で動き回っている亡霊兵たちだけが近付いて来るSd.Kfz.223にそれぞれの銃口を向けている。
「たしかあれは――――」
「にとり、蘊蓄はあとにしてください。どうやらお呼ばれされていないわたしたちを盛大にお出迎えしてくれるようですから」
兵器解説を始めようとしたにとりを妖夢が遮る。
正々堂々「よーい、どん!」で戦いが始まるならまだしも、ここは情け容赦も一切ない本物の戦場で一瞬の遅れが即座に死へとつながる。
すでに妖夢は臨戦態勢に移っていた。
「はぁ……。歓迎委員会の準備までできているってことかい。宴以外のお誘いは遠慮することにしているんだがねぇ……」
「そこだけはわたしも同感しますよ、小町」
楼観剣の柄へと手を伸ばした妖夢はいつしか頬を撫でる風の中に、新たな匂いが混ざっていることに気がつく。
流れる空気に漂うのは、硝煙と――――むせかえるほどに濃密な死の香りだった。