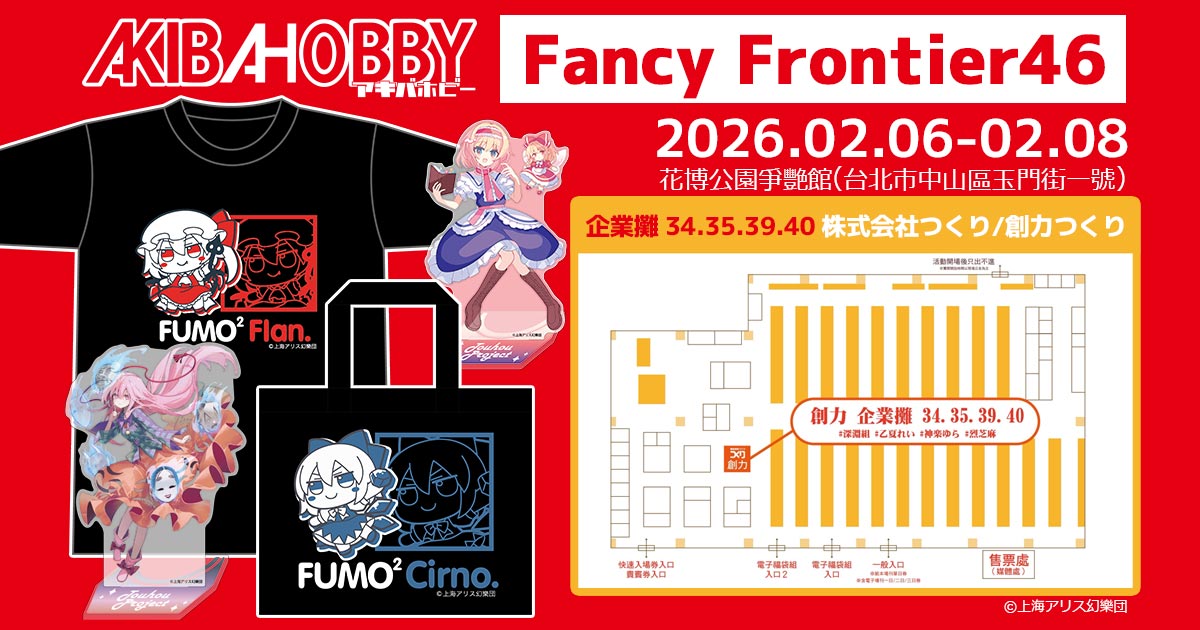【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第21回 空襲】
見上げたにとりの視線の先で、まっすぐ突っ込んでくるP-36の機首と両翼に装備された機関銃が轟音を上げて火を噴いた。
これまで戦ってきた火器類――――MG34など比較にならない密度の弾丸が驟雨となって、パンツァーファウスト150を発射直前だったにとりに襲いかかる。
「うげっ!?」
小さく悲鳴を漏らしたにとりが慌てて避けると、唸りを上げて通り過ぎて行った弾丸がその先に合った木々の枝や幹に穴を穿ち、あるいは込められた破壊力によって吹き飛ばしていく。
実際に見せつけられた威力を前ににとりの顔から血の気が引いていく。
しかし、そこでP-36は地表への衝突の恐れから追撃を断念したか、機首を引き上げると、ふたたび高度を稼ぐべく14 気筒星型1,200馬力空冷エンジンの唸りを響かせて上昇していく。
その際、コクピットにいた亡霊兵の生気の欠如した目と視線が交差した気がした。
――――そこには生者へ向ける確かな憎悪があった。

「ちくしょう!もうちょっとのところなのに邪魔をしやがって! あぁ、あっちにも見つかった!」
仲間からの機銃掃射で伏兵の位置を察知した亡霊戦車兵から放たれる銃撃を回避しながらにとりは毒づく。
絶好の射角を取ったというのに、それさえも闖入者によってフイにされてしまった。
しかも、鈍重な戦車だけが相手と思っていたところに機動力の塊と言っても過言ではない戦闘機の襲来だ。こんな航空支援のある中でまともに戦車と戦えるはずもない。
動き回る戦車を倒すなら、地べたを這って真正面から相手をしなければならない歩兵とは異なり、空から装甲の薄い部分にパンツァーファウスト150をお見舞するのが最適解だろう。
だが、この場でそんなことをしようものなら、空を縦横無尽に飛び回るアイツに蜂の巣どころか挽き肉にされる未来しか見えない。
生身相手に容赦なく重機関銃をぶっ放してくるあたり本格的にどうかしていると思うが、最強最悪の兵器をこの幻想郷で使おうとしているのだからそんな感想さえも今更のことである。
とはいえ、あまりにも不公平だ。
幻想郷の連中も色々と能力を持ってはいるが、あくまでも弾幕ごっこに特化しているといっていい。もっとこっちにも兵器の援護があってもいいんじゃないだろうか。
「妖夢! 小町! いったん退避するよ! ヤバいのが来た!」
T-34への陽動を続けている妖夢と小町の下へと飛んでいきながらにとりが大声で叫ぶ。
「え? どうしたっていうんですか、にとり? というか、あの羽虫はいったい?」
「いいから! 相手が上昇している今が隠れる絶好の機会なんだよ!」
今までにない剣幕で声を発するにとりに、さすがの妖夢と小町もただごとではないと判断したか素直に木々の中へと退避する。
「戦車まで出てきたんだし、そのうち現れるんじゃないかとは思っていたけど、まさか今かよ……。この様子だと最悪の事態に近付いているなぁ。ああ、本当にもう最悪だ……!」
額に汗を浮かべ、後頭部を掻き毟って苛立ちを露わにするにとり。普段よりも口数が多くなっているが、逆に言えばそれだけ状況が良くないのだろう。
「なんだかまた厄介そうなのが出てきたねぇ……。前に宝船がどうのこうのとかの騒ぎがあった気がしたけれど、あれはそいつの親戚かい?」
妖夢と小町が木々の間から外の様子を窺うと、上空を旋回するからくり仕掛けの羽虫の姿が見えた。
あれほど大きな人工物がからくりの力で空を飛ぶなど、幻想郷の住人からすれば想像できる範囲を完全に超えている。外の世界の人間がそれを聞いたら「単体で空を飛べる方がよっぽど非常識だしどうかしている」と抗議をしてきたに違いない。
「まったく違うよ。あんなのと一緒にしてたら、そう遠くないうちにあんたが別の死神に運ばれる側になるだろうね」
冗談に付き合っている余裕もないのか、鼻を鳴らして放たれたにとりの言葉は冷ややかだった。
「すばしっこいのはわかりましたが、見たところわたしたちにみたいに細かい動きはできないのでは? 正直そこまでの脅威には感じられないんですが……」
怪訝な表情を浮かべた妖夢が疑問を挟む。
なまじ空を飛べてしまうからそう思ってしまうのだろう。ただ飛ぶのが速いだけなど幻想郷では何の自慢にもならない。
だが、あの敵はそんな生易しいものではない。
「あいつのど真ん中についている機関銃の威力が桁違いなんだよ。掠っただけでも生身じゃ吹き飛びかねないくらいのね」
妖夢が訊ねた空飛ぶ兵器――――P-36は、1930年代にアメリカ合衆国のカーチス社で開発された戦闘機だ。
アメリカ陸軍航空隊だけではなく、海を渡ってヨーロッパをはじめとして世界各国にも輸出された実績がある。愛称はホークで、アメリカ陸軍航空隊にとって初となる近代的戦闘機のひとつといえる。
機首の7.62mm機関銃だけでも生身の存在が相手なら十分すぎるほどの殺傷能力を持っているのに、それを大きく上回る12.7mm重機関銃が搭載されているのだからとんでもなく厄介な存在だ。21世紀になっても重機関銃弾などとして幅広く使われている世界レベルでのベストセラー商品なだけにその性能も折り紙つきといえる。
これらを思い返しただけでも、にとりはとっとと逃げ出したい気分になってくる。
しかも、亡霊たちはどこまで殺意全開なのか、このP-36は武装が強化されたC型で両翼に7.62mm機関銃が一挺ずつ追加されているのだから余計始末に負えない。
新たな敵は、濃密な弾幕で獲物を逃さない空の狩人――――ホークだった。
「じゃあどうするんだい? 地上はダメ、空もダメだってんなら動けないよ? まぁ、どっちかに賭けるなら空だろうかねぇ……」
このままじっとしているのは御免だよと、小町が打開策を要求する。どちらかを倒して先に進まなければ、追い詰められてジリ貧どころか“世界”が吹き飛ぶのだ。
「そりゃこっちも飛べるし小回りもずっと利くけど、だからって易々とカバーできる領域じゃないよ。あれをまともに相手しようとしちゃまずいんだ」
残念ながら、相手を行動不能に追い込むという点では、この場にいる三人の能力は火力に特化したものではない。つくづく戦力が自分たちだけなのが悔やまれる。
「でも、あの羽虫をなんとかしないと、戦車とかいうのを倒せなくなってしまいますよね。何か策はあるんですか?」
「それはこれから考えるんだよ! わたしだってどうすればいいかわかんないんだ! 状況が変わっちゃったからどうしようもないんだ!」
余裕のない声色で返しながら、にとりは高速で思考を展開する。
それぞれ単体を葬り去れるだけの武器・兵器ならこの場にある。
しかし、あるだけだ。
我が物顔でそれぞれの領分で動き回っているT-34とP-36Cだが、前者はパンツァーファウスト150で、後者は8.8cm FlaK 36で機能停止に追い込むことができる。
もちろん、結界のようなものではなく直接ぶつける兵器なので命中させなければ意味をなさない。
しかし、それ以上に厄介な問題があった。それらが真価を発揮するための“隙”を、現状では容易に作り出せないのだ。
特に8.8cm FlaK 36は取り込めれば絶大な効果を発揮する。長い射程と正確な照準によって戦車も相手にできるほど強力なのだが、その反面、三人程度ではまともに動かせない。
いや、もし動かせたとしても速攻でP-36Cを撃ち落とし、返す刀でT-34を一撃で破壊するなどという文字通りの神業ができるわけもないし、そうなった場合敵を引き付ける陽動役がいなくなってしまう。
「にとり、ここで悩んでいても解決しません。P-36Cはわたしが引き付けます。その間にふたりは戦車を潰してください!」
このままいたずらに時間を浪費できないと覚悟を決めた妖夢が飛び出していく。
「ちょっと、妖夢!」
「磨き上げたこの剣の腕と楼観剣……! あれなら斬れる! ……かも」
気炎を吐いて長刀を携え、P-36Cが待ち構えている高空へと駆け上がっていく妖夢。
限りなく間近に迫る死の気配前にしても、少女剣士から怯む様子は微塵も感じられなかった。
「あいつ――――」
残していった言葉のあまりの締まらなさに「せめてそこは断言しておけよ!!」と、見上げるにとりは叫びそうになるも、続いて湧き上がる「というか、なんでもかんでも斬ろうとするな! あとさっき一瞬見せた悲壮感はどこにいった!?」という呆れの言葉が混ぜ合わさり、結局なんと言っていいかわからなくなってしまう。
もっとも、彼女の胸中に渦巻く感情の中に打開策を見出せなかった自身への忸怩たる思いがあったのも否めなかった。
「まぁ、そう気を落としなさんな」
言葉を失いかけていたにとりに、小町が声をかけてくる。
「言いたいことは山ほどあるけど、なんだかんだといつもの妖夢だよ。でも……あんな博打みたいなやり方でも賭けてみないことには勝てやしないとあたいは思うけどね」
この状況でもブレない妖夢にさすがの小町も呆れ気味だったが、やがて表情を引き締めてにとりを見据える。いつもの飄々とした雰囲気の中に、どこか覚悟を問うような気配があった。
「……わかった。空は妖夢に任せてわたしたちは戦車を倒そう」
いくら考えたところで、常人を自認するにとりには“妖怪辻斬り”の心理など到底理解できないのだ。
何か代案が思い浮かぶわけでもないし、P-36Cのことは意気揚々と突っ込んで行った妖夢に託すとしよう。
「もし失敗して完全な霊体になっても、連中と一緒に襲いかかってこるようなことだけはしないで欲しいもんだけどね」
パンツァーファウスト150の発射筒を握りしめ、溜め息と共ににとりは軽口を発する。
「ははは、安心しなよ。その時は、あたいが真っ先に彼岸に運んであげるから」
「一応訊いておくけど、それはどっちを?」
「そりゃあ、どっちもさ」
なかなかに絶望的な状況だが、まだ心は折れていない。
己を奮い立たせるように言葉を交わし、ふたりは鋼鉄の獣を倒すべくふたたび動き出すのだった。