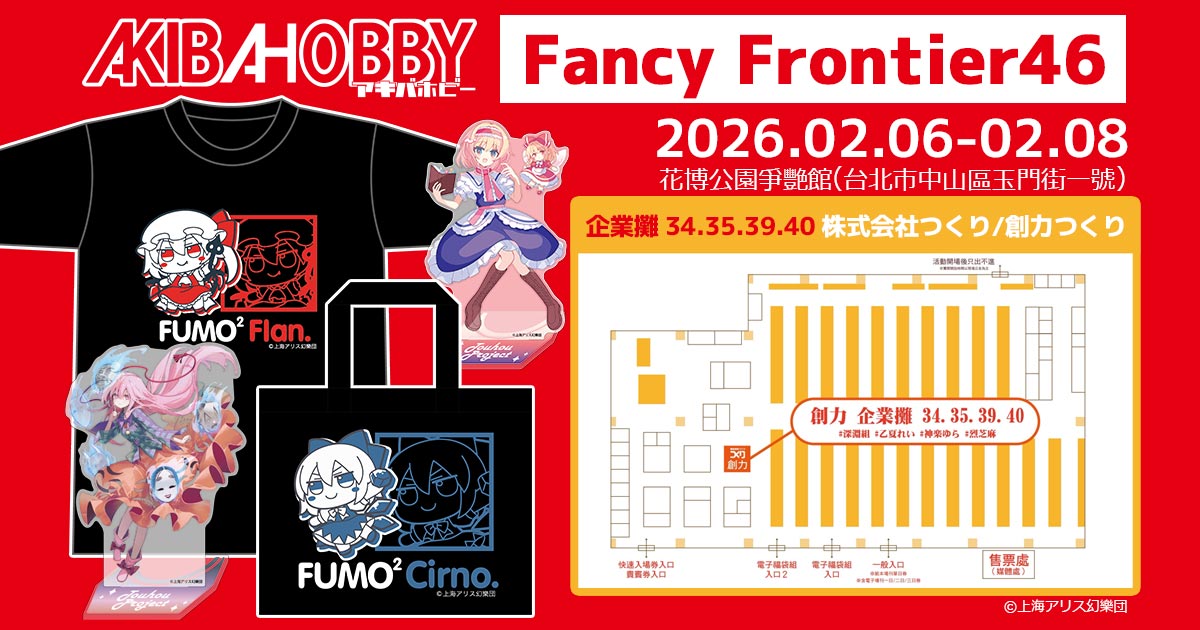【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第15回 趨走】
正午を過ぎて日が傾いていく中、森近霖之助は人間の里へ伸びる道をひとり急いでいた。
「冗談じゃないよ、まったく……」
やるせない思いから悪態が口を衝いて出た。
通い慣れた里への道を進んでいるというのに、はっきり言って気分は最悪に尽きる。
他に誰もやる者がいないとはいえ、久方の訪問が「危険が迫っているから気をつけろ」と告げに行くのだから気分など上がりようもない。
しかも、「本当は外から流れ着いたトンデモ兵器で幻想郷自体が消し飛びかねない」なんていう関係者以外には明かせない事情まで抱えているのだから、心労から憂鬱を通り越して胃まで痛くなってくる。
これなら「世捨て人になったから俗世なんかとは関わり合いになりたくない」とかそんなしょうもない理由で気が進まない方がずっとましではないか。
(あの兵器が起爆した場合の加害範囲を考慮すると、どう足掻いたって地上はどこもかしこも論外だ……。となれば、いっそのこと避難場所として地下に逃げ込ませてもらうっていうのは……)
こんな状況だというのに、どうにも霖之助は一度考えはじめると長考に入りやすい。
一旦思考に陥ることで自身が置かれている環境も忘れてしまう悪い癖を、頭を横に振る事で外へ追い出そうとした。
「あー、もっと普段から身体を動かしておくべきだったかな……」
そろそろ息が切れそうになっている。なにぶん彼は体力に自信があるタイプではなかった。
あるいは日頃の運動不足が祟っているのかもしれないが、それを嘆いている余裕さえ今はどこかへいってしまっている。
「おーい、香霖ー!」
息を切らせて走る霖之助の頭上に影が差し、そして張りのある可憐な声が降ってくる。
立ち止まっている時間も惜しいくらいだったが、声が自身にとって既知のものであるため、休憩がてらと割り切って霖之助は速度を落とした。
「ちょっと香霖ってば!」
一行に止まる様子が見られないことから霖之助が急いでいるのは察したらしく、影は高度と速度を下げて彼の横へと並ぶ。
普段なら行く手を塞ぐくらいのことはしてのけそうなものだが、今回は幸運にもそうはならずに済んだらしい。
霖之助が目だけを動かした視線の先では、片側だけに垂らした金色の三つ編みが揺れている。
これだけならばどこにでもいそうな少女と形容できそうなものだが、大きく世間と異なっているのは彼女が身に纏う服装だった。
大きな白いリボンが付いた黒い三角帽子に、白ブラウス・黒の服、白いエプロンと、ほぼ黒と白で整えられている。
これで仕上げと言わんばかりに箒へ跨って飛んでいるのだから、さながら絵本に出てくるような魔法使いのようにしか見えない。
あまりにもコテコテの格好だが、おそらく形から入ることが大事なのだろう。
「そんなに大きな声を出さなくてもちゃんと聞いているよ。なんだい、魔理沙」
「おいおい、それはこっちのセリフだぜ。そんなに急いでどうしたっていうんだ?」
彼女の名は霧雨魔理沙。一部種族そのものが魔法使いとなっている存在とは異なり、あくまでも人間の魔法使いだ。
霖之助とは彼が魔理沙の実家で修行していた関係もあってか、幼いころ今にまで続く長い付き合いとなっている。
これだけ聞いたなら浪漫のひとつもありそうなものだが、残念ながら両者はそれ以上の関係ではなかった。
下手をすれば道具屋に冷やかしに来て勝手に道具を持ち去ることもあるため、客ですらないし、知り合いでなければ盗人認定されかねない間柄だ。
「悪いけどまたにしてくれないかい? 里へ行かなきゃいけないんだ。ちょっとワケありでね……」
眉に皺を寄せながら放たれた霖之助の言葉を聞いた途端、魔理沙の目があやしく光った。
「おっ、なんだよワケありって。気になっちゃうんだぜ?」
――――しまった。これは余計なことを言ってしまったかもしれない……。
自らの失言に霖之助は軽く後悔を覚える。
気の多い魔理沙のことだ。適当にあしらっておけばそのうち会話にも飽きてどこかへ飛んで行っただろう。
しかし、細かいことまで考えている余裕のない彼は真正面から相手をしてしまった。
「なぁ、いじわるしないで話してくれよ~、香霖~」
我慢のできない子どものように、魔理沙が霖之助に近寄ってくる。もちろん、それくらいで彼が気をよくして話そうなんて考えることはない。
(あぁ……。こうなったからにはもうある程度正直に答えなければ魔理沙は満足しないだろうなぁ……)
「わかった、話すよ。ちょっとばかり厄介なことになってしまってね……」
歩きながらではあるが、より面倒な事態を回避するために霖之助は観念して重い口を開くのだった。
◇◆◇ ◇◆◇ ◇◆◇
「はぁっ!? 地獄から溢れた亡霊たちが外から流れ着いた兵器を依り代にして暴れまわってるって!?」
霖之助の説明を受け、魔理沙は跨った箒から転がり落ちそうなほど驚いた。
そこまで反復しなくてもいいと思うんだけれど……と霖之助は思うも、突っ込むと話が長くなるため触れずにおく。
「そうだよ。だから意図せずして事件に関わった僕が、里まで行って注意を促すために走ってたのさ。備えもなしにいきなり襲われでもしたら困るからね」
嘘は言っていないが、ぼかしている部分が多すぎて気が引けてくる。
罪悪感に苛まれながらも霖之助は本当のことを言うわけにはいかなかった。
いくら注意喚起したところで、最終的に阻止失敗した凶悪兵器ツァーリ・ボンバが起爆してしまえば、この幻想郷のすべてが一切の例外も許さず吹き飛ぶのだ。
しかし、それを口にしようものならとんでもない混乱を引き起こしてしまう。
「なるほどなぁ。それなら肉体派じゃない香霖が急ぐのも納得できるってもんだぜ」
「べつに運動不足なだけで虚弱体質なわけじゃ……」
どうにも認識の齟齬があるようだ。
憮然とした霖之助が反論しようとするが、すでに魔理沙は人の話が耳に入ってくるような状態ではなかった。
「わかってるわかってるって。……よーし、それならわたしがそいつらを退治してきてやるよ!」
「えっ」
予想外の言葉に霖之助は言葉を失う。
先ほどまで魔理沙は驚きを浮かべていたため油断していたが、いつの間にかその瞳は爛々と輝きだしていた。
すでにどこからどう見ても関わる気満々である。こうなっては止められる気がしない。
「いやぁ、いくらなんでも魔理沙が危険に関わる必要はないんじゃ……」
さすがに恩人の娘を危険に突っ込ませるわけにはいかない。
いつもは異変を聞きつけて止める間もなく解決しに飛び出して行くのだが、事前に知り得たのだから年長者としては考え直させるべきだろう。
「なーに言ってるんだよー、香霖。そんなこと言っていられないから急いでいるんだろ?」
指摘されたがまさしくその通りだった。
気が付けば里が遠くに見えつつある。
「そりゃそうだけど……」
「わたしだって里のことは心配なんだぜ? ただ、さすがにちょっと顔を出しにくいからさ……。まぁ、そこは香霖に任せてやるからありがたく思ってくれよな」
一瞬ではあるが視線を里へ向ける魔理沙。
彼女はいろいろあって実家を飛び出してきた“ワケあり”の身ではあるものの、それでも自分の見知った者たちに災禍が降りかかる可能性があると聞けば心配にもなるのだろう。
本当に素直じゃないなコだな……。霖之助はそう思う。
「よし、わたしはもう行くぜ! 里には寄らないでおくけど、みんなによろしく言っておいてくれよなー!」
そう言うやいなや、魔理沙は箒の頭を引き上げそのまま一気に空中へと舞い上がる。
あっという間に速度を上げて、午後の白みを増した空へと去っていく魔法使いの少女。
「まったく、素直じゃない上に自由なコだな……」
遠くの空へと消えていく魔理沙を見送った霖之助は、十分な休息ができたと気を取り直して最後の頑張りだと走り出す。
そのまま立ち止まらずに進んでいくと、里の入り口で顔見知りに出会った。
「む、霖之助じゃないか。そんなに息を切らせて珍しいじゃないか。いったいどうしたんだ?」
膝に手をついて肩を上下させる霖之助にかけられる張りのある声。
「や、やぁ、慧音……」

息の上がった状態では相手の名前を呼ぶのがやっとだった。
慧音。上白沢慧音。
人里の守護者であり、半獣であり、半人であり、寺小屋の先生と様々な肩書を持つ実に稀有な存在ともいえる少女だ。
さらにいえば、香霖堂の売り上げに貢献する上客でありながら、良く値切る厄介な客でもある。
あらためて考えてみると、どうにも肩書が多い。
「ちょっとばかりよくない事態になってしまってね……。君の知恵を借りに来たんだよ……」
ふたたび無理に走ったことで上がってしまった息を整えながら、霖之助は軽く手を掲げて言葉を返す。
まさかもっとも探していた相手と最初に出会えるとは。
特定の神は信仰していないが、霖之助は内心で運命に感謝する。
ここでもうすこし彼が冷静であれば、運命に感謝などすることはなかったに違いない。
この世で起きている諸々の事柄がすべて運命の仕業だとするならば、それは幻想郷に厄介なものが流れ着いた今回の件さえも運命の仕業となってしまう。
どう控えめに見ても、住まう場所を破壊しようとする意志に感謝などできようはずもない。
運命が自身にとって都合のいいことばかりを運んでこないと頭ではわかっていても、理屈だけで割り切れるものではないのだ。
そう考えれば、このタイミングで彼の意識がそちらに向かわなかったのは幸運であるだろう。
「頼りにされるとあれば悪い気はしないが、わたしの知恵が必要とはいささか大げさじゃないか?」
口にした言葉と反してまんざらでもない様子の慧音。
頼られるのは悪い気がしないのだ。
そもそも彼女と霖之助はなにげに付き合いが深い。
なんなら魔理沙よりもずっと長いくらいであるが、それは両者が共に妖怪の血を半分ほど引いているため長い寿命を持っているからでもあった。
境遇が似ているといえばそれまでだ。ともすれば“半端者”と蔑まれる者同士が感じる同情の類かもしれない。
しかし、だからこそ築くことのできる関係性というものは確かに存在していた。
なし崩しにくっついたりしないのは、互いにあれこれと余計なことを考えてしまう悪癖があるからだろう。
とはいえ、そんな微妙な関係性に心地よさを感じているのもまた事実だった。
「いやいや、君は自分のことを過小評価してやいないかい?」
「そうか? わたしはわたしにできることをしているだけだぞ?」
霖之助からすれば自分の価値がわかっていない人間のセリフだった。
ただただ考えばかりに没頭して商売とも言えない道具屋を営んでいる自分とは違い、慧音は確固たる力と意志をもってこの里を守っている。人との関わりを断つように森へ移り住んだ自分とはまるで違うものだ。
同じ境遇でありながら彼女には眩しさがある。
でも、不思議と霖之助に不快感は生まれない。過ごした時間が長いからこそ、結局は自分に合った場所で生きていると思えるのだ。
「そうかもしれないな。じゃあ、そんな君を見込んでの相談なんだけど……」