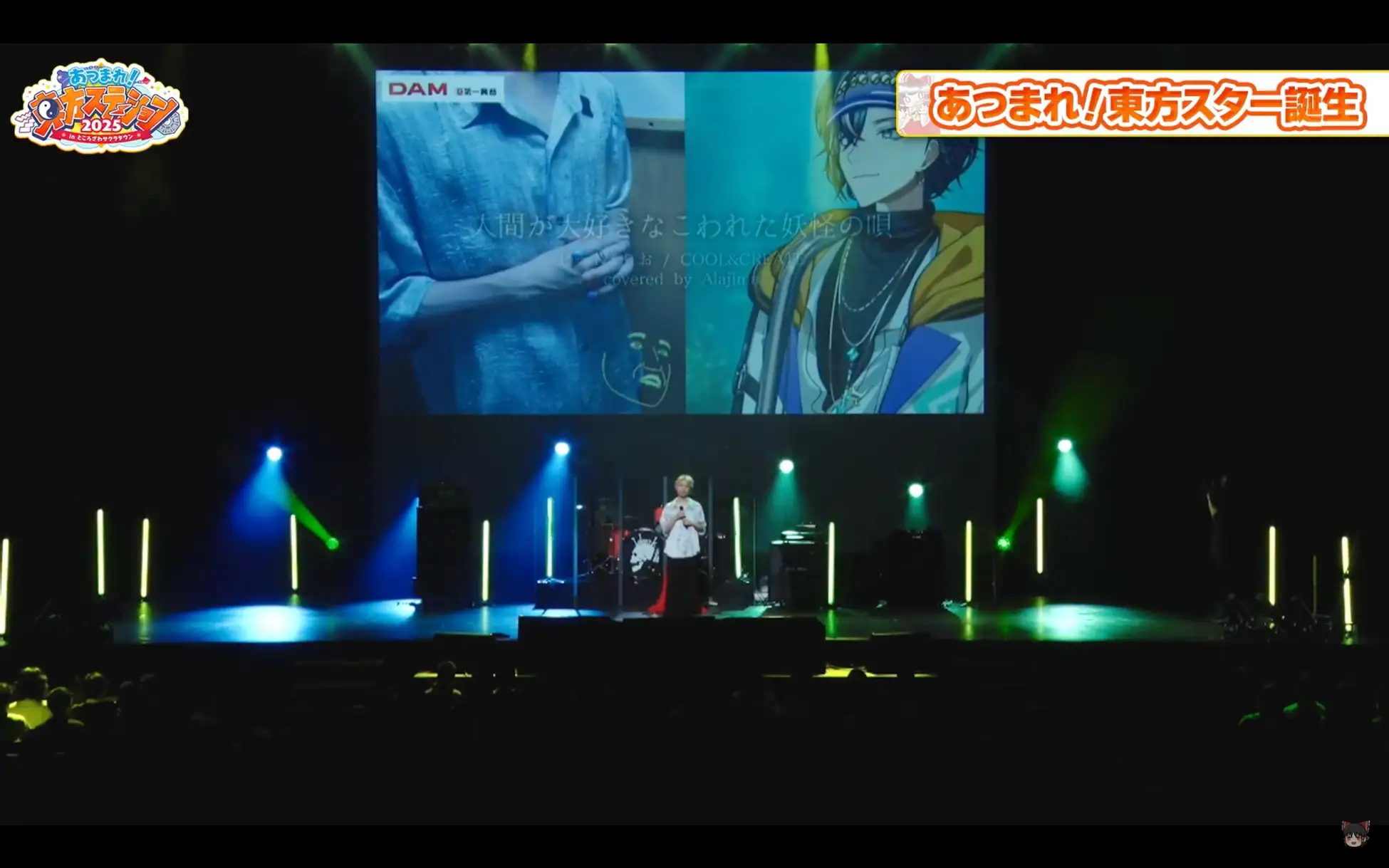「原曲でよくない?」アレンジなんてする必要はないのでは、という問題意識 RD-Sounds(凋叶棕)インタビュー
RD-Sounds(凋叶棕)インタビュー 第1回

東方の二次創作には、様々な形があります。 ストーリーを基にしたもの、キャラクターを基にしたもの、音楽、世界観、元ネタ、メタネタに至るまで……… コレほど余す所無く、一次創作=原作のあらゆる所を題材としている二次創作ジャンルは、他には無いのではないでしょうか。 それは「東方Project」というゲームが、何処をとっても、誰かの琴線に触れるものであるからかもしれません。
今回は、サークル「凋叶棕」のRDさんに、 東方楽曲をアレンジすることについて、東方Projectという作品そのもの、登場するキャラクターについて思うことなどを、 RDさん自身の「オタク遍歴」に触れつつ、紐解く形でインタビューさせて頂きました。
(取材は2019年12月に行われました)
取材:杉江松恋・斉藤大地・西河紅葉
文:杉江松恋
「東方Project」の総合演出としての面白さ
——はじめに自己紹介をお願いします。
RD:
コンポーザーおよびアレンジャーとして活動しています。東方としてはもちろんアレンジャーとなるんですけど、第一回例大祭から参加はしていまして、2005年の第二回に楽譜の本を出したのがサークルとしての最初、2007年にC73でアルバムの『祭』を出して、今まで活動を続けているという感じです。

——例大祭の第一回からピークまで、東方に人が増えていった時代のことを龍道さん、JUNYAさん、ビートまりおさんに伺ったのですが、まさに嵐のようだとおっしゃっていました。その現場に立ち会っておられたわけですね。RDさんはインディーゲームを精力的にプレイされていますが、まずはゲームとしての東方Projectの魅力をお聞きしたいなと。
RD:
ゲームには、単純にプレイする面白さの他に総合演出としての面白さがあると思っています。総合演出っていうのは、音楽とか、見た感じのビジュアルの素晴らしさも含めたものですね。たとえば「妖々夢」のラスト一連の流れとか、「永夜抄」全体、特に4面で霊夢と魔理沙がボスとして出るところなんかは、音楽も、操作キャラクターが出演するという意味でも、背景なんかも全てがカッコよくて、当時めちゃくちゃ熱くなりました。こういうビジュアル、音楽、ゲームプレイ全部が合わさった総合演出が好きでたまりません。最近だと「鬼形獣」6面です。なんといっても史上初の撤退戦ですからね。背景が逆に流れていって、もうビビりました。「イドラデウス(偶像の神)」という名称も古きシューティングを連想させます。「ゼビウス」のような。そういう演出が素晴らしいというのがありますし、あとは単純に、難しいゲームへ挑戦の魅力もあります。やっぱり、できなかったスペルカードが取れるようになった瞬間というのはめちゃくちゃいいものです。
——階段を上がっていくレベルデザインの楽しさと、アートとかストーリーとか総合演出としての楽しさの2つがゲームにはあるということですね。
RD:
ゲームの難しさは色々な側面があると思います。面クリア式の場合、道中の戦略も考えなければなりません。各面のここでこれだけ稼ぎエクステンドし、ここでゴリ押して、という計画を考えるような感じです。4面まで残機をためこんで、5面で一気に削られて、ギリギリ6面を突破できる、みたいなことも結構ありますが。「紅魔郷」とか、咲夜さんにどれだけ削られたことか(笑)。そういうのは、やっている最中にミスをしたりすればすごく悔しいんですけど、計画がうまくいってクリアしたときは最高です。例えば「地霊殿EX」は私の場合クリアまですごく時間がかかったので、相当色々な計画を立ててはやり直しをしました。最後のほうになるとやっぱり手に震えがくるんですが、そういうのもたまらないんですよね。
——緊張感のデザインがすごく上手ですよね。
RD:
東方ってスペルカードを作りたいがために今のシステムにしたっていうのもあると思うんですけれど、全体としてスペルは美しい絵になっていることが多いですよね。そういうところもすごく素敵だと思います。
——ZUNさんは基本のシューティングにいろいろなゲームデザインを付け加えているじゃないですか。そういうゲームシステムの中でどれが一番好きですか?
RD:
好きなのを3つ挙げると、まず「永夜抄」です。「永夜抄」の刻符のガリガリ感はたまらないですね。道中は高速主体、ボスは低速主体で切り替えたりして、ガリガリと刻符がたまっていくあの音がたまらないです。次に好きなのは「地霊殿」で、あれは被弾さえしなければ残機を確保できる。つまりボムを使ってでも生き延びさえすればよいというのが気に入っています。あとは最近でいうと「輝針城」ですね。×2.0【※】が出るときの気持ち良さはたまらないです。最近は魔理沙でカンストする楽しさを発見しました。いつも伝統的に霊夢ばっかり使うので。逆にシステム的に苦手なのは「星蓮船」のUFOです。「鬼形獣」で復活しましたが、あれは「星蓮船」ほど集める縛りが厳しくないと感じているのでちょっと違いますね。あと「風神録」は被弾すればするほど自分に優しくなくなっていく、ボムを使えば使うほど弱くなっていくというのが、個人的にはバランスが厳しいと感じます。
【※】×2.0:アイテム自動回収時のボーナス倍率がマックスの状態。「輝針城」では、アイテムを同時に複数個回収することで得点にボーナスが付く。 60個以上同時に回収すると最大値の「×2.0」ボーナスになり残機のかけらが発生する、という利点がある。
——ストーリーという観点から見るとどうですか。
RD:
「風神録」までとそれ以降ではかなり話が変わってきていますよね。昔は異変が起きたら巫女が殴り込んで、殴って最終的にお酒飲んでおしまい、みたいなパターンだったですけど、最近はどちらかというと主人公たちが大きな陰謀の中で利用されているというパターンが結構多いし、一作品で完結しない大きな流れの中に各作品が置かれているという感じがあります。単発の異変を見るというよりは、キャラや勢力ごとのストーリーがあって、それを追いかけていくという方向に変わっていっているのかなと思います。個人的には「永夜抄」の完結っぷりが一番好きですが、ワンパンかましてスカッと終わるか、長いサーガになっていくか、という違いかなと思うので単純に良し悪しは比べられないかなとは思います。

原曲の魅力とアレンジをするということ
——ZUNさんが「音楽を作りたくてゲームを作り始めた」と言われているように原曲の魅力が必須要素としてあるのが東方です。そちらについて伺えますか。
RD:
私はゲーム音楽で育ってきたも同然なのですが、最初に東方でいいなと思ったのは「上海紅茶館」でした。この曲すごくいい、と思って次に「明治十七年の上海アリス」ですっかりやられて、紅魔郷から当時最新の妖々夢まで一気にプレイして、そのあと神主のサイトで公開されていたMIDIを聞いてすっかり魅了されました。あとはもうずっと虜です。「ZUN進行」と個人的に呼んでいるコード進行があるのですが、それにはまったということなのかもしれません。また印象的なのは「レソラドラソ」、これはセブンスサスフォー(7sus4)をバラした音で、「テーマ・オブ・イースタンストーリー」として各作品のタイトル画面で使われているメロディです。厳密に言えば「レソラドラソ」の音程ではないのですけれど、「永夜抄」のタイトル画面のレソラドラソという音が個人的に一番印象的だったので私は便宜上そう読んでいます。そしてそれが「竹取飛翔」の一番盛り上がるところで使われていて、それはもう感動しました。どこかにこの基本テーマが鳴っているというのが美しいです。ちょっとだけ和風でもあってちょっとだけ中国風でもあって、あとはオリエンタル、オクシデンタル、全部混ぜて、その上でどこかによりすぎないようにしているのが聴いていて安心するというか楽しいです。
——なるほど。
RD:
楽器でフォーカスするとピアノです。神主は時として絶対に弾けない暴力的なピアノを書かれるんですよね。私はこれでピアノっていうのは弾けなくてもいいんだっていうことを知りました(笑)。昔、有名な作曲家さんが「人間って息を吸えないと歌えないんだということに気付いた」とおっしゃったことがあるんですけど、いつか神主も「このピアノは弾けないんだ」ってことに気付くのかもしれません。でも、それはそれで弾けないピアノのままでいってくださいと思いますね(笑)。
——いわゆるZUNペットってどうですか?
RD:
トランペットは聞くとああ、神主の曲だなと安心します。『幽霊楽団 〜 Phantom Ensemble』のサビは三人が適当に、思いっきり好き放題演奏している感じなんですけど、あれでトランペットの素晴らしさをはっきり意識しました。
——そういう魅力ある原曲を、アレンジする快楽というものがあると思うのですが。
RD:
いや、快楽はあまりないのかもしれません。原曲を聴けばそれでいいのだから、アレンジなんてする必要はないのではと私は常々思っています。原曲が一番素晴らしくて勝てないし、勝つ必要もない、というか勝負などしてはいけない。でも「真に美しいものを見たときに人はどうするか」という話なんですが、こういうときってその美しさに打ちのめされて沈黙してしまうんですけど、それと同時に、その美しさについて声を上げざるを得なくもなるんです。オタクとして。これが美しいんだよ!!って。そういう想いがあるので、アレンジすることを止められない。それが快楽なのかどうかは、よくわかりません。
——魅力なのか、とりつかれてしまう、なのか。
RD:
とりつかれるっていうのはそうですね。こう言ってはあれなんですけど、アレンジ曲を聴く必要はないと思います。原曲さえ聴いていてくれればそれでいいと思います。二次創作などの露出が増えたからか一般の場にも東方Projectが登場する機会が増えたと思うのですが、そういうときって何かしらアレンジされたものが出てくることが多くて、原作そのものがきちんと出ているわけではないじゃないですか。入り口はなんでもいいんですけど、ちゃんと原作に到達して、そこが源泉なんだよということをちゃんと見てほしいです。東方を盛り上げましょう! みたいなことを言うのはまあわかるんですけど、別に盛り上がらなくても、神主がいてさえくれれば私はそれでいいんですよね。アレンジしていることを自負しはじめたりする度合いが増していくとやばいなと思っていて、常に「二次創作なんですよ、これは」と言う必要があると思います。
——二次創作は、創造主から許されているけど罪である。単純にもっと原作のいいところを知ってほしいという想いですよね。今日は原作の魅力についてまずとことん語っていただきたきたいと思います。幻想郷それ自体の設定についてはどう感じていますか?
RD:
幻想郷ってちょっと怖いところがあって、不吉なモチーフを明るく描くのが多いと思います。たとえば(火焔猫)お燐ってモチーフがものすごく不吉で不気味な存在ですよね。ただ本人のキャラクターはすごく明るい。そういう縁起の悪いものを明るくストレートにぶつけてくるところが好きなんです。幻想郷は平和ではないと私は思うんですけど、平和ではないが故に平和というんでしょうか。みんなが刃物を笑顔で向け合っているような空気感がいいです。
——もうひとつの特徴が「忘れられたものが流れ着く」というところですね。こちらについてはいかがでしょうか。
RD:
最近流れ着くものは、あんまり忘れられていないような気がします(笑)。でもAIBOとか思い返せばもう大分過去の物体ですね。さておき、幻想郷に入れる宇佐見の登場でちょっと話が変わりましたよね。あと、忘れられたものが幻想郷にたどりつくのを見て、ファン層がそれに再び注目し始めるというのは業だと思います。最近だと追いやられた神である摩多羅神がそうですよね。忘れられたものがたどり着く場所というのにはロマンがあるようにも思います。オタクって昔から人権がないみたいに言われることがあったんで、ああいう「行き場のない者が集まる場所」という設定にちょっとした憧れがあるのかな、ともちょっと思います。
——ZUNさんが見てきた景色やオタクや同人の環境がストーリーに入り込んできている感触はありますね。シューティング自体、幻想郷が作られた当時は忘れられていたものですから。現実とのシンクロニシティを感じます。
RD:
でも難しいのは、神主がいろんな景色を見て来られた上で幻想郷は出来上がっているわけじゃないですか。その根元は果たして追いかけるべきでしょうか。ファンが神主と同じ世界を見る必要があるかどうか、という話です。元ネタを通して同じ景色を見たいという気持ちはわかります。でも私が見たいのはあくまで神主というフィルターを通した世界であって、根元を見て、あるいはそれへの理解は深まるかもしれないけど、神主というフィルターを通せなければそれ以上の意味はもしかしたらないんじゃないかとも思うんです。神主が何を考えているかに思いを馳せるとしても、そこから先を探るのは悩みどころです。あくまでも神主の表現する世界だけを見ていればそれでいいんじゃないかと思わないではいられません。
——フィクションは、フィクションのところをまず見ようといったところですね。ZUNさんも、元ネタに対する言及を避けるときもあれば触れるときもありますし、東方と自分がダブるのを避けるときもあれば、むしろ意図して行われることもある。その曖昧さ、逡巡が生まれることそのものが魅力という面もありますね。フィクションレベルに話を戻すと、ファンにとっては霊夢と魔理沙が感情移入の対象になると思うんですが、二人についてはどうお考えでいらっしゃいますか。
RD:
霊夢は誰に対しても平等で、幻想郷のことを考えている。それに対して、妖怪はみんな霊夢にちょっかいを出していて、リアクションを楽しんでいるふしがありますよね。魔理沙はそれに倣っているんじゃないのかと思います。魔理沙は霊夢が大好物というのは公式設定ですが、霊夢に一番近いところで彼女は妖怪の動きをやっている感じがありますね。そういう意味ではレイマリって難しいですよね。霊夢は誰に対しても平等ということですけれど、例えば小鈴のことはやたらと守っていたなと思います。もしかしたら「人間」というレイヤーは保護対象として別格扱いになっているのかもしれない。でもそれだと魔理沙はどっちなのか。人間扱いなのか妖怪扱いなのか、微妙なところ、みたいになっているのかもしれない。
——霊夢は元々、設定上の特異点なんですけど、魔理沙は感情移入の特異点だと思っています。魔理沙は妖怪になる可能性を常に残しているじゃないですか。魔法使いになるかもしれない。妖怪と人間、どっちでもある魔理沙をすごく感じるんです。
RD:
どっちでもあるというのは、メタ的には多分正しい気がします。というのは、魔理沙はプレイヤーとゲームとの橋渡し役のはずなんですよね。東方の起動アイコンは大体魔理沙ですし、そういう意味ではプレイヤーを幻想に導く入り口なんだと思います。なので、どちら側の場にも等しく立っているという感じがあるんですね。霊夢は魔理沙を、人間なんだけど人間じゃない、変なやつ、という目で見ているのかもしれないです。人間の部分は多少甘く見るかもしれないですけど、妖怪の部分には平等に厳しく対応する、というような。半人間、半妖怪なのかなと思うところがあります。なので、霊夢と魔理沙って、極めてきわどいバランスの上に立っているので、いつ崩れてもおかしくないのかもしれません。

——バランスなんですよね。どっちに倒れてもおかしくない場所をずっと歩いている感じ。入門編として霊夢と魔理沙をみると、東方の本質が見えるような気がします。
(第2回へつづく)
「原曲でよくない?」アレンジなんてする必要はないのでは、という問題意識 RD-Sounds(凋叶棕)インタビュー おわり