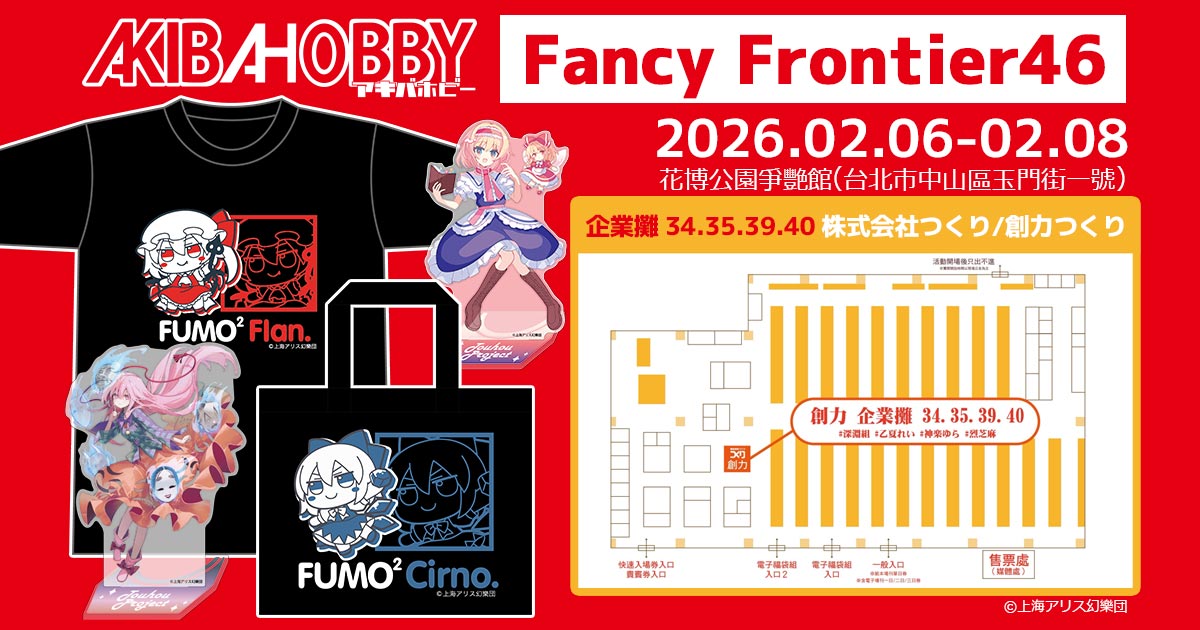【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第7回 兵器】
なにごとにもはじまりがある。いや、正確には原因と呼ぶべきであろうか。
どのような異変であれ、それはなにかを起点としている。
もし事件に関わった者たちがその中心にいる人物たちの名を知ったとすれば、きっと溜め息を吐きつつも仕方ないことだと納得したことだろう。
「……おや、これはこれは。ずいぶんとめずらしいお客様だ」
香霖堂のカウンターで、主人である森近霖之助は読んでいた本から視線を上げた。
視線の先には悠然と佇むひとりの女性の姿。
ドアが開いた気配はなかったため、おおかた彼女の能力である境界をいじり、そこからやって来たのだろう。
反射的に「せめてドアから入ってくれないか」と言いかけるが霖之助はそれを止めた。
目の前の相手にそんなことを懇々と説いたところで意味がないことを思い出したからだ。
「こんにちは」
霖之助の前に立って挨拶の言葉を口にした女の名は八雲紫。
この幻想郷における最古参の妖怪の一人にして、最強の一角として数えられる内のひとりであり、そして同時に賢者とも称えられる存在だ。
幻想郷を包む博麗大結界の提案者にも名を連ね、幻想郷の創造にも関わっているとまことしやかにささやかれている。
「今日はいったい?」
「ちょっとお願いがあって来たのよ」
やや特徴的ではあるが、それでも優雅さを損なわない瀟洒な造りの傘をそっと肩に添えて、紫は蠱惑的な唇を笑みの形に歪める。
「あなたからのお願いとはなんともぞっとしないね」
「ふふ、そう身構えないでちょうだい」
室内にもかかわらず傘をそのままにした紫はあくまでも嫣然とした笑みを崩さない。
「そう思うなら、もうすこし普段の言動を顧みられてはどうかな?」
「あら、心外ね。幻想郷のためにいつも奔走しているじゃない」
奔走しているのは本人ではなく主に使役される式神だ。もちろん、霖之助はわかった上で口を挟まない。
「そうかもしれない。でも、それが原因となって招いたトラブルは?」
「まぁ、ないとは言えないかもしれないわね」
どこからともなく扇子を仰ぎながら涼しげに微笑む紫。
しかし、霖之助の指摘に心当たりがあるのか口元はいつの間にか扇子で隠されていた。
「ほら、身構えたくもなるだろう?」
「……ひどい。やっぱり納得がいかないわ」
会話を盛り上げるための冗談であれば良いが、彼女との長い付き合いから導き出された答えからするとは本気でそう思っているようだ。
これはダメだと霖之助は早々にこのまま会話を続けていても不毛に終わると諦める。
「それで、このしがない道具屋にどのような用件が?」
もっとも、この主人も癖の度合いでは負けていなかった。
店に並ぶ得体のしれない外の世界の品々はどこからか拾ってきたものだというが、幻想郷で滅多に見ることのない異界の物がこうも都合よく手に入るとなれば疑問を感じずにはいられない。
もちろんそこには八雲紫の存在が関わっていた。
「正直ね、道具屋さんに頼むものかはわからないけれど、ちょっと処理してしまいたいものが流れ着いてしまったのよ」
そこでおもむろに踵を返す紫。
どうやらついて来いということらしい。
小さく肩を竦めた霖之助は椅子から立ち上がって紫に続いて扉へ向かう。
その際、営業中の札を「外出中」に変えておくのも忘れない。
しばらく歩いて人気のない場所へと辿り着くと、そこには大量の鉄の塊が積み上げられるように存在していた。
「これは……」
それぞれ種類も用途も違うのか、その形から何からそれこそ大きさもまちまちだ。
「外の世界の武器――――いえ、“兵器”よ」
そう言葉を放つ紫の表情には普段の底知れぬ笑みは存在していない。
霖之助もそれを感じ取り、しばしの間言葉を失うこととなる。
幻想郷には時折、外の世界で忘れ去られた存在が流れてくる。
元々は妖怪が外の世界で力を失いつつあることを利用して、その正反対の性質を持つ結界に閉ざされた“世界”を創造したわけだが、そのロジックでいくと、神秘の存在でなくとも多くから忘れられた存在はこの世界へとやってくるのだ。
「今までも細々とした物はあったけれど、まさかこんなものが流れつくなんてね。さすがに僕も思ってはいなかったよ……」
「……外の世界では、もう長いこと大きな戦争も起きていないわ。それこそ、“大戦”という概念が忘れ去られるくらいにはね」
まるで見てきたように語る紫だが、目の前に存在する未知の群れを前にした霖之助は完全に興味をそちらに取られていて違和感に気付かなかった。
「平和なのか次の戦争のための準備期間なのか……。いずれにせよ外の世界が進歩する速度ははっきり言って異常だよ。特にこの100年くらいはね」
「そうね」
「二度の大きな戦争が膨大な命を呑み込み、そしてそれを代償として多くの技術を進歩させた。あるいは、より多くの命を呑み込むためかもしれないけれど」
紫に呼応するように、なにやら語り出す霖之助だが、こちらが持っている情報はあくまでも流れ着いた書籍によるものだ。
人類が長いこと月に関する話題を失っているせいで、香霖堂の本棚にもアポロ計画の書物が並び、月に行こうとする者がそれを求めに来たことさえあったほどだ。
そして、月ほどではないにしても、長い間多くの人間から忘れられている戦争についても同じことが起きないとは限らず、その結果として霖之助にも知識だけは存在していた。
「技術の粋を集めた兵器なんていっても使える者がいない幻想郷では意味のないものだわ」
「ごもっとも。でもそれならどうして僕のところに?」
「万が一の事態が起こらないとも限らないからよ。こういう時の勘はよく当たるの」
幻想郷を長きに渡って見つめてきた妖怪が言うと妙な説得力があった。
「それにね、なるべく早めに片付けてしまいたいものがあるのよ」
紫が視線を向ける先には巨大な物体が鎮座していた。全長だけでも十メートル近く、直径でも太いところで成人男性の身長よりも大きい。
一見しただけでは紡錘形の金属の塊が転がっているようだが、それゆえに正体がなにとわからずとも幻想郷にとって異様な存在であると肌で理解できた。
「これは?」
「バラせるアテを知らないかしら?」
霖之助からの質問には答えず紫は話を進めようとした。この様子からするに、できることなら説明すらしたくないようだ。
「いきなりだね。なにをするにしてもそもそもこれがなんなのかくらいはわからないと……」
「……よくないものよ」

忌々しげに語る紫の言葉を裏付けるように、空気を通して伝わってくる禍々しいオーラ。
妖気が発生しているわけではない。しかし、なぜか霖之助にも即座に感じ取ることができた。
こんなところにあってはいけないものだと。
「それはわかる。でも訊きたいのはそんなことじゃなくて――――」
そこまで口にして霖之助は言葉を止めた。
彼の持つ“道具の名前と用途が判る程度の能力”が発動したためだ。
「ね? あなたならわかるでしょう?」
「そうか……。他のものも大概だけど、中でもこれは極めつけにどうしようもないものだね」
「そんな気はしていたけど、そこまでのものなのね……」
「ほら、間欠泉騒動の時に、八咫烏の力を与えられた地底の妖怪がいただろう? あの力を物体を破壊するためだけに極限までつきつめたものだよ」
さすがの霖之助も、判明した用途について言葉に出すことはしなかった。いや、できなかった。
正式名称AN602、通称“ツァーリ・ボンバ”――――半径数十キロを吹き飛ばすどころか超高熱の熱戦が襲いかかる。威力を秘めた爆弾なんて、霖之助の常識を遥かに凌駕するもので口にすることすらおぞましいものだったのだ。
どう考えてもこれが本来の役目を果たすだけで、幻想郷は――――終わる。
「やっぱりそうなのね……。であれば、なおさら早いところ始末しなければね。こんなもの……幻想郷には要らないわ」
扇子で口元を隠しながら紫はつぶやく。まるでその下に浮かぶ表情を見られないとするかのように。
「あの八咫烏を見ればわかるように、エネルギーは使い方次第で大きな恩恵を生み出すとは言うけれど、下手をすれば本当にこれだけで幻想郷そのものが文字通り吹き飛ぶかもしれない」
「厄介なモノはあのおバカな妖怪――――いえ、ここに今暮らす連中だけで十分なのよ」
それは紫の偽らざる本心だった。
そんな彼女の様子を見る霖之助は小さく肩を竦める。
「こんなものは要らない、か……。かつて二度に渡って月の技術を奪おうと侵攻を目論んだ妖怪の発言とは思えないね」
「あの時とは事情がまるで違うわ。月の技術と外の技術はまるで違うものよ。外のだってあなたも知っているようにけしてバカにはできないけれど、同時に危険なものもある。これらのように良からぬ結果を招くであろう技術をわたしは求めていない」
「それは人間が力を――――」
「たとえ思っていても、それ以上は口に出さないことをオススメするわ」
音を立てて扇子を畳み紫は霖之助に視線を向ける。笑みは崩していないが目は笑っていなかった。
「おっと、口が過ぎたようだ」
小さく掲げた手を振って 霖之助は沈黙を選ぶ。
これ以上はお互いのためにならない。そう判断できる程度には彼も引き際を心得ていた。
「それでこれの処理は頼めるのかしら? わたしはあなたが適任だと思っているのだけれど」
「興味はあるね。あとはそうだな……。もしかしたら“彼女”であればこれをどうにかできるかもしれないか……」
本題に戻って霖之助は思案する。
ざっくりとしかわからない未知の技術ではあるものの、同じような性質を持つ者のなら案外これをどうにかできるかもしれない。
それこそ新しくこの幻想郷に引っ越して来た神々も絡んで、日夜地底でなにやら怪しいことをしているのだ。
万が一被害が出るとしても、地下深くのあそこならそれを最小限に抑えられるかもしれない。
脳内で素早くそろばんを弾く霖之助。
さっそくどうにかしようと思考を始めた彼を見て紫は安堵する。
「まぁ、彼女だけでは心配だ。ここは河童たちの力も借りようじゃないか」
「その様子なら任せても大丈夫そうね。あとは頼んだわよ」
言葉だけを残し、紫はスキマへと消えていった。