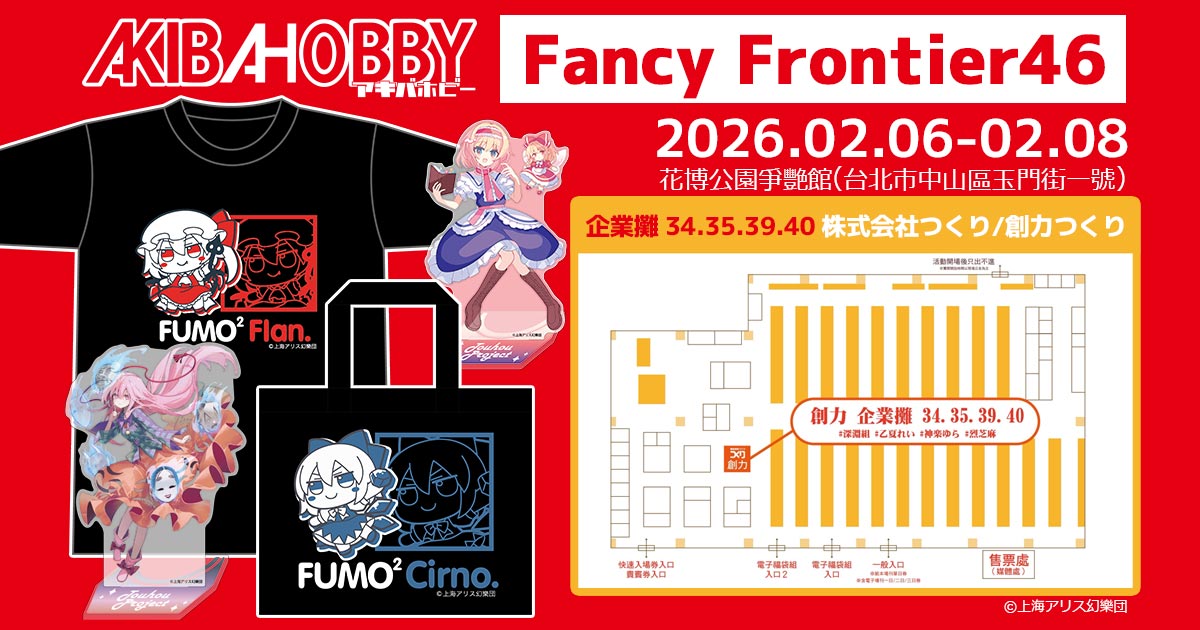【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第66回 死神】
照準器に表示された十字線の向こうで、超音速の弾丸に頭部を吹き飛ばされた亡霊が、のけぞりながらに力なく倒れ込んでいく。薄暗い闇の中でもそれだけははっきりと見えた。
「いよっしゃぁー!!」
銃把は握ったまま照準器から目を放し、小さく拳を握り締めながら声を上げた小町。
そのわずか数秒後、小町の側頭部近くをまったく別の方向から飛来した銃弾が通過していった。空気が引き裂かれる衝撃波が唸りを上げて耳朶を強く打つ。
「うおおっ!?」
視界の端を弾丸が走り抜けたような気がして思わず大声が出た。
いや、そんなものは些末事だ。
もしも顔を動かすのがあと1秒遅れていれば、小町も倒した亡霊と同じ運命を辿っていたかもしれない。そう気づくと同時に恐怖が湧き上がってくる。
『小町、ぼさっとするな! 今すぐそこから動け! 狙撃手はひとりじゃない!!』
「そ、そういうのは撃つ前に言ってよ!!」
にとりの声で現実に戻った小町は、距離を操ってすぐさま建物の陰まで避難した。
さすがに今のは肝が冷えた。そればかりか早鐘を打つ心臓の鼓動に合わせて全身から変な汗まで噴き出てきている。
これで安全圏に逃げ込めただろうか? いや、もしも他のヤツが自分を補足していたとしたら――
とりとめもない不安が次々に鎌首をもたげてくる。
「そういうことか――」
頭頂部から周囲の冷気が体内に流れ込んでくるような感覚。錯覚なのは頭でわかっているがそれでも止まってくれない。
これも含めて狙撃手の効果なのだ。小町は理性よりも先に本能でそう理解した。
『相手が何人いるかもわからないのに先に言えるかよ!』
危うく死にかけた小町の気持ちなど知らないとばかりに、通信機の向こうでにとりが怒鳴り返してきた。
そのおかげというわけではないが、小町の意識がふたたび現実に引き戻され、頭から逃げ出しかけていた血の気が巡り、硬直化していた思考も明瞭になっていく。
(大丈夫だ、まだ生きてる。にとりの声がうるさいと思える間は戦える!)
気分が落ち着いた今は、仲間の声さえも生きている実感と思えてくるから不思議だ。
手の震えがないことをたしかめた上で、小町はターニング・ボルトを引いた。滑らかな動きに合わせて空薬莢が飛び、次弾が装填された。真鍮製の薬莢が地面を叩く澄んだ音が聴覚に沁み込んでくる。また少し鼓動が安定した。
「可能性だっていいだろ? あやうく首なし騎士になるところだったじゃないか。気が利かないねぇ」
どこまで本気かわからない苦情が小町から発せられた。ようやくいつもの調子が戻ってきた。
『あれは首を抱えているだけで、べつに頭部が消し飛んでいるわけではないのでは?』
妖夢からのツッコミが入った。言われてみればそのとおりである。
仮にデュラハンを超越した何かになったとしても身振り手振り以外の意思表示手段を奪われては――
唐突に小町は正気に返る。どうして自分の頭が吹き飛ぶことが前提になっているのか。
そうなるのは自分ではなく隠れている連中だ。
そもそも自分にこんな極限の緊張を強いて来る敵を許すべきか。いいや、たとえ地獄の閻魔が許しても死神が許さない。
『小町が倒した相手の観測手は見つけました! すぐに仕留めてきま――っとぉ!?』
遠くで鋭い銃声が響き渡った。位置は少し変わっているようだが、おそらく同じライフルのものだ。無力化された相棒の銃を拾って反撃してきたのだろう。たいした仲間意識だと感心する。
『今の会話ちゃんと聞いてたか!? 他にも隠れてる狙撃手がいるんだよ!』
勘弁してくれとにとりが叫んだ。
声がわずかに乱れている。今頃光学迷彩を身に纏いながら、必死に建物と建物の間を通り抜けたり迂回したりしているのだろう。
普通は建物の間を抜けていくだけで緊張もあって方向感覚が狂わされるのだが、にとりは空間把握力に優れているのか、上手く敵を追尾しながら移動しているようだ。
「いや、ナイス囮だよ妖夢」
しっかり伝えるのが恥ずかしかった小町は、通信機のマイクが拾わないようそっとつぶやいた。
他愛のない会話だったが、こちらの興奮まで落ち着けてくれた。たったひとりで対狙撃手戦をやれと言われたらどうなっていたことか。やはり自分に狙撃の才能はないのかもしれない。
「でも、あたいにだって敵を撃つことはできる」
はたして自分はこんなにも好戦的な性格だっただろうか?
そう考えつつも小町は、妖夢が炙り出してくれた敵を仕留めるべく、感覚で「ここだ」と見当をつけた場所へとモシン・ナガンを伏せ撃ちの姿勢で構える。
銃床を頬につけると木の感触が伝わってきた。次いで覗き込んだ照準器越しに狙うべき建物が薄闇の中に浮かび上がってくる。左右に軽く銃口を舐めるように動かしてみると、それに合わせて視界がゆっくりと流れていく。
(いた……!)
闇の中でもわかる人型の頭部。それがライフルを構え、動き回る妖夢を追尾している。
そう認識した瞬間、心拍が跳ね全身から汗が噴き出してきた。
「――なるほどね、わかってきたよ。狙撃手同士で戦うってのはこういう感覚か……!」
いかに条件反射の興奮を抑え込むか、それが肝なのだと小町は自然のうちに理解した。
先ほどまでは、朝方にとりからの叩きこまれた知識の受け売りでわかったような気になっていただけだ。
そう、狙撃はひとつの精緻な作業――“芸術”だった。冷静に相手までの距離を掴まなければならない。先ほどは当てたが、あれが偶然であってはいけないのだ。
たとえば呼吸ひとつとってもそうだ。生きるために必要なそれは、銃口が上下に揺れる忌むべき存在となり、それが数百メートル先では大きな誤差となる。
自分の身体の仕組みさえ制御下に置いてもまだ足りない。次に支配下に置くのは意識だ。すべての感情を封じ込めて無の境地へと至り、流れるようなリズムで引き金を引く――いや、絞らなければ銃が揺れ、弾丸の軌道もまた大きく乱れてしまう。
慎重さを欠き、曖昧な点を残したままではライフルは狙撃を失敗させる。
無意識のうちに、訓練時に設定していた距離に着いていたようだ。
用心金に伸ばした人差し指をかけた小町は大きく息を吐き出し、そこで呼吸を止めた。
ほんの一瞬ではなく、数秒に渡る途絶によって自身とライフルを安定させる。それでも稼げるのはほんの数秒だ。これを過ぎれば今度は身体が呼吸を繰り返している時よりも大きく震え出してくる。時間をかければ素人の自分がより不利になっていくのだ。
小町は照準器の十字線を、飛び回る妖夢を捕捉しようとしている観測手の横顔にそっと合わせた。人差し指はすでに引き金にかけられている。
敵が動きを止めた瞬間、十字線の中心と重なった。
直後だった。鋭い衝撃が肩へと突き刺さるように押し寄せ、照準器の向こうの世界が大きく揺れた。
まさに無意識の出来事だった。それでも最高の瞬間だと追随する意識で確信していた。
その証拠に――元の位置に戻ったライフル、そして照準器の向こう側で、弾丸は敵の頭部を厳密には上顎から上を容赦なく吹き飛ばしていた。
「命中!」
自ら上げた歓喜の声。直後に唸りを上げた銃弾が付近で爆ぜる。
しかし、新手の狙撃手が潜んでいると見越していた小町はすでに空間を跳躍していた。
「あぶないあぶない。撃った直後が一番危ないんだよねぇ。あたいだってそこを狙うだろうよ」
移った建物の物陰で小町は次弾を装填しながら小さく息を吐き出した。
『なんだかんだでコツを掴んでるじゃん。その調子その調子。次いってみよー』
「あんたねぇ、褒め方下手くそか」
通信機の向こうからにとりの緊張感のない声が届き、小町は抗議の声を上げた。こちらが鉄火場に立っているというのに気楽なものだ。
『驚いてるんだよ。ぶっちゃけ、めんどくさくなって飛び回りながら撃ち合いを始めるもんだとばかり思ってた』
「この速度と威力の弾、『弾幕ごっこ』では飛んでこないしね。当たれば命がないのはわかってるさ」
普段の異変なら多少の無茶はしていたかもしれない。
だが、冗談抜きに一発の弾丸がすべてを決する戦いの中でそんな馬鹿な真似はできなかった。
どうにも変だ。さっきからずっと自分の身体ではないような錯覚を覚えている。
そもそも、こんなにあくせくと働く――もとい戦うのはご免蒙りたいはずなのに、肌のひりつくような感覚は不思議と怠惰な死神の魂を震わせてくる。自分は魂を運ぶのが仕事で、魂にすることは業務範囲外なのだが――。
『相手の土俵に立つのは悪手なんだけどな。正攻法での戦い方がやっぱ確実だよ』
ライフルの重みが何かを訴えて来る中、小町はにとりの言葉で現実に立ち返る。
「そうは言うけど、我らが斬り込み隊長は全力で突っ込んでいってるけど?」
『え?』
にとりが素っ頓狂な声を上げた。
『おりゃあああ!!! っぶな!!』
新たな銃声が木霊し、次いで金属音同士がぶつかるような――それにしてはもっと軽い音が鳴り響く。
妖夢が狙撃の銃弾を躱しつつ、残った観測手たちを仕留めにいったのだ。
『やった! さっき小町が倒したのを含めて2体仕留めました!』
『ちょっと無茶するなよ! 今あんたに死なれたら困るんだから!』
上手くいったからと結果オーライでは済ませられない。まだ敵はどれだけ潜んでいるかわからないのだから。
「そうか、あれが陽動の正攻法かい」
『違うわ! 普通はもっと安全に騙すんだよ! 参考にならないけど!』
にとりは全力で否定した。せっかくそれなりに上手くいっているのだから無茶をされては困るのだ。
「あーたしかに。妖夢にそんな器用なことはできなさそうだな」
『失礼な!』
続いて妖夢が怒りの声を上げるが、まるで説得力がなかった。
正直なところ、一連の騒動で剣の腕以外に信用があるとは言えない。敵と見れば突撃を繰り返すのだから無理もない話だった。
『まぁ妖夢はあえて危険に身を投じてる時が一番集中力を発揮して、一番勘が冴えてるから間違いじゃないのかもしれないけど』
直接「あれをやるな、これをやるな」と言っても、残念ながら素直に聞いてくれる性格ではないのでなるべく迂遠な言い回しでけむに巻く。けして妖夢が単純さではそちらの方が“効く”からではない。
『えっそうですか?』
満更でもなさそうに照れた様子の妖夢。気持ち鼻息が荒い。馬鹿正直過ぎる反応だった。そのうちチョロいと思われて詐欺に遭ったりしないだろうかと心配になってくる。
「あっさり乗せられんなよ。んでにとりは何してんのさ」
『妖夢の動きを見守っ――どう攻めるべきかチェックしてる』
あわよくば他人任せで片付かないか様子を窺っていたらしい。今日に限っては自分よりもよっぽどサボっているんじゃないかと思えてくる。
「いや働けよ」
『言われんでも働いとるわ。奴らが撃ちたくない方向、わたしらに行かせたくない方向を割り出そうとしてんだよ』
巡回している歩兵を巧妙に回避しながら、にとりは周囲の把握に努めていた。
状況的に気休めにしかならないが、敵が持っているライフルがボルトアクションで助かった。もしも自分が持つM1ガーランドのような半自動式であったなら、手数で押し切られていた可能性が高い。
もっとも狙撃手から逃れられても、歩兵に見つかったら弾丸の雨を浴びせられることにかわりはないのだが。
「なるほど? そいつはわかったのかい?」
こまめに狙撃位置を変え、銃口を構える場所を考慮しながら、小町は新たな敵の奇襲に備える。敵の中枢に近付いているのだ。相手も弱兵ばかりではなくなっている。
『ホームから侵入した時のことを覚えてる? あいつら2時上空からまず迎え撃ってきたろ』
「2時上空……?」
小町から困惑の声が上がった。クロックポジションが理解できなかったらしい。
『あー……正面を向いて12時、そこから30度ずつ角度を刻むことを1時2時って言うんだ。後ろは6時の方向。わかった?』
「把握した」
とりあえず今だけは覚えておこう。小町は本能に深く刻み込んだ。記憶でないところが彼女らしい。
『要はわたしらをホームに押しとどめておきたかった。そしてさっき動き始めた瞬間の妖夢を撃ったあと、最初の狙撃手の場所に辿り着いた妖夢を撃った』
「つまり――そこまでの間に何かある、と」
『先には行かせたくなかったけど、目的と違う場所に向かったから一瞬見送ったんじゃないかな。とすると……』
「その左手の建物が怪しいな」
言葉を受け継いだ小町は視線を動かした。確信があるわけではない。死神の直感だ。しかし、それで十分だった。
『ああ、結構頑丈で窓も少ないし、多分ここが奴らの司令部だ』
「すぐに突入するかい?」
訊ねつつも小町は不安を覚えていた。すぐにわかったということは、裏返せば危険を察知したとも言える。
神経を酷使する狙撃を完遂したせいかどうにも過敏になっているらしい。さっきからイヤな予感が止まらない。
『外の敵、見つけられる分だけでも全部倒しておこう。建物に入って襲われたら隘路だ。退路確保』
『了解』