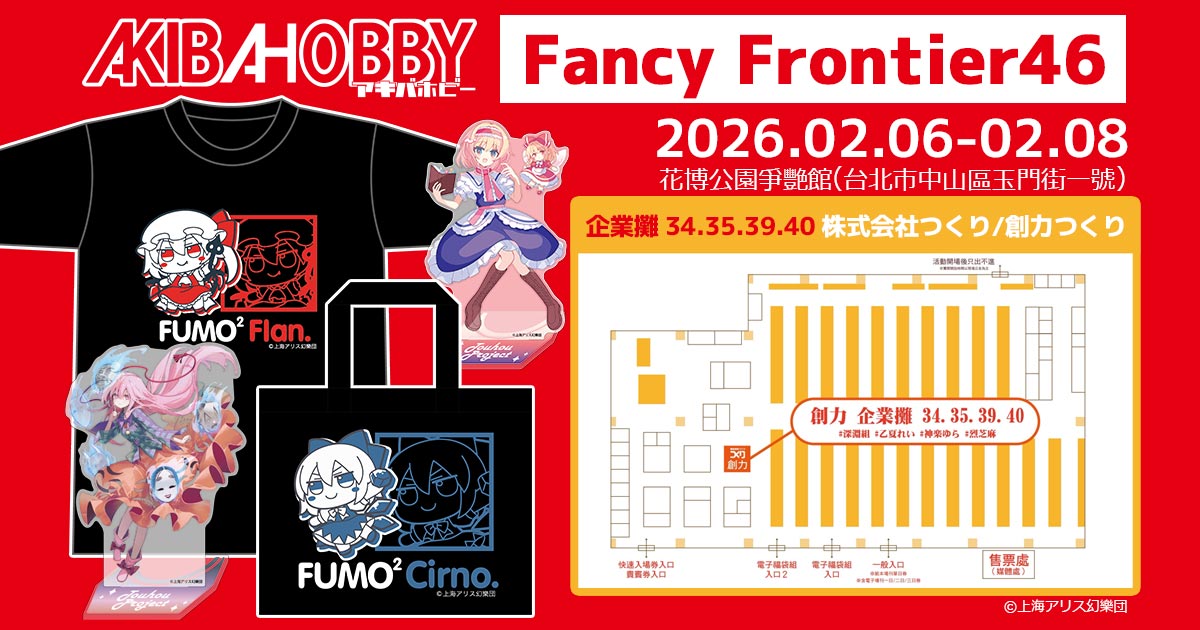【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第40回 霧中】
「よし! ご丁寧なことに初弾はすでに装填済みだったよ。あとは照準さえ合わせたらいつでも撃てるね!」
カール自走臼砲の照準を調整しようと格闘していたにとりが、次の砲弾の準備をしていた妖夢たちに向けて言葉を発した。
彼女の背後では、一体構造のため砲尾と合わせて重量約30tに達する、口径540mmにして112条のライフリングを刻まれた巨大な砲身が天を仰ぎ、咆吼する瞬間を今か今かと待ち構えている。
それはあたかも、これから巻き起こる死闘の気配を全身で感じ取っているかのようだった。
「結構なことだわ。込められている弾が紅魔館に向かって飛ばなかったのも含めてね」
作業を監督していたパチュリーが、にとりを見上げながら静かに応じた。その際、左手を額に持っていったのは、いつの間にか傾き始めた陽光に目が眩んだからだろう。
お世辞にも肉体派と言えない彼女に力仕事を手伝わせても無駄に体力を消耗するだけなので、持ち前の魔法知識で照準の計算などを担当してもらっていた。
「ははは、それには同意するしかないね」
カールの本体に取りつけられたハンドルを慣れた手つきで回し、細かな最終調整を行いながらにとりは小さく笑う。
「でも、撃てば最後、これがわたしたちの手に落ちたことが亡霊たちにバレてしまうでしょうけど、そっちは大丈夫なの?」
「どうだろうね。連中もバカじゃないだろうし……」
「では一撃必殺を狙うと? そんなに都合よくいくかしら」
「初弾命中で撃沈なんて上手くいくわきゃない、現実は空想とは違うんだ」
さほど面白くもなさそうに答えるにとり。彼女の認識によれば、このカール自走臼砲の命中精度はそれほど高くないらしい。
実際、外の世界で使われていた時も、砲の持つ宿命というべきか、初弾で得られた情報から次の着弾地点を修正していき命中弾を導き出すのだ。
それは幻想郷で魔法の補助を得られても、ここが地球の延長線上である限り変わらない物理法則に支配されたものである。さらに言えば“本来必要な16人の専門家”がいないこの場合は、より困難な戦いとなることが予想されていた。
もちろん、事実であっても不安を煽る言葉をにとりは口にしない。それでは士気が保てないからだ。
「あなた、もう少し頼りにできる言葉は口にできないの?」
黙って作業を続けるにとりの内心を見透かしたように、パチュリーがどこか咎めるような声色で問いかけた。
「希望に縋るのは大事だけど、それで死んじまったら元も子もないからねぇ」
要するに、やるしかないのだった。
とはいえ、このKarl–Gerät 041は、初期型であるKarl-Gerät 040の600mmよりも口径を小さくしつつ同時に長砲身化させることで、約2.2tの重ベトン弾よりも砲弾重量を半分近くにまで低減させながら初速を上げ、初期型比で倍以上の長射程化と威力を確保している。
これほどの大きな改良を施されながらも、やはり根本的な問題である超重量を覆すだけの革新を起こせはしなかったようだ。
それでも実戦に投入されたのは、おそらく戦時という非常事態が遊ばせておくことを許さなかったのかもしれない。
「……やはりエンジニアといったところね、何も考えていないわけじゃないようで安心したわ。それで、このあとの展開はどう予想しているの?」
「あまり嬉しくない褒め方だなぁ。あんたも予想しているだろうけど、撃ったと同時に敵も来るだろうから、コイツを守る防衛線が始まるよ。スピード勝負の陣取りゲームみたいなもんさ」
「湖からの攻撃と陸からの襲撃、完全に挟撃じゃない。あなたの見立てで勝ち目はあるの?」
「みんなの頑張り次第だけど、コイツを使えるだけでもわたしらはツいてるんじゃないかな」
たまたまこの場所に配置されていた長距離砲を、無傷で鹵獲できた時点で幸運以外の何物でもない。もしこうした兵器が手に入らなければ、威力に乏しい戦車砲で挑むか、地の利もない場所に乗り込んで白兵戦を挑むしかなかった。
案外、妖夢は喜ぶかもしれないが、それでは勝負そのものに勝つことができなくなる。
「それに、ネックの装填役だって“とっておきのヤツ”がいたから解消できたようなもんだし、もうちょっと前向きにいくべきだと思うけどね」
にとりが視線を向けると萃香が片手で砲弾を持ち上げながら酒を飲んでいた。
「あれを見て前向きになれるなんて大したものだと思うわ」
応じたパチュリーの顔もわずかながらではあるが引き攣っていた。
萃香が間違って砲弾を落としでもした日には戦う前からここにいる全員が文字通りバラバラに吹き飛んでしまうのだが、おそろしいことに当の本人の危機感がまるでない。周りからすれば火薬庫で花火大会でもしているような気分だった。
しかし、この飲んだくれ妖怪がいなければ、次弾装填にどれほど時間がかかるかわかったものではない。言いたいことは山のようにあったが、なるべく機嫌を損ねないよう黙って見過ごすしかなかった。
「本当に鬼って存在はタチが悪いわね……」
萃香以外の総意を代弁するようにパチュリーは溜め息を吐いた。
諸般の問題から目を背ければ、鬼という大妖怪が持つ規格外の怪力によって、カールはカタログスペック以上の発射速度を実現できそうだ。
だが、結局のところ当たらなければなにも意味がない。もたもたしていれば反撃の砲弾でカールごと地面を耕されておしまいだ。この自走臼砲には装甲も施されているが、ないよりマシ程度のものでしかない。
世界最強と謳われた超大型ではないにしても、戦艦の名を冠する艇とは本来それほどまでの力と装甲を持つ破壊の化身である。
もしも大和級かアイオワ級でも湖に浮かんでいた日には、今頃どうなっていたかわからない。冗談抜きに戦車ごと合挽き肉よりひどい存在になり果てていたかもしれないのだ。
「それで、照準の方はどうなっているのかしら?」
非常識代表の振る舞いはどうにもならないと諦めたパチュリーが、にとりへ進捗を問いかけた。
「あんたがやってくれた魔法の演算と、小町の偵察で得た測距値と敵艦の諸元からもうおおよそは合わせてあるよ。これ以上やることなんて言ったら……あとは祈るくらいだろうね」
「そう。だったら何に祈ろうかしら」
結局は出たとこ勝負らしい。もはや溜め息も出なかった。
「戦争の神にでも祈っとけばいいんじゃない? 主役は魔法じゃなくて兵器だし」
「そんな適当な腹の内じゃあ、御利益は薄そうね。リアリストなわたしたちより、兵器を操る亡霊たちの方が、ずっと信仰心があるんじゃないかしら」
「言っといてなんだけど、わたしは神より数字を信じるからな。まぁ天の運、時の運、それから勝負の運に賭けるしかないな」
「意外ね。あなた、博徒だったかしら?」
「賭け事はやらないけど、これでもゲンは担ぐタチでね。それに…………思い出した、山の上の神様も元とはいえ軍神であったって聞いたことがある」
「…………あの神さまを信仰するかって言われたら確かに悩むわ」
「だろ?」
小さく鼻を鳴らしたにとりが発射レバーにくくりつけた紐へと手を持ち、地面へと降りてくる。
「さぁ、離れた離れた! つまらない理由で死にたくなかったらね!」
さすがに540mmにも及ぶ大口径砲の発射炎と衝撃を至近距離から生身で受け止められはしない。戦車砲ですら歩兵が近寄らないよう危険距離が周知されているのだ。単に妖怪だからとか半分死んでいるから平気となるわけもない。
「いくよ! 耳を塞いで口を開けといて! 見ようとするのもダメだからね!」
その場の全員が耳を塞いで目を逸らしたのを見届けた上で、耳栓を差したにとりが大声で叫ぶと同時に全力で紐を引く。
「発射ァッ!!」
瞬間―――世界そのものが震撼した。
天に向けて突き抜けるような轟音が響き渡り、塞いだ耳に意味があったのかと叫びたくなるような空気の振動が身体を大きく揺さぶる。
極大の地震でも起きたかと錯覚させる――――いや、瞬間的な衝撃だけで語るなら地震すら超えるほどのものだった。
発砲と同時に、激烈な反動を吸収するためFlaK36同様に駐退復座機が作動し、瞬時に砲身を元の位置へと戻す。その際、砲口から溢れ出た砲煙が辺りを包み込み、妖夢たちの視界が完全に塞がれる。
とはいえ、そんな諸々の事象は些事に過ぎない。砲弾は既に放たれ、湖に陣取る戦艦マラートへ向けて超高速で飛翔していたからだ。
「次弾装填準備!!」
耳栓越しでも殺しきれない衝撃に脳を揺さぶられ、くらくらしながらも、にとりはすぐさま砲身へと駆け寄り、ハンドルを全力で回しながら叫ぶ。
数えること10秒前後、遠く離れた湖上から水の爆ぜる音が耳に届く。霧の中にうっすらと立ち上がった水柱は、カール自走臼砲がどれだけの威力を持っているか、妖夢たちにも肌で感じられるものだった。
だが、それだけだ。
「小町は着弾観測! 急いで!」
「あいよ!」
にとりが続けて叫び、我に返った小町が空に向かって空間を跳躍する。
唯一兵器を使った戦いの予備知識を持つにとりは、未知への驚愕に支配されることなく動き続ける。
いくら高威力の砲を有していようが、肝心の敵に命中しなければ何も意味がないし、そのために次弾の照準に必要な諸元を得なくてはならない。
「砲弾を送り込んで!」
わずかながらではあるが、未だ白煙を吐き出している砲身が下げられると、大急ぎで懸架に載せられた次の弾が装填準備に入る。
尾栓が解放され、底部に残った薬莢を排出する傍ら、装填用のハンドルを全力で回すと、砲弾が滑るように、それでいて巨大なためゆっくりと砲身内部へと押し込まれていく。
「じゅ、重労働……!」
全体重をかけながら装填ハンドルを回して妖夢が呻いた。
半分霊体であるため生身ほど踏ん張れないのがこれほど恨めしいと思ったことはない。
「大変なのはわかってるけど1秒を争うんだよ! 向こうは機械の力で易々と弾込めができるし、そもそも――――」
装填作業を手伝うにとりの言葉を掻き消すように、付近の森が連続して爆発した。
「同時に複数撃てるんだよ……」
答えるにとりの頬を“別の汗”が伝っていた。
遠くから鳴り響く敵戦艦の砲撃音と混ざり合うように、妖夢たちがいる場所周辺の大気そのものが振動しているようだった。あるいは、それもこの砲撃によって感覚がおかしくなってしまっているのかもしれない。
「向こうの着弾観測が気になるところだね。結界なら滅多矢鱈に撃っても当たりはするだろうけど……」
「森の奥から気配! 複数です!」
「このタイミングで来るか!」
にとりは鋭く舌打ちする。
おそらく、何らかの手段によって敵が攻めてきていることを察知したのだろう。
実際、そうでもなければ紅魔館を包囲している亡霊たちが、もしもの時にカールを発射するよう指示を出せなくなるからだ。
しかし、それにしては何かラグがあるように感じられた。
「妖夢、悪いけど何がなんでも守り抜いてもらうよ! こいつが使えなくなったら湖のあいつを倒す手段がなくなっちまう!」
湧き上がった疑念を今は振り払い、にとりは妖夢に指示を出す。
「わかりました! 任せてください!」
叫ぶように応えて、敵の来る方向へと駆け出す妖夢。すでにその手は楼観剣の鞘を握り締めていた。