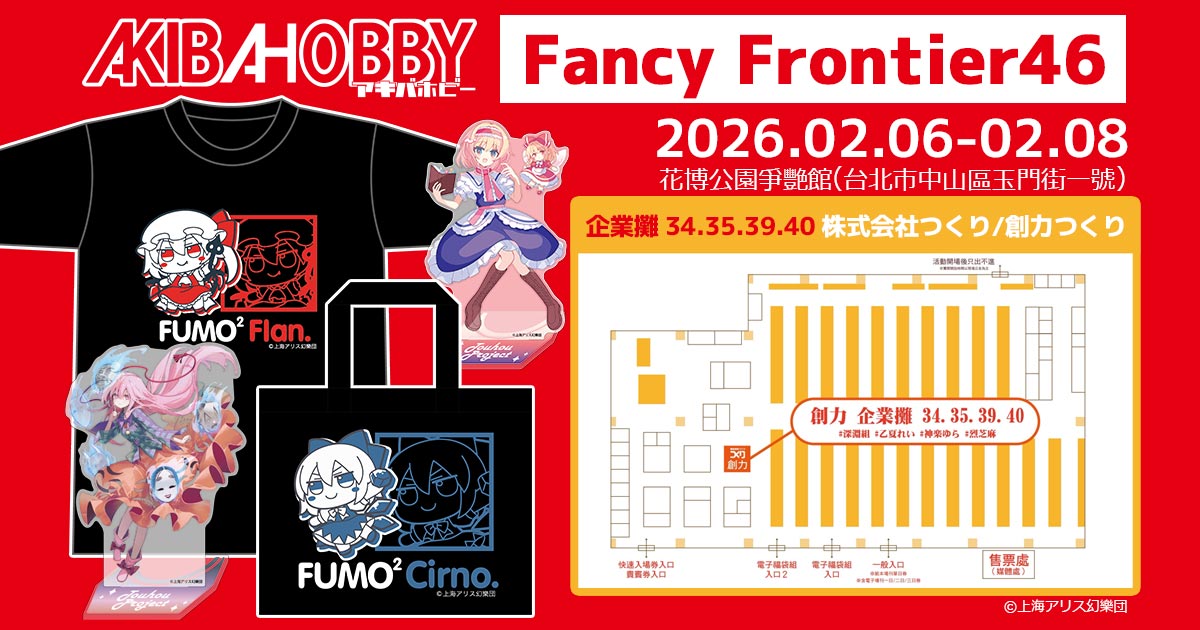【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第24回 鉄拳】
操縦席の風防に突き刺さった白楼剣を引き抜いた妖夢はP-36Cの機体を蹴って飛び上がる。
その直後、制御を完全に喪失した銀の鷹は地上へと向かって墜落していった。
しばらくして漏れ出した燃料に引火したか、轟音と共に森の中から爆炎が噴き上がる。
「……生死を懸けて戦えども恨みはありません。彼岸で存分に空を飛びなさい」
手向けの言葉をつぶやいた妖夢は白楼剣を腰の鞘へと納め、次いで残る敵が舞う空へと視線を向ける。
――――あとふたつ。
図らずも援軍となった魔理沙とアリスが牽制……いや、彼女たちの動きを見るに、隙さえあれば落とそうとしているようにも見受けられる。
しかし、初めて対峙する自身よりも速度に優れた戦闘機を相手にするのは、魔法使いをもってしても至難の業らしい。
手負いの1機を仕留めた時と同じく、不意を打つわけでもなければ高速で飛び回る飛行機械を相手にするのは難しいのだろうか。
このまま上空の援護に向かうべきか悩んでいると、近くで木の枝がにわかに音を立てる。
「!」
「ちょっと待って! わたしだって!」
楼観剣を旋回させながら振り向くと、木々の間から顔を覗かせ両手を上げたにとりと小町の姿があった。
尚、寸前で止めたため白刃はにとりの首元から指数本分手前で静止しており、哀れな髪の毛が数本切り離されてはらりと宙を舞っていた。
さすがに今のはギリギリだ。危うくとんでもないことになりかねない。
「はぁ~、こわいこわい。ここまで来て味方に斬られるなんて事故は勘弁してほしいね」
血の気を失い青くなった顔でにとりは頬を伝う汗を拭い取る。
「だったら先に声をかけてくださいよ、危ないなぁ。今は戦ってる最中なんですから」
大きな溜め息を吐き出して妖夢は刀を引く。
「しかし、生身のまま戦闘機をやっちまうなんて。本当にどうかしちゃってるよ、あんた」
「まったくだね。これじゃいつまでも“辻斬り”なんて呼んじゃいられないかもね。いっそ“曲芸師”と呼んであげた方がいいんじゃないかい?」
鋼鉄の塊相手に命がけの鬼ごっこを演じて疲れたか、ふたりは呆れているのか褒めているのか判断しかねる言葉を口にする。
それぞれの顔に浮かぶ微妙な憔悴具合を見るに、冗談のひとつでも言わないとやってられないのかもしれない。
「なんですか、ふたりとも。やっとのことで戦果を挙げてきたのにずいぶんな物言いをしてくれますね……」
「じゃあ“亡霊斬り”とでも呼びゃいいのか」
「……あんまりカッコいいとは思えないけど、あたしゃ」
言いたい放題な言葉に不満げに小さく頬を膨らませる妖夢。
……いや、“亡霊斬り”とかちょっと格好いいかもしれない。妖夢の中に眠っていた思春期特有の病にも似たなにかが、密かに鎌首をもたげてくる。
「ほらほらぁ! 逃げてないでわたしの相手をしろよー!」
一方、上空では魔理沙がなにやら騒ぎながら元気に飛び回っていた。
拉致された上に付き合わされている被害者は、頭痛を堪えるようにしつつも加害者の援護をそつなくこなしている。
最終兵器関連の事情を知らないとはいえ、いくらなんでも暢気すぎやしないだろうか?
意図せずして揃った三人の呆れ交じりの視線が魔法使いの少女に向けられる。
P-36C自体が未知の存在であっても、放たれる高密度の機銃掃射が厄介であることは本能的にわかるのか、聞こえてくる言葉とは裏腹に魔理沙の回避には相手を侮った様子はない。
相手の描く機動と射線を上手に読んで攻撃を躱していっているが、どうにも攻めあぐねている感もある。
高速度領域の相手に慣れていないと言えばそれまでだが、うっかりやらかすこともある魔理沙を知っているだけに、見ていて少々不安になってくる。
「……まったく、騒がしいヤツが増えたなぁ」
「でも、援軍のおかげで時間が稼げたのは事実です。今のうちに戦車を叩きましょう」
鬱陶しげに視線を向けるにとりに対し、妖夢は魔理沙を擁護する。
「そうだね。……よし、早いところ片をつけよう。小町、妖夢。上はあいつらに任せといて、もう1回だけ戦車を引き付けてくれないか?」
「あいよ!」
「ええ、それくらいなら問題ありません。むしろ任せておいてください!」
戦闘機同様に戦車まで斬れと言われたらどうしようかと思っていた妖夢は内心で安堵の溜め息を漏らす。
「はっはー! そんな動きでわたしを倒そうってんじゃ全然ダメだぜぇ! ……って、うわわっ!?」
亡霊の方も、ある程度本気でかからなければ危ないと判断したか、旋回を含めて動きがさっきまでよりも攻撃的になった。
最初は難なく回避していた魔理沙にも次第に焦りが見られはじめる。
「ちょっと、妖夢! そっちが片付いたんならボケっとしてないで援護に来てほしいんだぜー!」
余裕がなくなってきたのか、箒に跨って弾を避けながら大声で助けを呼ぶ魔理沙。
「ああ言っているけど、助けに行かなくていいのかい?」
「あー……。でも、先に戦車を片付けた方がいいじゃないですか?」
「そうだねぇ。できることなら戦車を潰してそのまま山へ向かいたいくらいだけど、そうもいかなさそうなんだよね……」
魔理沙とアリスが飛行機械を引き付けていてくれるならそれも可能だろう。虎の子と思われる航空機がそういくつも残っているとは思えない。
――――いや、これはただの願望で、正確な情報に基づいたものではない。
もしも敵の航空戦力がまだ残されていた場合は、その流れすら崩れかねない。万難を排するなら、やはりこの場の敵を順に片付け、あの空を向いて鎮座しているFlaK 36を確保する必要がある。
「急いては事を仕損じると言います。焦る気持ちもありますが確実にいきましょう」
「うん、あたいもにとりの決定を支持するよ。すくなくとも連中の武器やらに詳しいのはあんただしね」
「おーい、妖夢ってばー!?」
「すみません魔理沙! ちょっと今は無理でーす! というか無敵のマスタースパークでなんとかしてくださいよー!」
割りと容赦なく魔理沙からの支援要請を却下する妖夢。
「えー!? ミニ八卦炉の魔力の充填がまだなんだよぅ!」
なんとも締まらない話である。開幕一番に奥の手をぶっ放したせいで今の窮地を招いているなど、まるで笑えない。
とはいえいつまでも話しているわけにもいかない。
ひとまず上は魔理沙とアリスに持ちこたえていてもらうとして、まずは戦車を潰す。
「じゃあ動きが止まって、五つ数えたら真横に飛んで避けるんだ。そこであいつは撃ってくる。今度はスピード勝負でいくよ!」
本当にそんな感じでいいのだろうか?
妖夢は不安に思うも、現状この幻想郷において兵器関係の知識でにとりの右に出る者はいないので素直に従っておく。
もっとも、妖夢の疑問はあながち間違いとも呼べない。
最新鋭の主力戦車であれば機種によっては走行間射撃からのコンピューター制御で当ててきたりもするのだが、幸いそのような最新のものまで幻想郷に流れてきてはおらず、にとりも知らないことだ。すくなくとも今はそれで問題はなかった。
「さぁ、そろそろ決着をつけましょうか」
獲物を探してさまよっていたT-34の前方に妖夢が立ち、挑発するかのように楼観剣を旋回させる。
獲物を発見した亡霊車長が内部へと入り、T-34が動きを止める。射撃姿勢に移行するためだ。
彼我の距離は百メートルほど。ひとたび砲弾が唸れば刹那の間に肉体など完全に消滅させられる。
装甲などない生身の相手だ。徹甲弾など使う必要はない。命中させずとも加害半径内に榴弾を撃ち込んでやればそれで終わりだ。
鉄の塊から放射される殺意を受けた妖夢はわずかに腰を落とす。一瞬で最大のパフォーマンスを発揮するために。
5――4――3――
胸の中で鼓動ばかりが速くなる中、妖夢は冷静に数を数えていく。
T-34の砲塔もまた妖夢という標的を確実に葬り去るべく狙いをつける。
2――1――
不意に心臓のリズムは驚くほど落ち着き、身体を支配していた緊張は霧散。その時にはすでに妖夢は地面を蹴っていた。
次の動作など考えない全力の跳躍。そして付近の木を蹴って再度上空へ飛び上がる。
ほぼ同時に、先ほどまで妖夢がいた場所が轟音と共に吹き飛び、衝撃で大量の土砂が舞い上がっていた。
少しでも遅れていたら今頃半分の肉体は地面と共に耕されていたに違いない。
「避けられた! 次は――――」
空を駆ける妖夢の視線の先で、次弾装填までの時間がもどかしいとばかりに車長が天蓋を開けて顔を出す。
しかし、その視線は妖夢に向けられてはいなかった。
「さすがに読まれていますか!」
ここまで生き残っている亡霊もバカではなかった。あえて姿を晒した妖夢が陽動だとわかった上で接近する敵を探し出そうとしているのだ。
構えたPPSh-41から弾幕が放たれ、反対方向から近づいていた小町を釘付けにする。
その中で、亡霊は短機関銃を乱射しながら探していた。本命の一撃を繰り出しに来るであろう伏兵の姿を。
阻止すべく妖夢は全力で距離を詰めていた。
不意に旋回を続ける砲塔の動きが止まった。特大の悪寒を感じて大きく軌道を変化させると再度の砲撃。砲弾がとんでもなく速度で付近を通過していく。
心臓が縮み上がりそうになるが、今ここで止まるわけにはいかない。
(あれは外れた! もう脅威じゃない!)
背後で響き渡る爆音にも妖夢はけして速度を緩めない。
この時点で、三人の動きは亡霊の対処能力を完全に上回っていた。上空からの襲撃がほぼ心配なくなっていたのも大きい。
「わたしはここだぞっ!」
叫びと共に発砲を続ける亡霊を急襲。対処の遅れた車長の首を、翻った楼観剣が斬り飛ばしていた。
「今です、にとり!」
渾身の叫びを上げながら、妖夢は刀を振り終えた姿勢のままT-34の後方へと抜けていく。
「合点承知!」
ふたりの陽動によってにとりは絶好の発射位置に辿り着く。すでに肩に担がれたパンツァーファウスト150の安全装置は解除されている。
「地獄に戻りな、ベイベー!」
どこで覚えてきたのかあやしいセリフと共に、引き起こした照準器の中へ捉えた陸の王者を狙って発射ボタンを押し込む。
雷鳴にも似た発射音と、派手な発射炎を周囲に振り撒いて、鉄の拳が高速で飛翔。
まさかの直上から発射された弾頭は、車長を失い無防備になっていたT-34のエンジン部へとまっすぐに突き刺さった。
「命中!」
成形炸薬弾頭が秘められし効果を発揮し、モンロー/ノイマン効果によって高速で叩きつけられる金属の奔流が戦車の装甲を突き破り内部を侵食していく。
内燃機関の檻を貫き、内部の燃料へと引火するまではほぼ一瞬の出来事だった。あるいは爆発の凄まじさから内部の弾薬にまで引火したのかもしれない。
重厚そのものにしか見えなかった砲塔が完全に吹き飛び、見るも無惨な姿を晒して鋼の巨獣は動きを止めた。
爆炎を上げるT-34の残骸を背にしてにとりは大空へと向かって拳を突き上げる。
「地上は片付いた! いよいよこっちが反撃する番だよ、亡霊ども!」