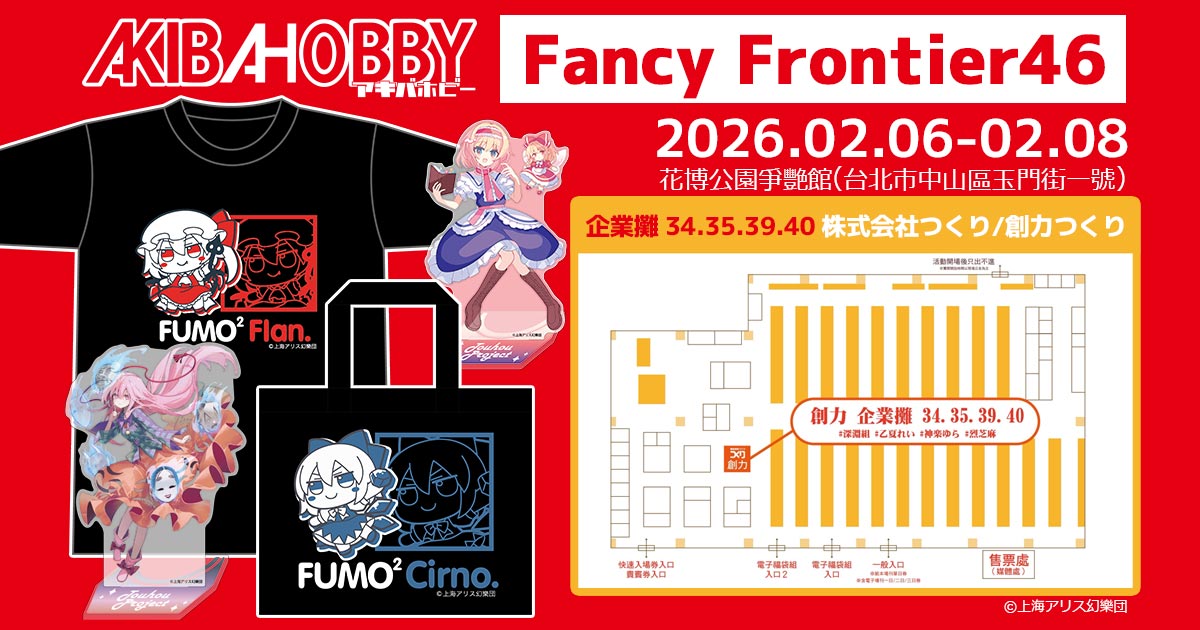【連載】妖世刃弔華
妖世刃弔華【第23回 乱戦】
「ふぅ……」
楼観剣を正眼に戻した妖夢の口から無意識のうちに大きな溜め息が漏れ出る。それにやや遅れ、P-36Cがかき乱した空気の流れが風となり彼女の持つ美しい銀色の髪をかき乱していった。
心臓の鼓動がいつになく激しい。
どだい無理だと諦めそうになっていた敵へ、たとえ正道ではないやり方であってもついに一太刀を浴びせることができた達成感によるものだった。
手の中に残る感覚――――またひとつ、今までにないものを斬れた歓喜に妖夢の口唇が知らぬ間に小さく歪む。未知の存在を斬ってのけることで、未熟である自分自身の剣が新たな高みに上がれたような気がするのだ。
幼い頃に「真実は斬って知る」と教えられたのは、今はどこかへ姿を消してしまった祖父の残した数少ない言葉のひとつであったが、今ならどういう意図でそれを口にしたかすこしだけ理解できるような気がする。
「うーん、これは鉄を斬れたと誇っていいものなんですかねぇ……」
重ね続けた研鑽の果てに雨を斬れるとか空気を斬れるとか、はたまた時を斬れるなんて聞いたこともあるが、どちらかいえば今の妖夢が斬っているのは亡霊ばかりだ。
それでも、高速で空を切り裂く弾丸を両断したり、今のように迫りくる鋼鉄の鷹に一太刀を浴びせたりと、己の剣境をわずかながらでも高めることができた喜びが胸中へ静かに湧き上がってくる。
だが、それに浸るのは後にしておかねばならない。
なにしろまだP-36Cを仕留められてはおらず、相変わらずうるさい音を立てて飛び続けている。
気を引き締めて向けた視線の先では、先ほどの斬撃で与えた損傷によって不安定になった翼の均衡をどうにか保ち、自身に課せられた役目を全うすべく上空へ逃げようとする姿があった。
せっかく掴んだ好機だ。このまま逃がすわけにはいかない。
「ここで決めさせてもらう……!」
にとりのように細かい原理はわからなくとも、今相手にしている敵が機首で回転する羽の群れが生み出す諸々の力と、大きく張り出された翼によって飛んでいられることは妖夢にもなんとなく直感で理解できていた。
先ほどと同じようにもう片方の翼を潰すか、あるいは操っている亡霊の肉体そのものをどうにかするべきか――――。
何が正解であるか、刻一刻と変化していく戦いの中で悠長に判断している暇などない。
だが、そんなことはどうでもいい。細かいあれこれは斬ってから考えれば済む。
余計なことを気にするから剣筋も迷ってしまうのだ。
ある意味、単純明快な“辻斬り思考”へと切り替え、妖夢は戦いに決着をつけるべく楼観剣を真横へと旋回させて足元の木を強く蹴り、ふたたび大空へと舞い上がろうとする。
「……?」
その時、手負いのP-36Cへ追撃を仕掛けようとした妖夢の視界に、なぜか太陽の輝きが射し込んでくる。不意を打つような眩さによって瞳孔が収縮。
妙だ。今向いている位置からでは陽の光は妖夢の顔に当たらないはずなのに。
となれば――――
直後、猛烈な悪寒に襲われた妖夢は弾かれたように視線を真上に向ける。
雲ひとつないはずの蒼穹。真っ青なキャンバスを横切っていくいくつかの小さな存在に気付く。
「あれは……」
目を凝らすとその先にあったのは光る銀の翼。視線を向けている間に、その群れはこちらへと向きを変え急激に高度を下げてくる。
「ここで新手ですか……!? あとちょっとで倒せそうなところで……!」
新たな敵の数は3つ。どれもPー36Cだ。
なんとも上手くいってくれないものだと、妖夢は悔しげに歯を食いしばるが、それと同時に覆されてしまった状況を理解して顔面から血の気が引いていく。
もっとも、半分幽霊で色白な肌をしているせいか妖夢の見た目に大きな変化は見られない。ある意味では損な体質だった。
「ちょっとヤバいよ、妖夢。あれはさすがに想定外だ」
足元からにとりがひょこっと顔を出す。
遠くでは依然としてT-34のディーゼルエンジンと機銃が唸る音が聞こえる。おそらく、小町が懸命に陽動役を引き受けているのだろう。
もし敵に援軍が来るとすれば、にとりは戦車とばかり思っていたが現実にはそうならなかった。
おそらく、戦車1台を動かすために必要な人員が多いこともそうだが、戦力の大半を本拠地の防衛に充てているため侵入者の迎撃にそれらを割けないのだろう。
その点、航空機であれば圧倒的な速度を活かしてすぐに根拠地へ戻ることもできる。主な任務も空中哨戒になるだろうから何もなければ戦闘空域以外を回っていれば済むはずだ。
たかが亡霊などと今さら侮ってはいないが、なかなかに敵も考えている。
「わたしもあれが切り札だと思っていたんですけどね……。でも、今さら退くわけにもいきません。にとりは早く戦車を。……たぶん、長くは持ちません」
「あっ、ちょっと妖夢!」
覚悟を決めた妖夢はにとりの制止を無視して戦闘機の群れを相手取るべく虚空へ飛び出す。
対する戦闘機の群れも、多勢に無勢でありながら向かってくる敵を粉砕すべく総勢4機体制で降下を開始。
さすがに今回ばかりは厳しいかもしれない。たった1機にもあれだけ翻弄されてしまったのだ。4機を相手にして無事で済むとは到底思えない。
そう考えていたところで突如として遠くから光の群れが飛来。亡霊たちも一斉に回避行動に移るが、光条の直撃を受けたPー36Cの1機が空中で爆散した。片翼に損傷を負ったあの機体だった。
「えっ!?」
いきなりの事態に驚愕の叫びを漏らした妖夢の耳朶を新たな声が打つ。
「おいおい! なんだかおもしろそうなことをやってるじゃないか! わたしも仲間に入れてくれよ!」
聞き覚えのある声に視線を向けると、揺らめく森の“波” ――――揺らめく木々の葉を切り裂くように向かってくる影があった。
どこにでも転がっていそうな箒に乗って颯爽と現れたのは魔法使いの少女霧雨魔理沙と、彼女に抱え込まれる形で死んだような目をした“種族魔法使い”のアリス・マーガトロイドだった。
「あ、あなたたち……どうしてここへ?」
もっぱら問いかける先は魔理沙だ。彼女の腕の中でぐったりとしているアリスはどう見ても巻き込まれたようにしか見えない。こちらには聞くだけ無駄だろう。
「さっき香霖に会って聞いたのさ。妙な連中がなんか企んでいるってね」
抱えていたアリスを放り出してふふんと笑う魔理沙。
この様子では面白そうだから駆けつけて来ただけで、事件の全容まで聞いてはいないのだろう。たしかに賢明な判断だったと妖夢は思う。
幻想郷の結界を管理している霊夢ならまだしも、事あるごとに異変に顔を突っ込みたがる魔理沙にツァーリ・ボンバの存在を知らせるのはまずい。
下手に興味を持ってしまうと新たな異変の引き金になりそうな気がする。
いや、明確な前科があるわけでもないのだが、彼女をある種の起爆剤として他の何者かがしゃしゃり出てきそうなのだ。
「さぁ、くっちゃべっている時間はないんだろ? まずはあいつらを片付けちまわないとな!」
いきなり現れていきなり戦いを始めようとする魔理沙。いつもこんな調子で振り回されることも多いが、とにかく戦力の足りない今はありがたかった。
「魔理沙、わたしの剣では戦いにくいんです。陽動は引き受けますので連中が地上へ向かわないようにしてもらえますか!」
「任せておくんだぜ!」
短く答え、戦闘機にも負けず劣らずの速度で箒を操る魔理沙。
上空で旋回していたPー36Cも新たな敵の接近を察知して迎撃に向かってくる。全力で機銃が唸り、火線が魔理沙目掛けて集中するが、危なげない動きで見事に回避していく。
「ひゃー! こりゃ歯応えがあるってもんだぜ!」
(遊びじゃないんだけれどなぁ……)
後を追う妖夢は暢気なものだと内心で溜め息を吐き出すが、背後にある厄介事を知らないのだからこうなるのも仕方がない。
魔理沙から星を模した弾幕が張られ、P-36Cの放つ弾丸を時に飲み込み、あるいは機体そのものを狙って飛び交っていく。精緻さなど微塵も感じられないが、牽制の役割は十二分に果たしていた。
もっとも、魔理沙は自身の攻撃で敵を落とす気満々だったので不満は隠せない。
「ちょこまかと鬱陶しい連中だなぁ! ……あっと、まずい! 1機抜けた! 妖夢、ここはあんたに任せたぜ!」
「えっ!? ちょっとぉっ!?」
いきなり無茶を言ってくれる魔理沙の言葉に妖夢は抗議の声を上げるが、その時にはもう魔法使いの少女は他の敵を狙って加速していた。
「おたがい大変ね……。けど、ここを乗り切るにはやるしかないわよ」
傍らにいたアリスも諦めの溜め息を吐き、どこから取り出したのか多数の人形を操り大空の敵へと向かって放つ。
魔理沙の弾幕と、アリスの人形は、被弾にこそ追い込んではいないものの航空機たちから地上を攻める余力を奪っていた。
ならば、自分もひと仕事せねばならないだろう。
「言われなくてもわかっています。あーもー! わかっていますよぉ!」
叫びたい言葉はいくらでもある。だが、それらをすべて飲み込んで妖夢は地上目がけて全力で空を駆ける。
数が増えてもP-36Cの狙いは変わらず、地上に展開しているT-34を守ることにある。だから、隙を見ては動き回る邪魔者――—―にとりと小町を排除しようとする。
「わたしを無視して進もうとはいい度胸してますよね!」
自由落下を大きく上回る速度――――その役目を持つ戦闘機もかくやと言わんばかりの全力で急降下を仕掛け、地表への激突を阻止しようと減速する機体に向けて一気に突っ込む。
仕掛けるならこのタイミングしかなかった。
乱戦の中で一瞬の隙を衝くように、妖夢はついに射撃体勢の移行し速度を緩めたP-36Cへ追いつく。
「迂闊だな! 今度はわたしが後ろを殺ったぞ、亡霊……!」
機種を引き上げようとした瞬間を狙い、妖夢は自由落下にも似た速度で空飛ぶ翼の真上から垂直降下。

構えた楼観剣の切っ先がキャノピーを突き破って内部にいる亡霊の身体を貫き、噴き上がる血飛沫が内部を赤黒く染め上げる。
生身が相手であれば絶叫が響き渡りそうな状況下でも、刃をその身に受けた亡霊はなにも口にしない。ただ血塗れの顔で怨嗟の視線を妖夢に向けるだけだ。
だが、今の一撃は確実に空を舞う鷹の翼を捥ぎ取っており、制御を失った機体が明後日の方向へと飛び始める。
いかに亡霊が不死に近い特性を持っていても、生物としての理に支配される肉体を破壊されれば生物としての動きを果たすことはできなくなる。
「何度でも言いますが――――」
動きが鈍化した亡霊から楼観剣を引き抜いた妖夢は左手に白楼剣を握る。
「カ、エ……イ……」
不意に赤く染まった亡霊の口がなにか声を発しようとする。
「ここはあなたたちがいていい場所ではありません!」
しかし、妖夢が手を緩めることはない。
翻った白楼剣が手を伸ばそうとする亡霊の身体に突き込まれ、死して尚足掻き続ける肉体を完全に消滅させていった。