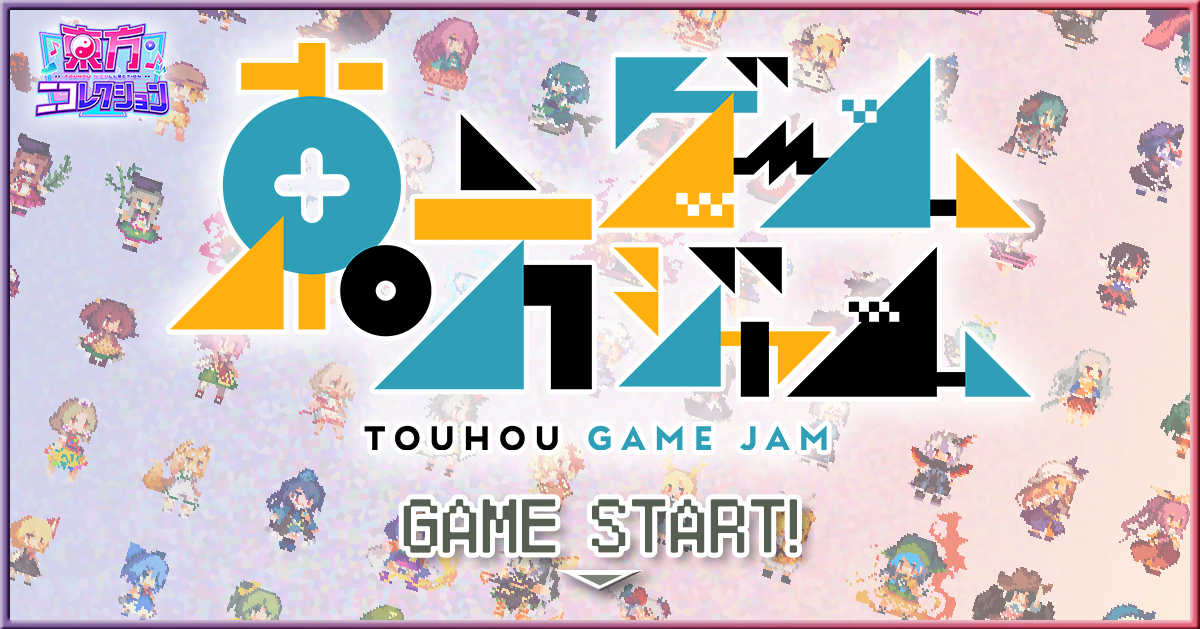「魔導書ばかり読んでないで、たまにはおとぎ話や物語に触れてみたらどうなの」
湖畔に佇む紅魔館。その広い屋敷の中にある、静寂が満ちた図書館の中で、パチュリー・ノーレッジはそう言った。
「……なんだって?」
その言葉をかけられた普通の魔法使い、霧雨魔理沙は眉をひそめながら聞き返す。まるで信じられないものを聞いたかのように。
「魔導書ばかり読んでないで」
「わかった、わかった。どうした? 熱でもあるんじゃないか? 魔女でも風邪をひくとは驚きだ。咲夜にジンジャーティーでも入れてもらって、休んだ方がいいぜ」
熱を測ろうと額に伸ばされた魔理沙の手を、パチュリーは鬱陶しそうに払いのける。
「私が言ったんじゃないわ。里の貸本屋の娘が言ったのよ」
「ああ、小鈴か」
本居小鈴。人間の里で貸本業を営んでいる家の娘である。魔理沙は彼女の顔を思い浮かべて「魔導書もいいですけど、たまには娯楽小説なんてものもいかがですかぁ?」とパチュリーに営業をかけている姿を想像した。言いそう。いや、絶対に言う。
ただしおそらく、その文句はパチュリーが言ったような棘があるものではなく、純粋に他のジャンルの本を勧めるような雰囲気だったのだろう。そんなイマジナリー小鈴とパチュリーの態度のズレに、思わず魔理沙は噴き出した。
「なに笑ってるの」
「いや、なんでも。しかしあいつも魔女に対してえらい暴言を吐いたもんだ。特にお前なんて、魔導書を読むことだけが生きがいだってのに」
「だけ、は余計よ。まあでも、自分でも思うところがないわけではないけれど」
パチュリーはそう言って椅子にかけると、丸テーブルに置いてあった本を魔理沙へと差し出す。
「で、彼女だけど。これを置いていったわ。世界の名作に触れるのもたしなみですよって」
「絶対そんな言い方してないぜ……」
魔理沙は本を受け取り、まじまじと見る。大きめの版型。目立つ赤い表紙。そして。
「タイトルは、”ジャックアンド、ザビーンスターク”……」
「日本人の魔理沙にもわかりやすいように教えてあげると、つまり『ジャックと豆の木』ね」
「わかるぜそれくらい。でも、これ、変だよな」
読んだことがあったかどうかは定かでないが、内容はなんとなく知っている。しかしそれは、あくまで児童書やおとぎ話というジャンルであって、大長編の冒険活劇ではなかったはずだ。それなのにこの本はやたらと厚くて大きく、タイトルに対して不釣り合いな重さをしている。装丁だってあまりにも豪華だ。
ふむ、と呟きながら本を持ち上げる。不思議なことに、中で何かが転がるような音がした。
何か入っているのだろうか。そう思った魔理沙は表紙に手を掛けるが――
「ん!? 開かない……」
表紙をめくろうとしたが、びくともしない。裏から開こうとしても、真ん中あたりのページを開けようとしても、まるで接着されたかのように動かない。あれこれと格闘している魔理沙を見て、パチュリーはため息交じりの声を出した。
「そうなの。封印魔法がかかっているみたいで。別に解除するのは難しくなさそうなんだけど」
そう言って、彼女は魔理沙が持つ本に指を伸ばした。だが魔理沙が慌ててそれを防ぐように抱え込む。
「わぁ、待て待て!」
「どうしたの」
「いやこれ、普通じゃないぜ。当たり前だろうけど、小鈴もこの本開けなかったんだろ?」
「そうでしょうね」
「どうせ外から流れ着いた外来本だろうが、ただの童話に封印魔法? さすがに怪しすぎるぜ。ていうか、小鈴はこの展開を期待してるんじゃないのか?」
魔理沙の言葉を咀嚼するように、パチュリーを人差し指を顎に当て、頭を傾ける。
「まあ……私たちに封印を解かせた後で、ウッキウキで本を引き取りにくるんじゃないかしら」
「だろうな。さらにお前から貸本料まで回収できるおまけつきだ。隙が無いったら」
二人はうーんと唸り、他に誰もいない図書館に静寂が流れた。
開ければ小鈴の掌の上。それはなんとなく癪に障る気がする。なら開けなければよいのだが、封印魔法まで施された代物を目の前にして、それに触れないというのも気が収まらない。
魔法使いは、目の前の不思議を放っておけないものなのだから。
「……別に、小説になんか興味ないけど」
「そうだな。私たちは、本の中身が気になるだけさ」
誰にしているのかわからない言い訳を二人で並べた後、改めてパチュリーは本の表紙をその指で撫でる。大きく、赤い表紙の本は、くすぐったそうに身を震わせると、魔理沙の手を離れてふわりと浮き上がった。
パチンと、何かが弾けるような小さな音がした。次の瞬間、表紙がひとりでに、滑らかに開く。
「おお?」
魔力の残滓でキラキラと光る紙。魔理沙は吸い込まれるように、それを覗き込んだ。
中表紙に書かれている物語の出だしは、間違いなくジャックと豆の木のようだ。しかしそれより目を引くのは、分厚い表紙側を切り抜いたかのようなスペースに埋め込まれた、大きな丸いもの。
「どうやら、こっちが私たちのお目当てみたいだな」
「種、かしらね。封印されていたものの正体がこれってことね」
パチュリーはその種を本から摘まみ上げると、無造作に床に転がした。魔理沙が驚く間もなく、彼女は指を振って呪文を唱える。
――日水木符「グローリーグロウ」
一級成長呪文。このスペルの対象となった植物は、メキメキと細胞分裂を繰り返してあっという間に花を咲かせる――はずなのだが、種は何の反応も示さず、図書館には変わらずの静寂が流れていた。
五秒。十秒。十五秒――
やがてその沈黙に耐えかねたらしい魔理沙が、呆れたように言う。
「あのな、パチュリー。植物の成長にはまず土が必要で……」
「う、うるさいわね。わかってるわ」
自分でも性急だったと思ったのか、パチュリーは耳を赤くしている。
「にしてもだ。本当にこれが伝説の豆の木だとしたら、成功しなくてよかったな。もし上手くいってたら、今頃天井をぶち抜いて、咲夜が気絶するだろうぜ」
「はいはい。じゃ、これはあなたにあげるから」
冗談を飛ばす魔理沙に対し、パチュリーは種を拾い上げて彼女に押し付けようとする。それほどまでに先ほどの出来事を水に流したいのか、それとも開かない本の中身がわかって本当に興味を失ったのか。
「えー、なんでだよ」
「いや、別に。土がね、種に必要なのはわかってるわ。そう、わかってたのよ。でも多分、これは勘だけれど、それもただの土じゃダメだと思うの。魔法の本から出てきた種だもの。きっとそれが育つ土も、魔力に満ちたものでないと」
「ああ、なるほど」
魔理沙は、納得いったように手をポンと叩いた。
「魔法の森なら!」
「そういうこと。もし上手く育ったら、天狗でも呼んで写真でも撮ってもらったら?」
じゃ、と言って会話を切り上げようとするパチュリー。だが魔理沙は口を尖らせて食い下がる。
「何言ってんだよ。一緒に行こうぜ」
「嫌よ。外になんて出たくないし。別に豆の木になんて興味は……」
「でも、魔法の種だろ?」
小説になんて興味ない。だが本から転がり出てきた魔法の種が、どういう風に成長するのか、見たくないと言えば。
「……仕方ない」
魔法の森。
暗い。湿度が高い。化け物キノコが歩いて通る。
およそ人間が好んで近づくような場所ではない。
だが普通の魔法使い、霧雨魔理沙はここを選んで住んでいる。扱っている魔法薬の材料が手に入りやすいため、と彼女は言うが、その本心は誰も知らない。だがこれから植えるものがその材料の一つに加わる可能性は、大いにあるだろう。
「さて」
魔理沙は鬱蒼とした森の中で少しでも開けた場所を探し、いくらか掘り返して土を柔らかくした後で、そこに種を埋め込んだ。そして家から持ってきていた大きな袋を肩に担ぐと、思い切りそれを種の上へとまいていく。
「ここで魔法の肥料を一袋っと」
「何が入ってるの、それ」
「どうしても知りたかったら教えるけど、後で聞かない方がよかったってぼやいても知らないぜ」
「そ。じゃあ聞かない」
パチュリーはあっさりと引き下がると、その代わりに種が埋まった土に目を向けた。
「……どうなるんだっけ?」
「なにが?」
「豆の木。育つんでしょ? お話の中では、その後どうなるんだっけって聞いたの」
魔理沙も、同じように土を見る。それから、豆の木が育つであろう空を見て、こう言った。
「そりゃあ、私の口から聞くよりも、自分で読んだ方がいいんじゃないか? せっかく実物があるんだし」
それはそうだ。パチュリーは頭の中で納得しつつ、口では「意地悪ね」とこぼす。それから彼女は成長魔法を唱えて、その指を振った。
さっきとは違う、美しい魔力の光が指から流れて、種に降り注いでいく。
途端、地響きが鳴り、メキメキと地面が盛り上がり始めた。
「わっ」
慌てて二人は距離を取る。その瞬間、巨大な蔓がいくつも絡み合い、太い幹になって爆発するように上へと延びていった。
景色が揺れる。目まぐるしく変わる。立っていられないほどの振動に耐えかねて、二人は空へと飛びあがる。
そこで見たものは、土煙を押しのけるようにして天へと伸びる、大きな木。その伸び方は、まるでプログラムされているかのように迷いなく、上へ、上へ、上へ。
「すごい!」
そんな短い言葉しか言えなかった。伸び続ける木の先を追いかけるようにして、二人も空を駆ける。
景色を変えていく。
周りを変えていく。
森を巻き込んで。
驚いて飛んだ鳥たちの隙間を縫うように。
「どこまでのぼるんだ? うっかり落ちたら死にかねないぜ」
箒を駆る魔理沙は、勢いよく上がる木を睨む。だが、その背中を追いかけるように飛ぶパチュリーは、自分の体に無視できない違和感を感じていた。
「ゴホッ……」
心の中で、舌打ちしそうになる。急に身体を動かしたせいか、それとも木が起こした土埃が気管に入ったか。喘息の影が見え隠れする。
魔力の流れが、僅かに乱れた。慣れきった、「飛ぶ」という行動に支障がでるほどじゃない。しかしそれは木の成長に追いつくくらいに「早く飛ぶ」ことに対しては、確実に影響を与えていた。
上を見上げる。空に浮かぶいくつかの雲。そのどれかを目指して、木は伸び続けているのだろうか。
いや、別に。そんなに一生懸命追いかけなくても。元々、魔法の種が育つところを見れたらって思って。それだけ。
ふと、速度が緩む。それと同時に、悲鳴を上げそうになっていた気管支が落ち着く。
だから、いいよ。別に、それで。
心の中でそう言った瞬間、彼女に射していた太陽の光が遮られた。
「――ほら!」
気が付くと、先を行っていたはずの魔理沙が手を伸ばしていた。
それをみて。
どうしてとか。
もういいよとか。
そういうことは、考えなかった。
出された手を、掴む。当たり前みたいに。
「いくぜ!」
魔理沙はパチュリーの手を引いて、どんどん速度を増していく。重力に逆らう弾丸のように、彼女たちは天へと走る。
彼女の手を借りて、パチュリーは木の先端まで追いついた。しかしそれは、今もすごい速さで伸び続けていく。
「なあ、話の中だと、ジャックは雲の上の城に着いたんだってさ!」
魔理沙の声が流れていく。
「でも、空もいいけど、私は星の方が好きなんだよな。もっとずっと伸びてさ、他の星まで届くような木になったらどうしようか!」
弾むような少女の声。
宇宙が、とか。空気が、とか。そんなことを聞くのは、意味がなかった。
「いいんじゃない。お話を、小説を超えるものがあっても。魔法なら、それができるかも」
パチュリーの言葉に、魔理沙は「そうだよな」と返す。
地から空へ。星の海へ。
小説で終わらない、雲の向こうへ。
木がどこまで伸びていったのか、それは二人だけが知っている。